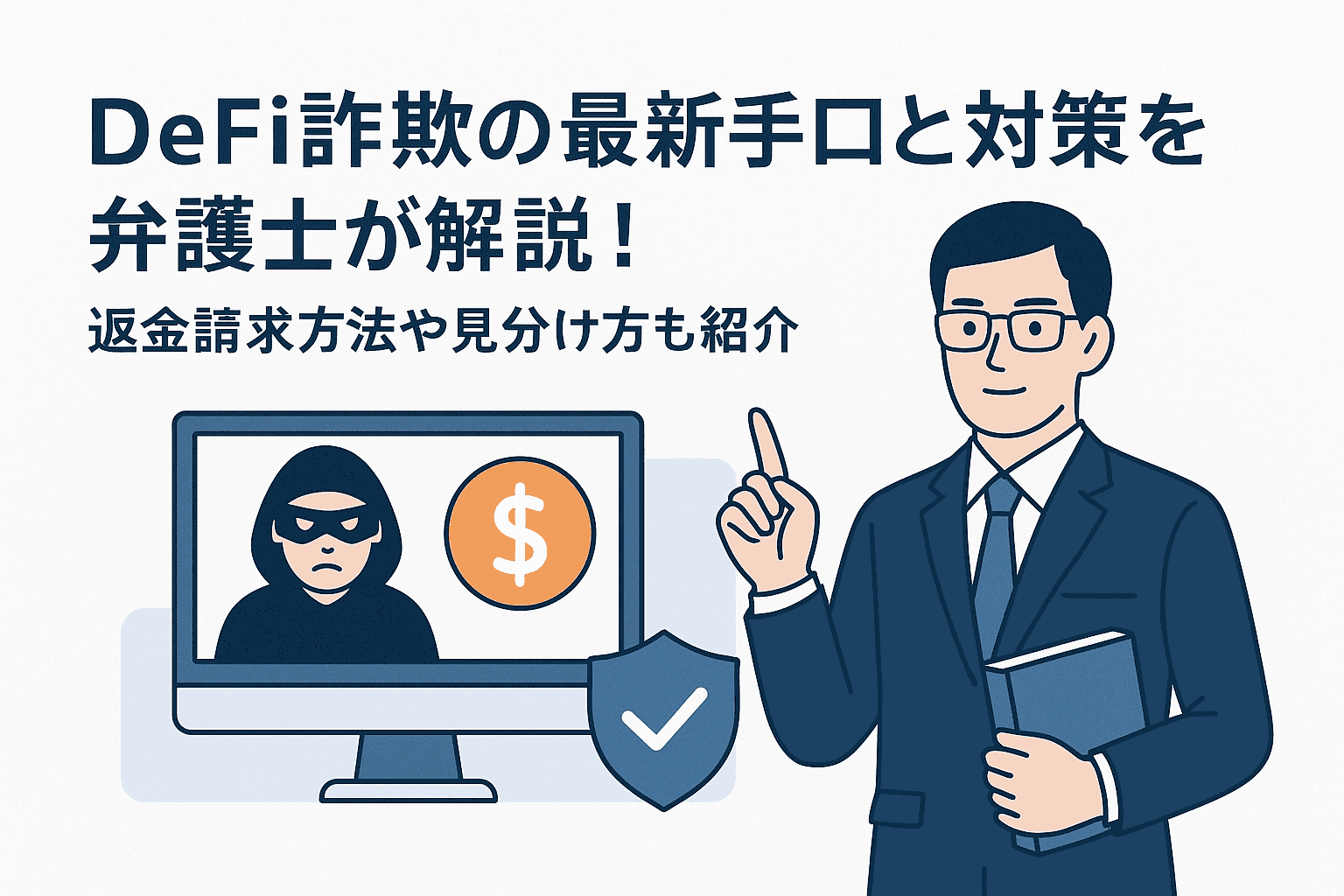DeFi(分散型金融)は、新しい資産運用の形として大きな可能性を秘めている一方、その匿名性や技術的な複雑さを悪用した詐欺が後を絶ちません。「高利回りを謳うプロジェクトに投資したが、突然資金が引き出せなくなった」「知らないうちにウォレットから仮想通貨が抜き取られていた」といった被害相談は、残念ながら増加傾向にあります。
DeFiポートフォリオを確認するたびに、自分の資産が本当に安全なのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。また、すでに何らかの被害に遭い、どうすれば良いかわからず途方に暮れている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、DeFi詐欺の典型的な手口から、詐欺プロジェクトを見抜くための具体的なチェックポイント、そして万が一被害に遭ってしまった場合の初動対応や相談先まで、網羅的に解説します。
この記事を最後まで読むことで、DeFi詐欺に対する正しい知識と対処法が身につき、冷静な判断のもとでご自身の資産を守るための具体的な一歩を踏み出せるようになります。もし今、お一人で悩みを抱えているのであれば、この記事が解決の糸口となれば幸いです。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
DeFi詐欺とは何か?
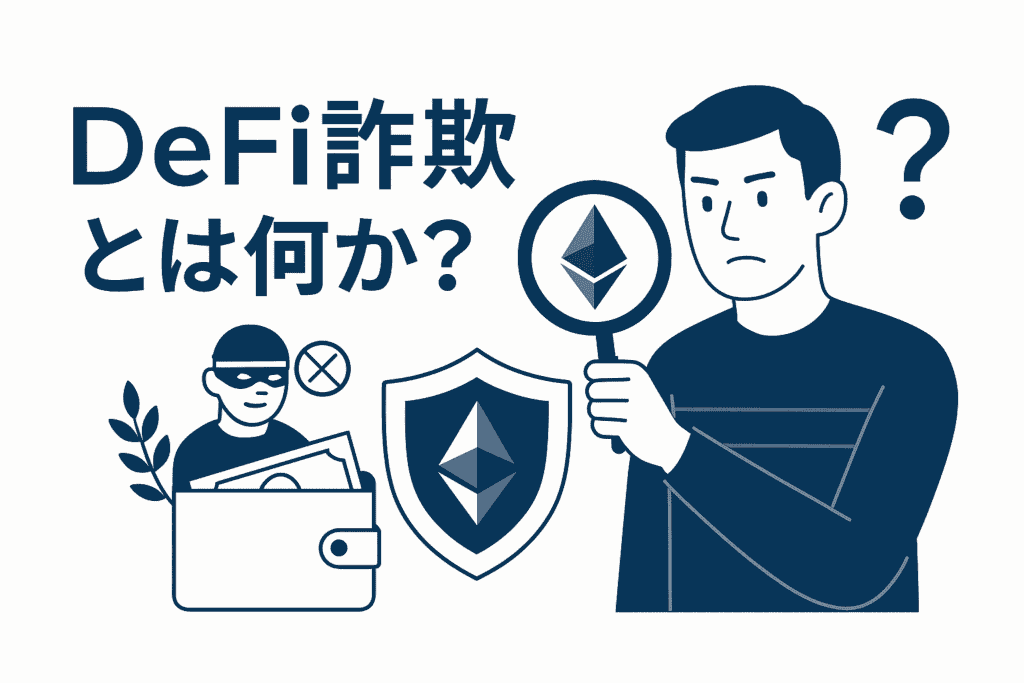
DeFi詐欺とは、DeFiの仕組みを悪用して投資家から不正に仮想通貨をだまし取る行為の総称です。その手口は年々巧妙化しており、欧州証券市場監督局(ESMA)もその運用上の脆弱性について警告しています。運営者が突然資金を持ち逃げしたり、偽の投資アプリを使わせたりと、その手口は様々です。
この記事では、DeFi詐欺の中でも特に被害の多い手口や、資産管理ツールを装った詐欺について、以下の点で詳しく解説していきます。
- DeFi詐欺仮想通貨で多い典型的な手口
- DeFiポートフォリオ詐欺の特徴と被害事例
DeFi詐欺仮想通貨で多い典型的な手口
仮想通貨を狙ったDeFi詐欺には、いくつかの典型的な手口が存在します。これらの手口を知ることは、詐欺被害を防ぐための第一歩です。
最も古典的で有名なのが「ラグプル(Rug Pull)」です。これは、プロジェクト運営者が投資家から集めた資金を十分に集めた段階で、突然プロジェクトを放棄し、資金を持ち逃げする手口を指します。カーペット(Rug)を引く(Pull)ように、足元をすくわれる様からこの名がついています。
また、近年増加しているのが、偽のウェブサイトやアプリに誘導してウォレットを接続させ、資産を抜き取る「フィッシング詐欺」です。特に、スマートコントラクトの承認機能(Approve)を悪用する「アプルーバル詐欺」は巧妙で、一度承認を与えてしまうと、知らないうちに継続的に資産を盗まれる危険性があります。
その他にも、以下のような手口が確認されています。
- ハニーポット: 投資した資金は引き出せない仕組みになっている詐欺的なスマートコントラクト。
- アイスフィッシング: 偽のアドレスを表示させ、誤った宛先に送金させる手口。
- 豚の屠殺詐欺: SNSなどで長期間にわたり信頼関係を築き、最終的に偽の投資話に誘導して大金をだまし取る手口。警察庁もSNS型ロマンス詐欺として注意喚起しています。
これらの手口は単独ではなく、複合的に使われることも多いため、十分な警戒が必要です。
DeFiポートフォリオ詐欺の特徴と被害事例
DeFiポートフォリオ詐欺は、投資家が自身の資産状況を確認・管理するために利用する「ポートフォリオ管理ツール」を装って近づいてくる、非常に悪質な手口です。
この詐欺の主な特徴は、公式のツールやアプリとそっくりな偽サイト・偽アプリを用意し、ユーザーを巧みに誘導する点にあります。例えば、検索エンジンの広告枠やSNSの投稿を通じて偽サイトにアクセスさせ、ウォレットの連携や秘密鍵の入力を促します。一度入力してしまうと、ウォレット内の全資産が攻撃者の手に渡ってしまうリスクがあります。
実際の被害事例として、「有名なポートフォリオ管理ツールのアップデートを装った通知が届き、リンク先のサイトで秘密鍵を入力したところ、数分後にウォレット内の仮想通貨がすべて盗まれた」というケースが報告されています。また、「高機能なポートフォリオ分析ができるという触れ込みの新しいアプリをダウンロードし、ウォレットを連携させたところ、特定のトークンに対する無制限の引き出し許可(アプルーバル)を与えてしまい、資産を失った」という事例もあります。
これらの詐欺は、ユーザーの「資産状況を正確に把握したい」という心理を巧みに利用します。見慣れたロゴやデザインであっても、安易に信用せず、公式サイトのURLであるかをブックマークから確認するなど、慎重な行動が求められます。
DeFi詐欺を見抜くためのチェックポイント

DeFi詐欺の被害に遭わないためには、詐欺プロジェクトや危険なサイトを自らの力で見抜くことが不可欠です。詐欺師は巧みな言葉で投資を誘ってきますが、その多くには共通する危険なサインが隠されています。
ここでは、詐欺を見抜くための具体的なチェックポイントを4つの観点から解説します。
- 高利回り保証や元本保証をうたう危険サイン
- 出金時に追加金を要求する手口
- ウォレット連携・秘密鍵入力を求められる場合のリスク
- 偽ポートフォリオ管理ツール・偽アプリの見分け方
これらのポイントを常に意識することで、詐欺被害に遭うリスクを大幅に減らすことができます。
高利回り保証や元本保証をうたう危険サイン
「月利30%保証」「元本は絶対に保証します」といった甘い言葉は、DeFi詐欺の最も典型的な危険サインです。消費者庁も「必ず値上がりする」といった勧誘文句に注意するよう呼びかけています。
DeFiを含むすべての投資において、リターンとリスクは表裏一体の関係にあります。高いリターンが期待できるものは、それ相応の高いリスクを伴うのが原則です。そのため、「高利回り」と「元本保証」が両立することは、投資の世界では基本的にあり得ません。このような非現実的な条件を提示してくるプロジェクトは、詐欺である可能性が極めて高いと判断すべきです。
特に、以下のような謳い文句には注意が必要です。
- 具体的な根拠なく、異常に高い利回りを提示する
- 「ノーリスク」「絶対に損はしない」といった言葉で安心させようとする
- 紹介制度などを設けて、友人や家族を巻き込むよう勧誘してくる
詐欺師は、投資家の「楽して儲けたい」という射幸心を煽ってきます。魅力的な言葉に惑わされず、投資の基本原則に立ち返り、冷静にプロジェクトの内容を分析することが重要です。少しでも「話がうますぎる」と感じたら、それは詐欺を疑うべき最初のサインです。
出金時に追加金を要求する手口
投資した資金を引き出そうとした際に、「税金の支払いが必要」「手数料が不足している」など、様々な名目で追加の入金を要求してくるのは、詐欺の典型的な手口です。金融庁も同様の手口について注意喚起しており、絶対に応じないよう呼びかけています。
この手口では、最初はスムーズに利益が出ているように見せかけ、投資家を信用させます。そして、いざ出金しようとすると、次から次へと言い訳をつけて追加の支払いを求めてきます。しかし、これは投資家からさらにお金をだまし取るための罠であり、要求通りに追加の資金を支払っても、結局出金できることはありません。
出金時に追加の支払いを要求された場合の正しい対処法は、「一切支払いに応じず、すぐに関係を断つこと」です。一度でも支払いに応じてしまうと、「この人はまだお金を出す」と判断され、さらに執拗な要求が続く可能性があります。
「これを支払えば全額戻ってくる」という言葉は、詐欺師が使う常套句です。損失を取り戻したいという気持ちは分かりますが、さらなる被害を防ぐためにも、冷静に状況を判断し、きっぱりと要求を拒否する勇気が求められます。
ウォレット連携・秘密鍵入力を求められる場合のリスク
ウォレットの「秘密鍵(シークレットリカバリーフレーズ)」は、金庫の鍵そのものであり、絶対に他人に教えてはいけない情報です。いかなる理由があっても、ウェブサイトやアプリ、他人に秘密鍵の入力を求められた場合は、100%詐欺だと断定してください。
秘密鍵が漏洩すると、攻撃者はあなたのウォレットを完全にコントロールできるようになり、いつでも自由に資産を盗み出すことが可能になります。DeFiプロジェクトやDApps(分散型アプリケーション)が、ユーザーの秘密鍵を要求することは絶対にありません。
また、ウォレットをサイトに連携(Connect)する際の「署名(Sign)」や「承認(Approve)」にも注意が必要です。内容をよく確認せずに承認してしまうと、意図せずして資産の引き出し許可を攻撃者に与えてしまう可能性があります。
特に警戒すべきなのは、以下のようなケースです。
- エアドロップや懸賞の受け取りを理由に、秘密鍵の入力を求めてくる
- テクニカルサポートを装い、問題解決のために秘密鍵が必要だと説明してくる
- ウォレット連携時に、内容が不審な(例:「Set Approval For All」)トランザクションの承認を求めてくる
秘密鍵は誰にも見せず、厳重にオフラインで保管することが鉄則です。ウォレット連携時の要求は、その内容を十分に理解・確認してから承認するようにしてください。
偽ポートフォリオ管理ツール・偽アプリの見分け方
偽のポートフォリオ管理ツールやアプリは、公式サイトや公式アプリと見分けがつきにくいように巧妙に作られています。しかし、注意深く観察すれば、いくつかの点から偽物であることを見抜くことが可能です。
まず最も重要なのは、公式サイトのURLを必ず確認することです。検索エンジンの検索結果や広告、SNSのリンクからアクセスするのではなく、信頼できる情報源(CoinMarketCapやCoinGeckoなど)からリンクを辿るか、事前にブックマークしておいた公式サイトからアクセスする習慣をつけましょう。URLが公式のものとわずかに違う(例えば、文字が一つ違う、ドメインが異なるなど)場合は、フィッシングサイトの可能性が高いです。
また、アプリの場合は、公式のアプリストア(App Store, Google Play)からダウンロードすることが基本です。開発元が信頼できるか、レビューの内容は不自然でないかを確認しましょう。極端にレビューが少ない、あるいは不自然な高評価ばかりが並んでいる場合は注意が必要です。
さらに、以下の点もチェックポイントとなります。
- サイトのデザインや日本語に不自然な点はないか
- アプリが過剰な権限(パーミッション)を要求してこないか
- 秘密鍵やシードフレーズの入力を求めてこないか
これらのポイントを総合的に確認し、少しでも怪しいと感じたら、利用を中止するのが賢明です。
DeFi詐欺に遭った場合に被害を最小化するための初動対応
どれだけ注意していても、巧妙な手口によってDeFi詐欺の被害に遭ってしまう可能性はゼロではありません。万が一被害に遭った、あるいは被害に遭ったかもしれないと気づいた場合、パニックにならず、迅速かつ冷静に初動対応を行うことが、被害の拡大を防ぐ鍵となります。
被害を最小限に食い止めるためには、以下の3つの行動が重要です。
- すぐに行うべき行動(送金停止・権限取り消し・残資産移動)
- 証拠保全の方法(トランザクションID・やり取り記録・スクリーンショット)
- 連絡遮断と二次被害防止のための注意点
すぐに行うべき行動(送金停止・権限取り消し・残資産移動)
DeFi詐欺の被害に気づいたら、一刻も早く行動を起こし、さらなる資産の流出を防がなければなりません。
まず、進行中の送金や、詐欺サイトとのウォレット連携が疑われる場合は、直ちに送金を停止し、サイトとの接続を解除してください。
次に、最も重要なのが「コントラクトの権限取り消し(Revoke)」です。詐欺サイトに対して、あなたのウォレット内の資産を動かす権限(アプルーバル)を与えてしまっている可能性があります。Revoke.cashのような専門ツールを使い、心当たりのない、あるいは不審なコントラクトへのアクセス許可をすべて取り消してください。これにより、今後の不正な引き出しを防ぐことができます。
そして、権限の取り消しが完了したら、被害に遭ったウォレットに残っているすべての資産を、新しく作成した安全なウォレットに速やかに移動させます。一度でも攻撃者に狙われたウォレットを使い続けるのは非常に危険です。手間はかかりますが、必ず新しいウォレットを用意し、そちらで資産を管理するようにしてください。
これらの行動は、時間との勝負です。被害の覚知からいかに早く対応できるかが、残存資産を守れるかどうかを左右します。
証拠保全の方法(トランザクションID・やり取り記録・スクリーンショット)
被害後の調査や法的手続きに進むためには、客観的な証拠が不可欠です。冷静さを保ち、できるだけ多くの証拠を保全するように努めてください。
まず、ブロックチェーン上に記録されている情報は、改ざん不可能な最も強力な証拠となります。被害に遭ったトランザクションのID(TxID)やハッシュ値、詐欺師のものと思われるウォレットアドレスなどを、ブロックチェーンエクスプローラー(Etherscanなど)で確認し、必ず記録しておきましょう。
次に、詐欺師とのやり取りの記録も重要な証拠です。SNSのダイレクトメッセージ、メール、チャットアプリでの会話履歴など、相手とのコミュニケーションの記録は、すべてスクリーンショットやデータのエクスポート機能を使って保存してください。相手のアカウント情報(IDやプロフィール画面)も忘れずに保存しておきましょう。
さらに、詐欺サイトのURLやサイトの画面、偽アプリの情報など、被害に繋がったウェブサイトやアプリケーションに関する情報もスクリーンショットで保存します。
これらの証拠は、後に警察や弁護士に相談する際に、状況を正確に伝え、調査を進めるための極めて重要な資料となります。可能な限り詳細に、そして網羅的に情報を集めることを心がけてください。
連絡遮断と二次被害防止のための注意点
被害に遭った後、詐欺師から「資金を取り戻すために追加の支払いが必要だ」といった連絡が来ることがありますが、これはさらにお金をだまし取ろうとする二次被害の罠です。絶対に相手の要求には応じず、直ちに連絡を遮断してください。SNSのアカウントをブロックし、着信を拒否するなど、相手との接触を完全に断つことが重要です。
また、「ハッキングされた資金を取り戻す」と謳う別の業者や個人からアプローチがある場合も注意が必要です。被害者の弱みにつけ込み、高額な調査費用を請求する新たな詐欺である可能性が高いです。
一度被害に遭うと、冷静な判断が難しくなりがちですが、「失ったお金を取り戻したい」という気持ちを逆手に取られないよう、警戒心を緩めてはいけません。
公的機関や正規の弁護士事務所以外からの「救済」の申し出は、まず疑ってかかるべきです。これ以上の被害を防ぐためにも、詐欺師との接触は完全に断ち、信頼できる専門家のみに相談するようにしてください。
DeFi詐欺被害の相談先と法的対応
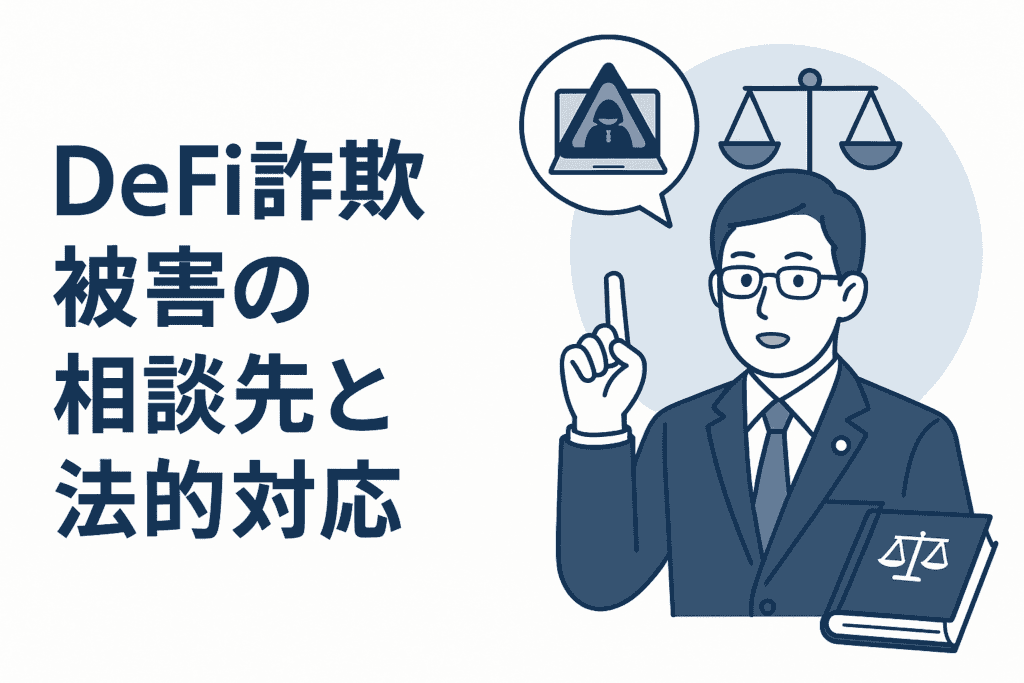
DeFi詐欺の被害に遭ってしまった場合、一人で抱え込まずに専門機関に相談することが、問題解決に向けた重要な一歩です。どこに、何を準備して相談すれば良いのかを事前に知っておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
主な相談先としては、以下の3つが挙げられます。
- 警察への被害届と相談時の準備
- 消費生活センター・金融庁など公的窓口の活用方法
- 弁護士への相談と回収可能性の現実
それぞれの機関の役割を理解し、ご自身の状況に合わせて適切な相談先を選ぶことが大切です。
警察への被害届と相談時の準備
DeFi詐欺は、詐欺罪や不正アクセス禁止法などに該当する可能性のある犯罪行為です。そのため、被害に遭った場合は、警察に相談し、被害届を提出することを検討してください。
最寄りの警察署、または各都道府県警察に設置されている「サイバー犯罪相談窓口」に連絡するのが第一歩です。相談に行く際は、事前に電話でアポイントを取り、必要な持ち物を確認しておくとスムーズです。
相談時には、これまでに収集した証拠をすべて持参しましょう。
- 被害の経緯を時系列でまとめたメモ
- トランザクションID、相手のウォレットアドレスなどの情報
- 詐欺師とのやり取りの記録(スクリーンショット等)
- 詐欺サイトのURLや画面のスクリーンショット
- 被害額がわかる資料(取引所の履歴など)
これらの資料を基に、担当者に状況をできるだけ正確に、かつ具体的に説明することが重要です。警察が捜査を開始することで、犯人逮捕や、国内の取引所などに残っている犯罪収益の凍結に繋がる可能性があります。ただし、必ずしも捜査が開始されるとは限らない点、また犯人特定や被害回復には時間がかかる点も理解しておく必要があります。
消費生活センター・金融庁など公的窓口の活用方法
警察への相談と並行して、他の公的窓口を活用することも有効です。
「消費生活センター(消費者ホットライン「188」)」は、商品やサービスの契約に関するトラブル全般について相談できる窓口です。DeFi詐欺の中でも、特に事業者との間で生じたトラブルについて、今後の対応方法や専門機関への紹介などの助言をもらうことができます。
また、詐欺的なプロジェクトが、金融商品取引法における「暗号資産交換業」の登録を受けずに日本国内で営業を行っている場合、それは法令違反となります。「金融庁・金融サービス利用者相談室」に情報提供を行うことで、当局による行政処分や注意喚起に繋がり、新たな被害者の発生を防ぐ効果が期待できます。
これらの公的窓口は、直接的な被害回復を行う機関ではありませんが、問題解決のための情報提供や、社会的な注意喚起を促すという重要な役割を担っています。ご自身の被害事例を報告することは、同様の詐欺を根絶するための一助となります。
弁護士への相談とメリット
被害金の回収を具体的に目指す場合、仮想通貨やDeFiの案件に詳しい弁護士への相談が最も有効な手段となります。
弁護士は、法的な観点からあなたの代理人として、犯人特定や被害回復のための専門的な手続きを進めることができます。例えば、以下のような対応が可能です。
- 発信者情報開示請求: 国内の取引所などを通じて、詐欺師の個人情報を特定する手続き。
- 口座凍結の要請: 犯人が利用している取引所の口座を凍結し、資産の移動を防ぐ。
- 損害賠償請求訴訟: 犯人が特定できた場合に、民事訴訟を提起して被害金の返還を求める。
弁護士に相談する際は、まず無料相談などを利用し、ご自身のケースにおける回収の可能性や、依頼した場合の弁護士費用について、率直な見通しを確認することが重要です。
弁護士法人FDR法律事務所では、DeFi詐欺に関するご相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
詐欺に遭わないための安全なDeFi運用方法
DeFi詐欺に遭わないためには、安全なDeFiの運用方法を学び、実践することが不可欠です。日頃からの少しの注意と対策が、将来の大きな損失を防ぎます。
ここでは、DeFi資産を安全に管理し、詐欺から身を守るための具体的な方法を解説します。
- コントラクト権限管理と定期的な確認
- ポートフォリオ管理の安全なやり方
- 無登録業者・無監査プロジェクトを避ける判断基準
これらの習慣を身につけ、安全なDeFiライフを送りましょう。
コントラクト権限管理と定期的な確認
DeFiを利用する上で、スマートコントラクトに対する「権限(アプルーバル)」の管理は、セキュリティの根幹をなす非常に重要な要素です。
DEX(分散型取引所)などでトークンを交換する際、私たちはそのDEXのコントラクトに対して、自分のウォレットからトークンを引き出すことを許可しています。この許可が悪用されると、アプルーバル詐欺に繋がります。
このリスクを管理するためには、定期的に自分のウォレットがどのコントラクトに、どのような権限を与えているかを確認し、不要な権限を取り消す(Revokeする)習慣が不可欠です。Revoke.cashやEtherscanのToken Approvals Checkerといったツールを利用すれば、簡単に権限の状況を確認し、不要なものを数クリックで取り消すことができます。
特に、以下のような権限はリスクが高いため、利用が終わったら速やかに取り消すことを推奨します。
- 無制限の許可(Unlimited Approval)
- 長期間利用していない、あるいは信頼性が不明なプロジェクトへの許可
月に一度など、定期的な「権限の棚卸し」をスケジュールに組み込むことで、ウォレットを常にクリーンな状態に保ち、アプルーバル詐欺のリスクを大幅に低減させることができます。
ポートフォリオ管理の安全なやり方
複数のDeFiプロトコルやブロックチェーンに資産を分散させている場合、ポートフォリオ管理ツールの利用は非常に便利です。しかし、その利便性の裏には、偽サイトや偽アプリによる詐欺のリスクが潜んでいます。
安全にポートフォリオを管理するための鉄則は、「View-Only(閲覧専用)」機能を活用することです。多くのポートフォリオ管理ツールでは、ウォレットアドレスを入力するだけで、そのアドレスが保有する資産や取引履歴を閲覧できます。この方法であれば、ウォレットをサイトに接続したり、秘密鍵を入力したりする必要がないため、資産が盗まれるリスクはありません。
取引やステーキングなど、実際にウォレットの操作が必要な場合は、必ず公式サイトから直接アクセスするようにしてください。
また、セキュリティをさらに高めるためには、「ホットウォレット」と「コールドウォレット」の使い分けも有効です。日常的に少額の取引を行うためのホットウォレットと、長期保有する大部分の資産を保管しておくためのオフラインのコールドウォレット(ハードウェアウォレットなど)を分けることで、万が一ホットウォレットが攻撃されても、被害を最小限に抑えることができます。
無登録業者・無監査プロジェクトを避ける判断基準
投資対象となるDeFiプロジェクトを選ぶ際には、その信頼性と安全性を自分自身で調査・判断する「DYOR(Do Your Own Research)」の精神が何よりも重要です。
まず、日本国内で暗号資産交換業や金融商品取引業を行うには、金融庁への登録が必要です。海外の事業者であっても、日本人向けにサービスを提供している場合は登録対象となります。金融庁のウェブサイトで「暗号資産交換業者登録一覧」を確認し、無登録の業者ではないかをチェックしましょう。無登録業者は、詐欺やトラブルのリスクが非常に高いと考えられます。
また、プロジェクトの技術的な安全性を判断する上で、第三者機関による「スマートコントラクトの監査(Audit)」を受けているかどうかは、米国財務省も推奨する重要な判断基準の一つです。CertiKやConsenSys Diligenceといった信頼できる監査会社による監査レポートが公開されているかを確認しましょう。監査を受けているからといって100%安全というわけではありませんが、監査を受けていないプロジェクトは、技術的な脆弱性を抱えている可能性が高く、投資対象としては避けるべきです。
その他、開発チームの経歴が公開されているか、コミュニティ(DiscordやTelegram)が活発で健全か、といった点も、プロジェクトの信頼性を測る上で参考になります。
DeFi詐欺に遭ったら弁護士法人FDR法律事務所へ
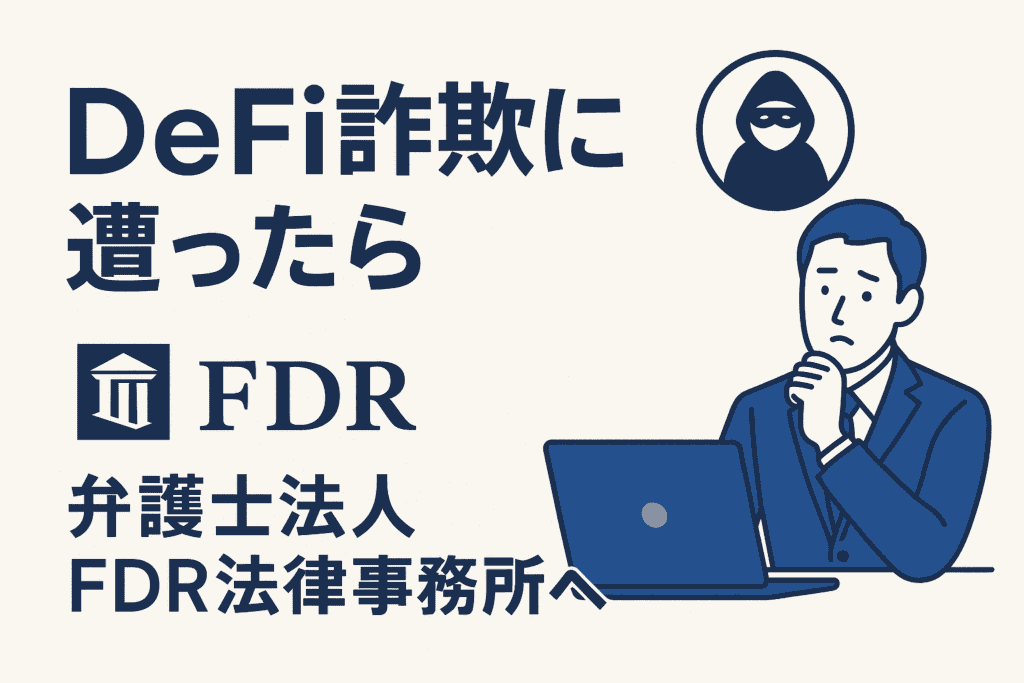
この記事では、DeFi詐欺の手口から対策、被害後の対応まで詳しく解説してきました。しかし、実際に被害に遭ってしまうと、冷静な判断が難しく、一人で対応するのは精神的にも大きな負担となります。
もし、あなたがDeFi詐欺の被害に遭い、どうすれば良いか分からず悩んでいるのであれば、どうか一人で抱え込まないでください。
弁護士法人FDR法律事務所は、仮想通貨やDeFi、NFTといったブロックチェーン技術が関わる詐欺被害の案件を専門的に取り扱っており、豊富な知識と経験を有しています。
私たちは、被害に遭われた方のお気持ちに寄り添いながら、法的な観点から被害回復の可能性を検討し、最善の解決策をご提案します。犯人の特定から資金の追跡、そして損害賠償請求まで、専門家としてあなたを力強くサポートします。
初回のご相談は無料です。「弁護士に相談するのは敷居が高い」と感じる必要は一切ありません。まずは、あなたの状況をお聞かせください。被害金の回収は時間との勝負です。少しでも早くご相談いただくことが、解決への第一歩となります。
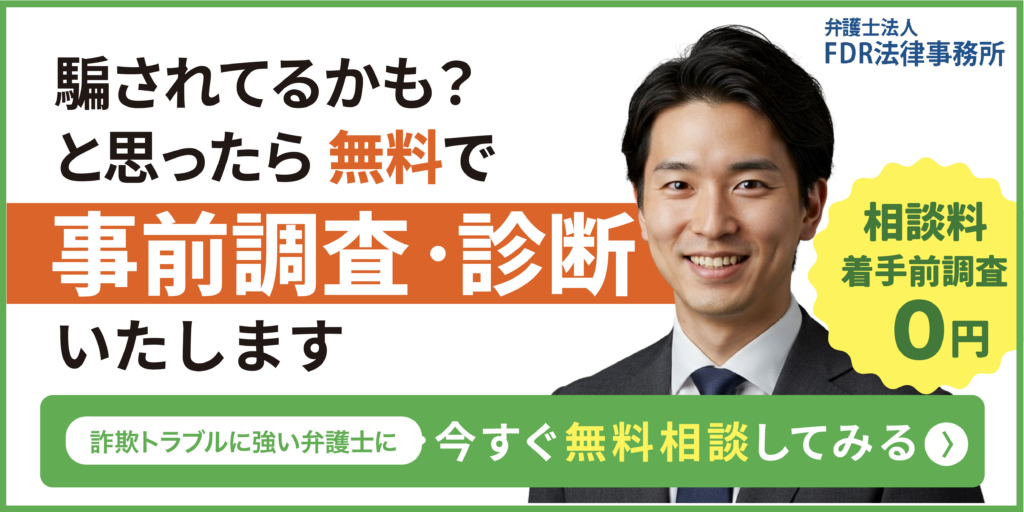
\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます