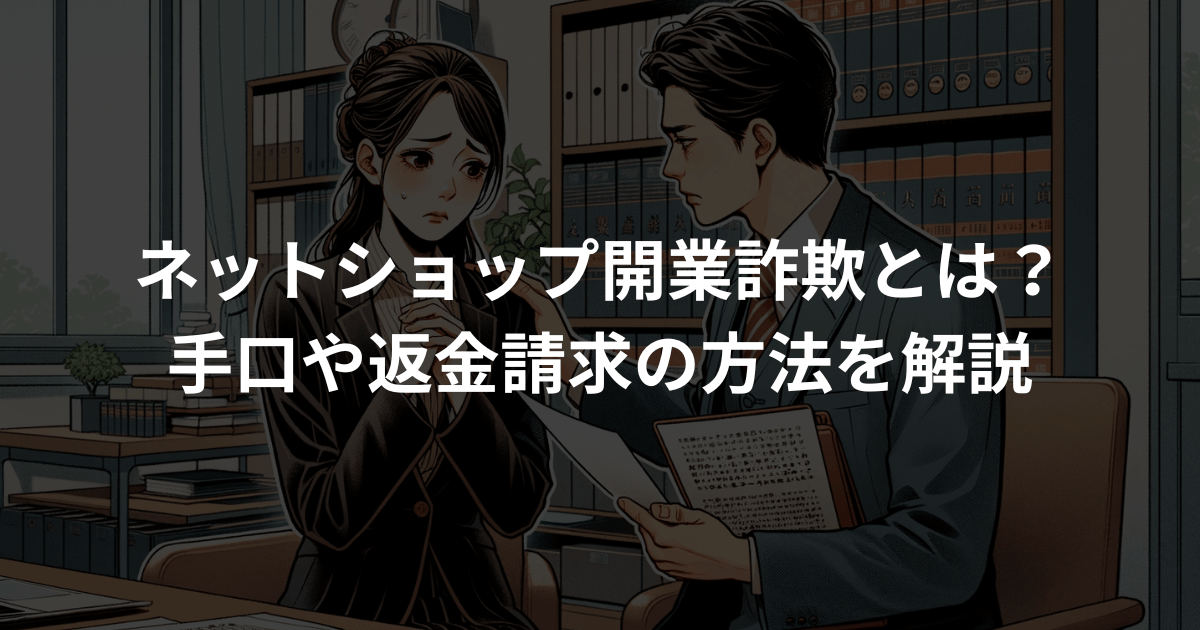「スマホ一つで簡単に稼げる」「未経験から月収100万円」。そんな魅力的な言葉に惹かれ、ネットショップの開業に興味を持ったものの、「これって本当に安全なの?」「もしかして詐欺じゃないか?」と一歩踏み出せずにいませんか。
その直感は非常に重要です。残念ながら、ネットショップ開業の夢に付け込む悪質な詐欺は数多く存在し、特に「ドロップシッピング」という仕組みを悪用した手口で多額の金銭をだまし取られる被害が後を絶ちません。
この記事では、ネットショップの出店や開業に潜む詐欺について、その具体的な手口から、危険な業者を即座に見抜くためのチェックリスト、そして万が一被害に遭ってしまった場合の正しい対処法まで、網羅的に解説します。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
ネットショップの出店・開業詐欺とは?ドロップシッピングを悪用した危険な手口

ネットショップの開業や出店にまつわる詐欺は、言葉巧みに被害者を誘導し、様々な名目で金銭をだまし取る犯罪です。特に、在庫を持たずに商品を販売できる「ドロップシッピング」の仕組みが悪用されるケースが目立ちます。
詐欺師は、一見すると非常に魅力的なビジネスモデルを提示してきますが、その裏には巧妙に仕組まれた罠が隠されています。具体的には、以下のような手口で被害者を追い込んでいきます。
- 「誰でも簡単に儲かる」とSNSや広告で勧誘する
- 手口①:「サイト作成料」「登録料」として高額な初期費用を請求する
- 手口②:研修やコンサルをセットにし、高額なサポート契約を結ばせる
- 手口③:架空の取引で「商品の仕入れ代」として繰り返し入金を要求する
- 手口④:「手数料」「税金」「保証金」を理由に利益の出金を拒否・妨害する
これらの手口は単独で行われることもあれば、複合的に組み合わされて、気づいた時には多額の被害に遭っていたというケースも少なくありません。それぞれの詳細を理解し、危険を察知する能力を身につけましょう。
「誰でも簡単に儲かる」とSNSや広告で勧誘する
ネットショップ詐欺の入り口のほとんどは、「誰でも」「簡単に」「絶対に儲かる」といった甘い言葉を使った誇大広告です。InstagramやX(旧Twitter)、FacebookなどのSNSや、動画サイトの広告で、きらびやかな生活を見せつけながら「あなたもこうなれる」と巧みに勧誘してきます。
これらの広告は、副業を探している会社員や、在宅で収入を得たい主婦など、現状の収入に不安を感じている層の心理に巧みに付け込みます。「専門知識は不要」「スマホをタップするだけ」といった言葉で、ビジネスの難しさやリスクを完全に隠蔽し、あたかも何のリスクもなく大金が手に入るかのように錯覚させるのです。
しかし、真っ当なビジネスに「絶対」はありません。市場の動向、競合の存在、集客の難しさなど、ネットショップ運営には様々なリスクや課題が伴います。こうした現実を無視し、メリットだけを異常に強調する話は、詐欺を疑うべき最初の危険信号です。実際に国民生活センターからも、「スキマ時間に気軽に稼げる」などとうたう副業トラブルに関する注意喚起が数多く出されています。
手口①:「サイト作成料」「登録料」として高額な初期費用を請求する
魅力的な勧誘に乗り、話を聞いてみると、次に待っているのが高額な初期費用の請求です。詐欺師は「オリジナルのネットショップを作るために必要」「特別な販売システムに登録するための費用」など、もっともらしい理由をつけて、数十万円から、時には100万円を超えるような法外な契約を迫ります。
本来、BASEやSTORESといった正規のサービスを利用すれば、ネットショップは初期費用無料からでも開設できます。有料プランだとしても月額数千円から数万円程度が相場です。これに対し、詐欺業者が請求する数十万円もの費用は、提供されるサービス価値に見合わない、異常な金額と言わざるを得ません。
この手口の悪質な点は、「最初にこの費用さえ払えば、あとは儲かるだけ」と被害者に思い込ませることです。しかし、実際には価値のないウェブサイトやシステムを提供されるだけで、約束された収益が得られることはありません。支払った高額な初期費用は、詐欺師の利益になるだけで、返金されることはほとんどないのです。
手口②:研修やコンサルをセットにし、高額なサポート契約を結ばせる
高額な初期費用と並行してよく使われるのが、情報商材やコンサルティング、運営サポートといった名目での高額契約です。「稼ぐためのノウハウが詰まったマニュアル」「プロがマンツーマンでサポート」などと謳い、サイト作成料とは別に、さらに数十万円の契約を要求してきます。
しかし、その実態は、インターネットで調べれば分かるような一般的な情報をまとめただけのPDFファイルであったり、質問しても当たり障りのない回答しか返ってこない、実態のないサポートであったりするケースがほとんどです。契約前は親身だった担当者が、入金後は連絡がつきにくくなるというのも典型的なパターンです。
このような情報商材やコンサル契約は、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性があります。もし契約してしまっても、法律に基づいてクーリング・オフ(契約解除)ができる場合があります。契約書面をしっかり確認し、少しでも怪しいと感じたら、すぐに消費生活センターなどに相談することが重要です。
手口③:架空の取引で「商品の仕入れ代」として繰り返し入金を要求する
これはドロップシッピングを悪用した詐欺の核心部分です。詐欺業者は、自らが運営する偽のECモールやASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)に被害者を登録させます。その管理画面上では、商品が次々と売れているかのように見せかけ、「売上が順調に伸びていますね!この商品を仕入れればさらに儲かりますよ」と、架空の商品の仕入れ代金を次々と要求してきます。
被害者は、管理画面上の偽の売上データを見て、「本当に儲かっている」と信じ込んでしまいます。そして、利益を出すため、さらにはこれまでの投資分を取り戻すために、言われるがまま追加の「仕入れ代金」を振り込み続けてしまうのです。
もちろん、これらの取引はすべて詐欺師が作ったシステム上の偽装であり、実際に商品が売買されているわけではありません。消費者庁が公表しているドロップシッピング契約のトラブル事例のように、振り込んだお金はすべて詐欺師の懐に入り、被害者の手元には一円も残りません。気づいた時には、数百万円もの大金をだまし取られていたという深刻な被害につながりやすい、非常に悪質な手口です。
手口④:「手数料」「税金」「保証金」を理由に利益の出金を拒否・妨害する
ある程度、管理画面上の「利益」が溜まった段階で、被害者が「利益を出金したい」と申し出ると、詐欺師は最後のだまし取りにかかります。「利益を出金するためには、まず手数料を支払う必要がある」「海外との取引だから税金を先に納めなければならない」「保証金を積まないと出金できない」など、様々な名目で追加の支払いを要求してくるのです。
これは、被害者の「せっかく出た利益を失いたくない」という心理を巧みに利用した手口です。あと少しお金を払えば大金が手に入ると信じ込み、最後の支払いに応じてしまう被害者は少なくありません。
しかし、当然ながら、その支払いをしても利益が出金されることは決してありません。詐欺師は、これ以上お金を引き出せないと判断した時点で、連絡を絶ち、姿を消してしまいます。この段階で、ようやく被害者は自分が詐欺に遭っていたことに気づくのです。このような事態に陥る前に、怪しいと感じた時点ですぐに行動を起こすことが何よりも重要です。
そのネットショップ開業話は詐欺?出店前に確認すべきチェックリスト

うまい話を持ちかけられた時、それが詐欺かどうかを冷静に判断するための知識は、あなた自身を守る最大の武器になります。契約を迫られたり、お金を払う前に、必ず以下のポイントを確認してください。一つでも当てはまる、あるいは疑わしい点があれば、その話は詐欺である可能性が非常に高いと言えます。
- 運営会社の情報(特定商取引法に基づく表記)は明記されているか
- 支払先の銀行口座が個人名義ではないか
- 「必ず儲かる」など断定的な収益保証をしていないか
- 契約を急かされたり、その場での即決を迫られたりしないか
- クーリング・オフなど解約条件について明確な説明はあるか
これらのチェックリストは、悪質な業者を見抜くための試金石です。一つずつ丁寧に確認し、安易に契約しない姿勢を徹底しましょう。
運営会社の情報(特定商取引法に基づく表記)は明記されているか
まず最初に確認すべき最も重要なポイントは、「特定商取引法に基づく表記」がウェブサイト上にきちんと記載されているかです。これには、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示することが法律で義務付けられています。
この表記がどこにも見当たらない業者は、その時点で論外です。また、記載があっても安心はできません。以下の点を確認しましょう。
- 住所を検索する: Googleマップなどで検索し、実在する住所か、バーチャルオフィスや普通の民家ではないかを確認します。
- 法人番号を調べる: 会社名が記載されていれば、国税庁の法人番号公表サイトで登記情報が実在するかを確認します。
- 電話番号にかける: 記載の電話番号に実際にかけてみて、本当につながるか、会社の人間がきちんと対応するかを確認します。
これらの情報が曖昧であったり、調べても実態が確認できなかったりする場合は、身元を隠して詐欺を働こうとしている可能性が極めて高いと判断できます。
支払先の銀行口座が個人名義ではないか
契約金や登録料などの支払いを求められた際に、その振込先口座が個人名義になっていないか必ず確認してください。真っ当な法人が事業として行う取引であれば、振込先は「会社名」や「屋号」の入った法人口座であるのが通常です。
もし、振込先が「スズキタロウ」のような完全に個人名の口座を指定された場合、それは極めて危険な兆候です。詐欺師は、足がつかないように他人名義の口座や、凍結されても構わない「捨て口座」を利用することが多いためです。
個人名義の口座への振り込みを求められたら、その理由を問いただしましょう。「経理の都合で」「今回は特別に」など、どんなにもっともらしい言い訳をされたとしても、決して応じてはいけません。法人口座を用意できない、あるいは意図的に使わない会社は、信頼に値しないと断言できます。
「必ず儲かる」など断定的な収益保証をしていないか
「誰でも月収100万円」「投資した資金が10倍になることを保証します」といった、将来の利益を断定的に約束するような勧誘は、特定商取引法で禁止されている「不実告知」や、景品表示法で禁止されている「有利誤認表示」にあたる可能性が高い違法行為です。
前述の通り、ビジネスの世界に「絶対」や「100%」は存在しません。市場は常に変動し、リスクはつきものです。真っ当な事業者であれば、成功の可能性を語ることはあっても、利益を「保証」するような無責任なことは決して言いません。
むしろ、事業に伴うリスクや、収益が保証されるものではないことをきちんと説明する事業者の方が、信頼できると言えるでしょう。断定的な利益保証は、情報弱者を安心させて契約させるための、詐欺師の常套句だと肝に銘じてください。このような言葉が出てきた時点で、即座に関係を断つべきです。
契約を急かされたり、その場での即決を迫られたりしないか
詐欺師は、被害者に冷静に考える時間を与えないように仕向けます。「今日中に契約すれば割引が適用されます」「このチャンスは今しかありません」といった言葉で決断を急かし、その場で契約書にサインさせようとするのは、典型的な手口の一つです。
これは、家族や友人に相談されたり、インターネットで評判を調べられたりすると、詐欺であることが発覚してしまうのを恐れているためです。高額な契約であればあるほど、一度持ち帰って冷静に検討する時間は不可欠です。
もし業者が即決を迫ってくるようであれば、「なぜそんなに急ぐ必要があるのですか?」と毅然とした態度で問いかけましょう。まともな事業者であれば、顧客が納得するまで検討する時間を十分に与えてくれるはずです。検討する時間を与えずに契約を迫るような業者は、あなたのことを考えていない、悪質な業者であると判断して間違いありません。
クーリング・オフなど解約条件について明確な説明はあるか
契約を結ぶ前に、解約条件、特にクーリング・オフについての説明がきちんとされるかを確認することは非常に重要です。特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売、そしてネットショップ詐欺が該当しうる「業務提供誘引販売取引」など、特定の取引形態において、消費者が一方的に契約を解除できるクーリング・オフ制度を定めています。
悪質な業者は、このクーリング・オフについて意図的に説明しなかったり、「この契約は特注品なのでクーリング・オフできません」などと嘘の説明をしたりすることがあります。また、解約手続きを非常に複雑にしたり、高額な違約金を請求する条項を契約書に紛れ込ませたりする手口も存在します。
契約書にサインする前に、解約に関する項目を隅々まで読み込み、少しでも不明な点や不利な条件があれば、納得できるまで説明を求めてください。説明を渋ったり、曖昧な回答しかしない場合は、契約してはいけません。
ネットショップ出店・開業詐欺の被害に遭った場合の対処法や相談先

「もしかしたら、もう詐欺に遭ってしまったかもしれない…」と気づいた時、パニックになり、どうしていいか分からなくなるかもしれません。しかし、諦めてはいけません。被害を回復し、拡大を防ぐために、迅速かつ冷静に行動することが何よりも重要です。
被害に気づいた場合に取るべき行動は、以下の通りです。
- まずは証拠を保全し、これまでのやり取りを全て記録する
- すぐに消費生活センターや警察に相談する
- 弁護士や司法書士など法律の専門家を頼る
- クーリング・オフ制度が利用できないか確認する
- クレジットカード会社や銀行に連絡する
一人で抱え込まず、これらの窓口にためらわずに助けを求めてください。行動が早ければ早いほど、お金が戻ってくる可能性は高まります。
まずは証拠を保全し、これまでのやり取りを全て記録する
被害の相談や返金交渉、法的手続きを進める上で、客観的な「証拠」が最も重要になります。相手との連絡が取れるうちに、以下のものを全て保存・記録してください。
- 契約書、申込書、パンフレットなど
- 相手のウェブサイトや広告のスクリーンショット
- メールやLINE、SNSのダイレクトメッセージのやり取り
- 通話の録音データ(可能な場合)
- お金を振り込んだ際の利用明細や振込記録
相手に詐欺だと気づかれた途端、ウェブサイトが閉鎖されたり、SNSアカウントが削除されたりして、証拠が消えてしまう可能性があります。少しでも「おかしい」と感じた時点で、すぐにこれらの情報を保全する習慣をつけましょう。これらの証拠が、後の相談や交渉を有利に進めるための強力な武器となります。
すぐに消費生活センターや警察に相談する
被害に遭ったかもしれないと感じたら、一人で悩まずに公的な相談窓口に連絡してください。どこに相談すればよいか迷った場合は、まず以下の窓口に電話しましょう。
消費者ホットライン「188」
「いやや!」と覚えてください。政府広報オンラインでも紹介されている通り、消費生活に関するトラブル全般について相談できる全国共通の窓口です。専門の相談員が、問題解決のためのアドバイスや、クーリング・オフの手続き支援、他の専門機関の紹介などを行ってくれます。契約上のトラブル解決に向けた具体的な助言が期待できます。
警察相談専用電話「#9110」
詐欺事件として刑事事件化(犯人の逮捕)を望む場合に相談する窓口です。「詐欺の疑いが強い」「脅迫的な言動をされている」など、犯罪性が高いと感じた場合はこちらに連絡しましょう。被害届の提出方法などについてアドバイスがもらえます。
これらの窓口は、同様の被害相談を数多く受けています。あなたのケースが詐欺にあたるのか、どういった対応が可能かについて、専門的な知見からアドバイスをもらえます。
弁護士や司法書士など法律の専門家を頼る
支払ってしまったお金の返金を具体的に求めていくには、法律の専門家の力が必要になるケースが多いです。弁護士や司法書士は、あなたの代理人として、相手業者との返金交渉や、必要であれば訴訟(裁判)などの法的手続きを行ってくれます。
特に、被害額が高額な場合や、相手が悪質で交渉に応じない場合は、専門家の介入が不可欠です。
相談する際は、事前に保全した証拠を持参し、これまでの経緯を時系列でまとめておくとスムーズです。費用はかかりますが、自分一人で交渉するよりもお金が戻ってくる可能性は格段に高まります。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
クーリング・オフ制度が利用できないか確認する
クーリング・オフとは、一度契約を申し込んだり、契約をしたりした後でも、一定の期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。ネットショップ開業詐欺が該当しうる「業務提供誘引販売取引」の場合、法律で定められた書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、クーリング・オフが可能です。
もし、業者から法律で定められた要件を満たす書面(契約内容やクーリング・オフについて記載されたもの)を受け取っていなかったり、書面の内容に不備があったりした場合は、20日が過ぎていてもクーリング・オフができる可能性があります。
クーリング・オフは、必ず書面(ハガキや内容証明郵便など)で行う必要があります。電話で伝えただけでは証拠が残らず、「聞いていない」と言われてしまう恐れがあります。手続きの方法が分からなければ、消費生活センターに相談すれば、書き方などを具体的に教えてもらえます。
クレジットカード会社や銀行に連絡する
支払い方法によっても、取るべき対応があります。
クレジットカードで支払った場合:
すぐにクレジットカード会社に連絡し、事情を説明して支払いの停止(抗弁の接続)を求めましょう。また、「チャージバック」という仕組みを利用して、カード会社から詐欺業者への支払いを中止し、返金を求めることができる場合があります。
銀行振込で支払った場合:
振り込め詐欺救済法に基づき、詐欺に利用された銀行口座を凍結し、その口座に残っている資金を被害者に分配する手続きを申請できる可能性があります。すぐに振込先の金融機関と警察に連絡してください。ただし、口座からすでにお金が引き出されている場合は、返金を受けるのが難しくなるため、一刻も早い行動が求められます。
実際に起きたネットショップのドロップシッピング詐欺の被害事例
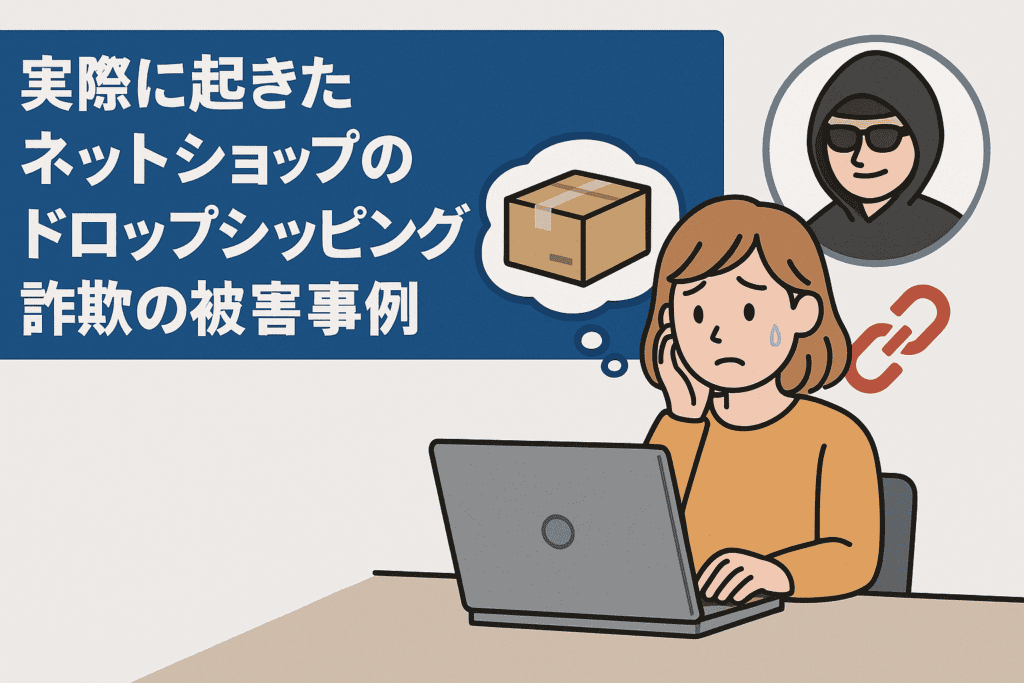
ネットショップ開業詐欺は、決して他人事ではありません。ここでは、実際に報告されている被害事例を2つ紹介します。手口や被害に至る経緯を知ることで、自分自身が同じような状況に陥ることを防ぎましょう。
- 事例:SNSの副業広告がきっかけで高額なコンサル契約をしてしまった
- 事例:マッチングアプリで知り合った相手に勧められ、実態のないECサイトに投資した
これらの事例に共通しているのは、最初は魅力的な話から始まり、気づいた時には後戻りできないほどの金銭を支払ってしまっている点です。
事例:SNSの副業広告がきっかけで高額なコンサル契約をしてしまった
会社員のAさんは、Instagramで「主婦でも月収100万円!」という副業広告を見つけ、LINEアカウントを登録しました。すると、担当者から「誰でも簡単に儲かるネットショップ運営」を勧められ、電話で熱心な勧誘を受けました。
「このシステムを使えば絶対に成功する」と言われ、ECサイトの構築費用として50万円をクレジットカードで決済。さらに、「成功するためにはマンツーマンのコンサルが不可欠」と畳みかけられ、追加で100万円のサポート契約を結んでしまいました。
しかし、提供されたサイトは簡単なテンプレートで作られたもので、コンサルタントに質問しても曖昧な回答しか返ってきませんでした。不審に思い返金を求めたところ、「契約書に書いてある通り返金はできない」の一点張り。最終的に担当者とは連絡が取れなくなり、Aさんの手元には150万円の借金だけが残りました。
事例:マッチングアプリで知り合った相手に勧められ、実態のないECサイトに投資した
Bさんは、マッチングアプリで知り合った海外在住を名乗る女性と親密な関係になりました。ある日、その女性から「叔父が経営しているECサイトのビジネスを手伝ってほしい。投資すれば大きな利益が出る」と持ちかけられました。
Bさんは女性を信用し、指定されたECサイトに登録。最初は少額の投資で、管理画面上では順調に利益が出ているように見えました。女性から「もっと投資すればもっと儲かる」と勧められるまま、Bさんは借金をしてまで、最終的に1000万円以上をそのサイトに入金してしまいました。
利益を出金しようとしたところ、「税金を払わないと出金できない」と言われ、追加で200万円を要求されました。さすがにおかしいと思ったBさんが友人に相談したところ、詐欺だと発覚。すぐに女性のSNSアカウントは削除され、連絡が取れなくなってしまいました。これは恋愛感情を利用した「国際ロマンス詐欺」と「投資詐欺」が複合した悪質なケースです。
詐欺を避けて安全にネットショップを開業・出店するための方法
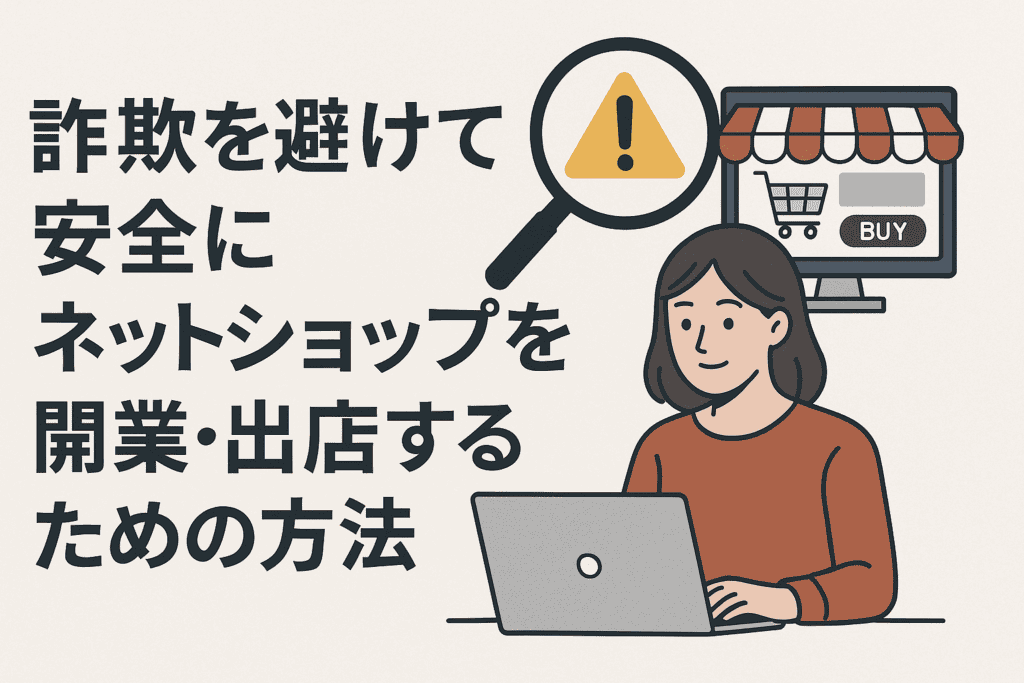
ここまで詐欺の危険性について解説してきましたが、もちろん、全てのネットショップ開業が危険なわけではありません。真っ当な方法で、安全に自分の店を持つことは十分に可能です。詐欺に遭うリスクを避け、安心してビジネスを始めるためには、以下の3つのポイントを徹底することが重要です。
- 信頼できる大手ECプラットフォームを利用する(BASE, STORESなど)
- 初期費用が無料または低価格で始められるサービスを選ぶ
- 「楽して稼ぐ」ではなく、健全なビジネス運営を目指す
怪しい儲け話に惑わされず、地に足のついた方法を選ぶことが、成功への一番の近道です。
信頼できる大手ECプラットフォームを利用する(BASE, STORESなど)
ネットショップを開業する際は、実績と信頼のある大手ECプラットフォームを利用するのが最も安全で確実な方法です。例えば、以下のようなサービスは、多くの事業者に利用されており、料金体系やサポート体制も明確です。
- BASE(ベイス): 初期費用・月額費用が無料で、商品が売れた時だけ手数料がかかるため、リスクを抑えて始めたい個人に人気です。
- STORES(ストアーズ): こちらも無料から始められるプランがあり、デザインのカスタマイズ性や顧客管理機能も充実しています。
- Shopify(ショッピファイ): 世界中で利用されているプラットフォームで、拡張性が高く、本格的なネットショップ運営や越境ECを目指す場合に適しています。
これらの正規サービスは、運営会社情報が明確であることはもちろん、長年の運営実績があり、多くのユーザーからの評判や口コミも確認できます。怪しい業者に高額なサイト作成料を払うのではなく、こうした信頼できるプラットフォームを活用しましょう。
初期費用が無料または低価格で始められるサービスを選ぶ
前述の通り、BASEやSTORESのように、現在のネットショップ作成サービスは初期費用無料で始められるものが主流です。これは、事業者が大きなリスクを負うことなく、スモールスタートでビジネスを試せるようにするためです。
もし、あるサービスが数十万円といった高額な初期費用を要求してきたら、その時点で「なぜそんなに高いのか?」と疑問を持つべきです。その費用が、提供されるサービスの価値に見合っているのかを冷静に比較検討してください。
「最初に大きく投資すれば、リターンも大きい」というのは、詐欺師がよく使う論法です。しかし、ビジネスの現実は逆です。最初はできるだけリスクを抑えて始め、事業が軌道に乗ってから、必要に応じて広告や機能追加に投資していくのが健全な進め方です。初期費用を抑えることは、詐欺のリスクを避けるだけでなく、経営上のリスク管理においても非常に重要です。
「楽して稼ぐ」ではなく、健全なビジネス運営を目指す
ネットショップ詐欺に遭ってしまう人の多くは、「楽して簡単に稼ぎたい」という気持ちを悪用されています。しかし、その考え方こそが、最も危険な罠への入り口なのです。
成功しているネットショップは、魅力的な商品を選び、美しい商品写真を撮り、丁寧な商品説明を書き、SNSなどで地道に集客し、顧客対応を誠実に行うといった、日々の努力の積み重ねの上に成り立っています。魔法のような「必勝法」や「自動で稼げるシステム」は存在しません。
詐欺を避け、本当に自分のビジネスを成功させたいのであれば、まずこの「楽して稼ぐ」という幻想から抜け出すことが不可欠です。地道な努力を覚悟し、自分の店を少しずつ育てていくという健全なマインドセットを持つこと。それが、詐欺から身を守り、ビジネスを成功させるための最も確実な方法と言えるでしょう。
ネットショップ開業とドロップシッピング詐欺に関するよくある質問

最後に、ネットショップ開業やドロップシッピング詐欺に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。
ドロップシッピング自体は違法ではないのですか?
はい、ドロップシッピングというビジネスモデル自体は違法ではありません。在庫を持たずに商品を販売できる仕組みであり、欧米では一般的なECの形態の一つです。日本でも、正規のドロップシッピング提供事業者(DSP)を利用すれば、健全なビジネスとして運営することが可能です。
問題なのは、この「在庫不要」という手軽さを悪用し、実態のない取引で金銭をだまし取ろうとする詐欺師が存在することです。ドロップシッピングを始める際は、その運営会社が信頼できる正規の事業者かどうかを慎重に見極めることが極めて重要になります。
被害に遭った場合、支払ったお金が返金される可能性はありますか?
返金される可能性はゼロではありませんが、残念ながら非常に難しいケースが多いのが実情です。詐欺師は、だまし取ったお金をすぐに海外の口座に移したり、引き出したりしてしまうため、口座が凍結された時点ではすでにお金が残っていないことも少なくありません。
しかし、諦める必要はありません。弁護士による交渉や、クレジットカードのチャージバック制度など、返金を実現するための手段は存在します。何よりも重要なのは、被害に気づいた時点ですぐに行動を起こすことです。時間が経てば経つほど、お金を取り戻すのは困難になります。一人で悩まず、速やかに専門機関に相談してください。
安全なネットショップサービスはどうやって見つければいいですか?
安全なサービスを見つけるためのポイントは、この記事で解説してきたことの逆を行くことです。
- 運営実績が長く、知名度が高いサービスを選ぶ(BASE, STORES, Shopifyなど)
- 料金体系がウェブサイトで明確に公開されている
- インターネット上で、利用者からの良い評判や口コミが多数見つかる
- 特定商取引法に基づく表記がきちんと記載されている
- 「絶対に儲かる」といった誇大広告をしていない
少しでも怪しいと感じたら、すぐに契約せず、時間をかけて情報収集する姿勢が大切です。うまい話には必ず裏があると考え、慎重に行動しましょう。