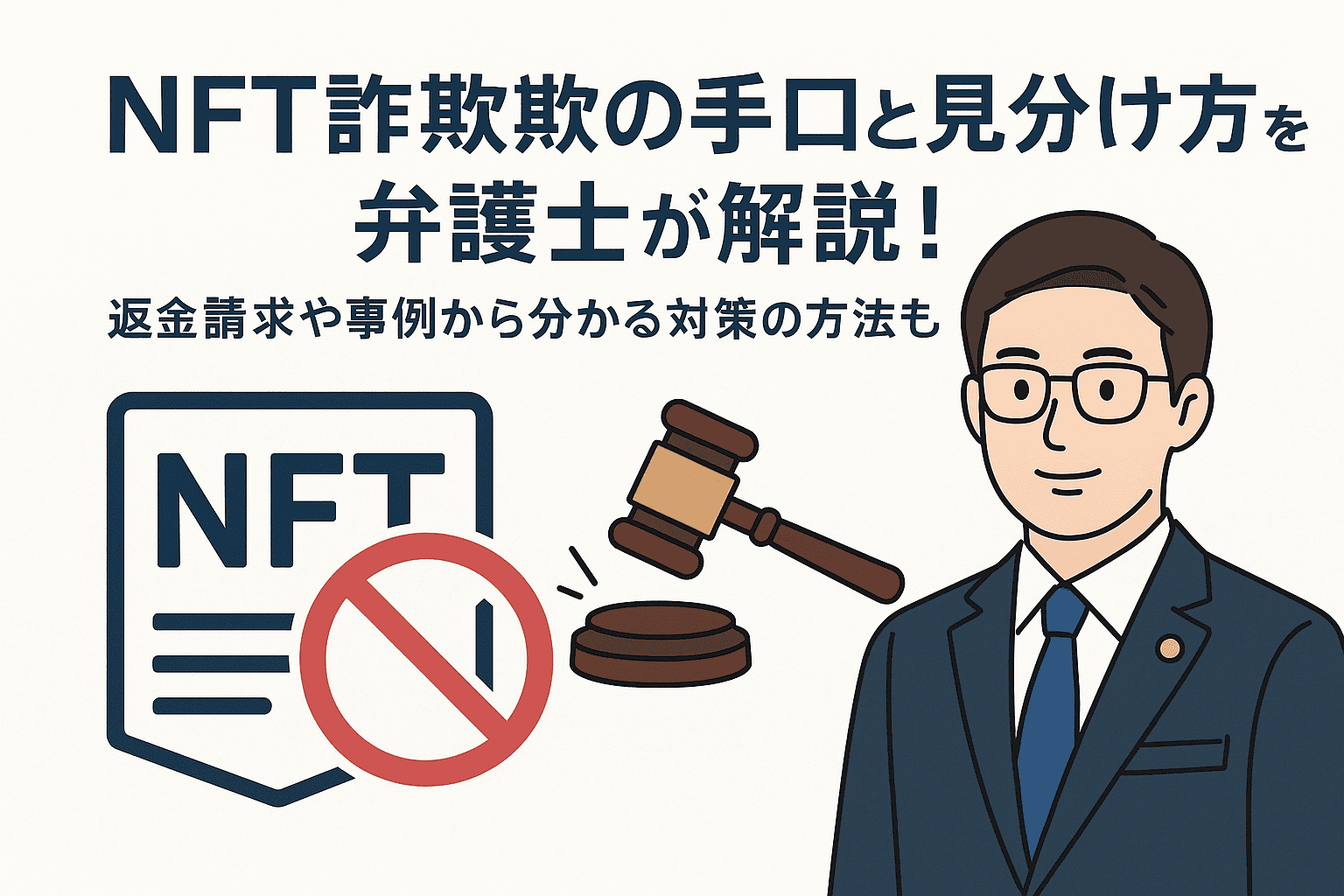「あなたのアートを高値で買いたい」「このNFTは絶対に儲かる」――そんなうまい話がSNSのDMで届き、不安や疑問を感じていませんか。あるいは、すでにNFTの取引で不審な点があり、「もしかして詐欺かもしれない」と悩んでいる方もいるかもしれません。
NFT(非代替性トークン)は新しい技術であり、その将来性に期待が集まる一方で、知識不足や心理的な隙を突く悪質な詐欺が急増しています。偽のサイトに誘導されて資産を盗まれたり、価値のないNFTを高額で購入させられたりと、その手口は巧妙化・多様化しており、誰でも被害に遭う可能性があります。
この記事では、NFT詐欺の代表的な手口から、被害を未然に防ぐための具体的な見分け方、そして万が一被害に遭ってしまった場合の対処法まで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、NFT詐欺に対する正しい知識が身につき、ご自身の資産を守るための具体的な行動がわかるようになります。そして、もし今まさに被害に遭い、返金を求めているのであれば、泣き寝入りせずに専門家へ相談するという選択肢があることもご理解いただけるはずです。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
NFT詐欺とは
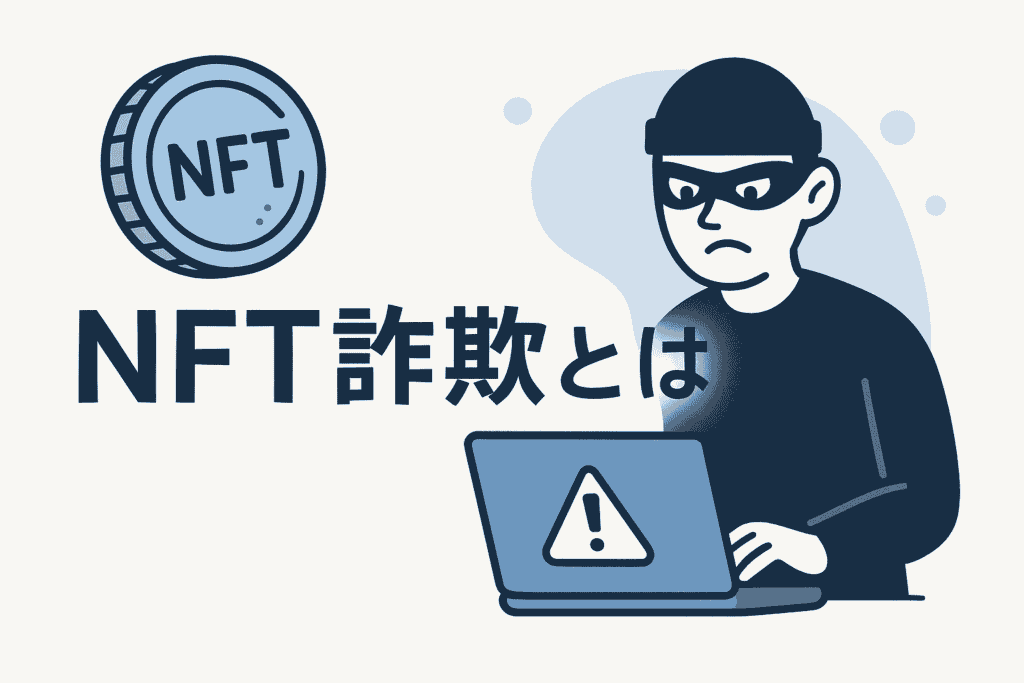
NFT詐欺とは、NFT(非代替性トークン)の取引に関連して行われる詐欺行為全般を指します。偽のNFTを販売したり、偽サイトに誘導して暗号資産を盗んだりするなど、その手口は多岐にわたります。
ここでは、NFT詐欺の基本的な概要と、なぜこれほどまでに詐欺が増加しているのか、その背景について解説します。
NFT詐欺の概要と最近の傾向
NFT詐欺は、デジタルデータに唯一無二の価値を持たせるNFTの特性を悪用し、金銭や暗号資産をだまし取る犯罪行為です。当初は偽物のNFTアートを販売する手口が主流でしたが、市場の拡大とともに手口は巧妙化しています。
最近では、SNSのDM(ダイレクトメッセージ)を利用して個人に直接接触し、偽の投資話を持ちかけたり、偽のマーケットプレイスへ誘導したりする手口が急増しています。特に、InstagramやX(旧Twitter)でクリエイターを装って「あなたの作品を買いたい」と持ちかけ、手数料名目で金銭を要求するケースや、マッチングアプリで恋愛感情を利用して高額なNFT投資を勧めるロマンス詐欺型の被害が目立ちます。
これらの手口は、NFTに関する知識が浅い初心者や、言語の壁がある海外ユーザーとのやり取りに不慣れな人を主なターゲットとしており、誰もが被害者になりうる状況です。
NFT詐欺が増加している背景
NFT詐欺がこれほどまでに増加している背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。
第一に、NFT市場の急速な拡大が挙げられます。2021年頃からNFTへの注目が世界的に高まり、アートやゲーム、コレクティブルなど様々な分野で高額取引が成立しました。この投機的な熱狂が「NFTは儲かる」というイメージを広げ、知識が不十分なまま市場に参入する人を増やした結果、詐欺師にとって格好の標的が生まれたのです。
第二に、技術的な匿名性の高さです。NFTの取引は主に暗号資産を用いてウォレット間で行われますが、ウォレットの所有者を特定することは容易ではありません。このため、詐欺師は身元を隠したまま犯行に及びやすく、一度盗まれた資産の追跡や回収が極めて困難になっています。
そして第三に、法整備や規制が追いついていない点も無視できません。NFTは国境を越えて取引される新しい分野であるため、消費者庁や金融庁などが議論を進めているものの、各国の法規制や消費者保護の仕組みがまだ十分に整備されていません。この無法地帯ともいえる状況が、詐欺師が活動しやすい環境を生み出しているのです。
NFT詐欺の代表的な手口
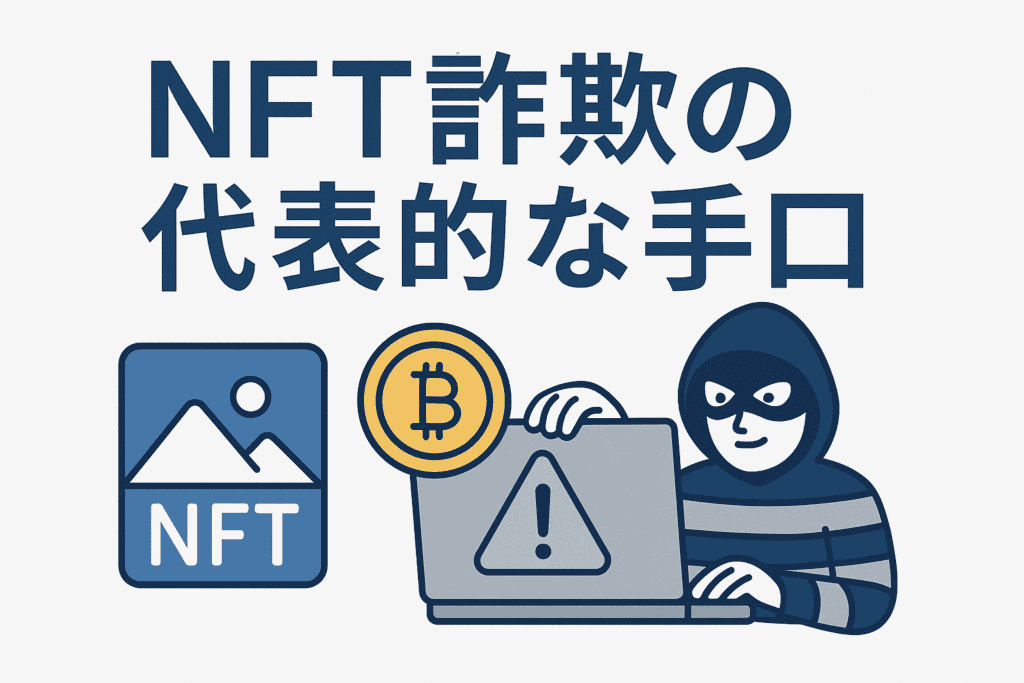
NFT詐欺の手口は年々巧妙化し、様々な形で私たちの資産を狙ってきます。ここでは、特に被害報告の多い代表的な詐欺の手口を具体的に解説します。
- SNSやDMを使ったフィッシング詐欺
- 偽NFTマーケットプレイスや詐欺サイトへの誘導
- 偽NFT・盗用アート・偽コレクション販売
- ラグプル(プロジェクト資金持ち逃げ)
- 価格操作(パンプ&ダンプスキーム)
- 偽ミントサイト・フリーミント詐欺
- NFTカードやNFTゲームを悪用した詐欺
- マッチングアプリやロマンス詐欺型のNFT投資勧誘
- 知らないNFTがウォレットに送られてくるエアドロップ型詐欺
SNSやDMを使ったフィッシング詐欺
フィッシング詐欺は、SNSやDMを通じて偽のWebサイトに誘導し、ウォレットのログイン情報やシードフレーズ(ウォレットを復元するためのパスワード)を盗み出す古典的かつ非常に効果的な手口です。
犯人は、信頼できる公式アカウントや有名人を装って利用者に接触します。メッセージの内容は、「限定NFTのプレゼント企画に当選しました」「セキュリティ上の問題が発生したため、ウォレットを再認証してください」といった、利用者の射幸心や不安を煽るものがほとんどです。
これらのメッセージに記載されたリンクをクリックすると、本物そっくりの偽サイトに遷移し、情報の入力を求められます。そこでシードフレーズなどを入力してしまうと、ウォレット内のNFTや暗号資産がすべて抜き取られてしまいます。公式のアナウンスを装った巧妙な手口には、特に注意が必要です。
X(旧Twitter)・Instagram・TikTokでの偽アカウント勧誘
XやInstagram、TikTokなどのSNSでは、有名プロジェクトやアーティストの偽アカウントを作成し、本物であるかのように振る舞う手口が横行しています。これらの偽アカウントは、公式と瓜二つのプロフィール写真や投稿内容で利用者を信用させます。
そして、「Giveaway(プレゼント企画)」や「限定セール」と称して、偽のミントサイト(NFTを発行するサイト)へのリンクを投稿したり、DMで直接送りつけたりします。特にクリエイターに対しては、「あなたのアート作品に感銘を受けた。ぜひNFTとして購入したい」と持ちかけ、偽のマーケットプレイスへの登録や、ガス代(手数料)の支払いを要求するケースが多発しています。これらの勧誘は、承認欲求や金銭的欲求を巧みに利用した悪質な手口です。
Discord・LINEでのダイレクトメッセージ誘導
NFTプロジェクトの多くは、情報交換の場としてDiscordを公式コミュニティとして利用しています。詐欺師はこの環境を悪用し、運営メンバーやサポート担当になりすまして利用者に直接DMを送りつけます。
「サーバー内でトラブルがありました」「特別なロール(役割)を付与します」といった口実で、利用者の不安や優越感を煽り、偽サイトへのリンクをクリックさせようとします。また、LINEなどのクローズドなコミュニケーションツールに誘導し、「ここだけの儲け話がある」とNFT投資詐欺を持ちかけるケースも報告されています。公式コミュニティ内であっても、個人間のDMは基本的に信用せず、必ず公式アナウンスを確認する習慣が重要です。
偽NFTマーケットプレイスや詐欺サイトへの誘導
本物のNFTマーケットプレイス(例:OpenSea)やプロジェクト公式サイトと見分けがつかないほど精巧に作られた偽サイト(詐欺サイト)へ誘導する手口も非常に多いです。
これらのサイトは、GoogleやXの広告機能を使って検索結果の上位に表示されたり、SNSのDMで送られてきたりします。利用者が偽サイトとは知らずにウォレットを接続し、取引の承認(アプルーバル)をしてしまうと、ウォレット内の資産を自由に抜き取れる権限を詐欺師に与えてしまいます。
特に、「ミント(Mint)」や「セール」といったイベント時には、利用者が急いでいる心理状態を利用して偽サイトへ誘導するケースが増えるため注意が必要です。公式サイトへは、検索エンジンからではなく、事前にブックマークしたリンクからアクセスする癖をつけることが有効な対策となります。
偽NFT・盗用アート・偽コレクション販売
これは、他人のアート作品を無断でコピーしてNFT化したり、有名なNFTコレクションの偽物を作成して販売したりする詐欺です。
NFTの仕組み上、一度ブロックチェーンに記録された情報の改ざんは困難ですが、最初にNFTを作成(ミント)する段階で、元となるデータが本物であるかどうかの保証はありません。詐欺師は、人気アーティストの作品をSNSなどから盗用し、あたかも自身が作成したかのように見せかけてNFTマーケットプレイスで販売します。
購入者は偽物と気づかずに購入してしまいますが、資産的価値は全くなく、後から本物の作者が著作権侵害を申し立てた場合、そのNFTはマーケットプレイスから削除される可能性もあります。購入前には、出品者が本当にその作品の作者本人であるか、公式SNSなどで確認することが不可欠です。
ラグプル(プロジェクト資金持ち逃げ)
ラグプル(Rug Pull)は、「敷物を引き抜く」という意味の言葉から来ており、NFTプロジェクトの運営チームが、投資家から集めた資金をすべて持ち逃げする詐欺行為を指します。
詐欺師は、魅力的なロードマップや将来性を謳ったプロジェクトを立ち上げ、SNSやインフルエンサーマーケティングを駆使して期待感を煽り、NFTを販売して資金を調達します。しかし、プロジェクトが軌道に乗ったと見せかけ、資金が集まった段階で、突然ウェブサイトやSNSアカウントをすべて削除し、連絡が取れなくなります。
投資家たちの手元には、価値のなくなった無意味なNFTだけが残されます。ラグプルを見抜くのは困難ですが、運営チームの身元が匿名であったり、プロジェクトの進捗が不透明であったりする場合は、警戒が必要です。
価格操作(パンプ&ダンプスキーム)
パンプ&ダンプスキームは、特定のNFTの価格を意図的に吊り上げ(パンプ)、価格が高騰したところで売り抜けて利益を得る(ダンプ)という、市場操作による詐欺手法です。
詐欺師は、まず価値の低いNFTを大量に買い占めます。その後、SNSやコミュニティで「このNFTは将来有望だ」「大手企業と提携した」などの偽情報を流布し、他の投資家の買いを誘います。多くの人が買いに走ることで価格は急騰し、それを見た一般投資家が「乗り遅れまい」とさらに購入します。
価格が十分に吊り上がったところで、詐欺師は保有していたNFTをすべて売り抜けます。大量の売り注文によって価格は暴落し、高値で購入した投資家は大きな損失を被ることになります。根拠のない熱狂や、急激な価格上昇には注意が必要です。
偽ミントサイト・フリーミント詐欺
「ミント(Mint)」とは、新しいNFTを作成・発行するプロセスを指します。偽ミントサイト詐欺は、人気プロジェクトの公式サイトを模倣した偽のミントサイトを作成し、利用者を騙す手口です。
特に、「フリーミント(無料ミント)」を謳う詐欺が増えています。「無料でNFTが手に入る」という甘い言葉で利用者を誘い、偽サイトでウォレットを接続させます。利用者がガス代(手数料)の支払いトランザクションに署名したつもりが、実際にはウォレット内の資産をすべて抜き取る権限を与える悪意のある契約(スマートコントラクト)に署名させられていた、というケースが後を絶ちません。
「無料」という言葉には常に警戒し、ミントサイトのURLが本当に公式のものであるか、Discordなどで何度も確認することが重要です。
NFTカードやNFTゲームを悪用した詐欺
トレーディングカードやゲーム内アイテムがNFTとして取引される「NFTカード」や「NFTゲーム(ブロックチェーンゲーム)」の分野でも詐欺は多発しています。
「レアなNFTカードが手に入る」「ゲームをプレイするだけで稼げる(Play to Earn)」といった宣伝文句で利用者を誘い、高額な初期投資を要求したり、ゲーム内通貨を購入させたりします。しかし、実際にはゲーム自体が未完成であったり、約束されたような収益性が全くなかったりするケースがほとんどです。
最終的には、ラグプルと同様に運営がプロジェクトを放棄して資金を持ち逃げするパターンが多く見られます。ゲームとしての面白さや持続可能性、開発チームの実績などを冷静に評価することが求められます。
マッチングアプリやロマンス詐欺型のNFT投資勧誘
これは、TinderやPairsといったマッチングアプリを悪用し、恋愛感情や信頼関係を築いた上でNFT投資に勧誘する、非常に悪質な詐欺です。警察庁や国民生活センターも注意喚起を行う、国際ロマンス詐欺の一種とも言えます。
詐欺師は、魅力的で裕福な人物を装ってターゲットに接触し、やり取りを重ねて親密な関係を築きます。そして、「二人で将来のために資産を築こう」「叔父がインサイダー情報を持っている」などと持ちかけ、特定のNFTや関連する暗号資産への投資を勧めます。
最初は少額の投資で利益が出たように見せかけ、信用させた後でより高額な投資を要求します。ターゲットが多額の資金を投じた後、あるいは出金しようとすると、詐欺師は突然連絡を絶ちます。恋愛感情が絡むため被害者が冷静な判断を下しにくく、被害額が非常に高額になる傾向があります。
知らないNFTがウォレットに送られてくるエアドロップ型詐欺
ある日突然、自分のウォレットに見覚えのないNFTが送りつけられてくることがあります。これは「エアドロップ」と呼ばれる手法を悪用した詐欺の可能性があります。
詐欺師は、不特定多数のウォレットアドレスに対して、無差別にNFTを送りつけます。そのNFTには、魅力的な画像や「ウェブサイトをチェックして報酬を受け取ろう」といったメッセージが含まれていることがあります。
利用者が興味本位でそのNFTを売却しようとしたり、記載されたリンク先のサイトでウォレットを接続したりすると、悪意のあるスマートコントラクトが実行され、ウォレット内の資産が盗まれてしまいます。身に覚えのないNFTは、絶対に触らず、無視(非表示にするなど)することが最も安全な対策です。
NFT詐欺の見分け方
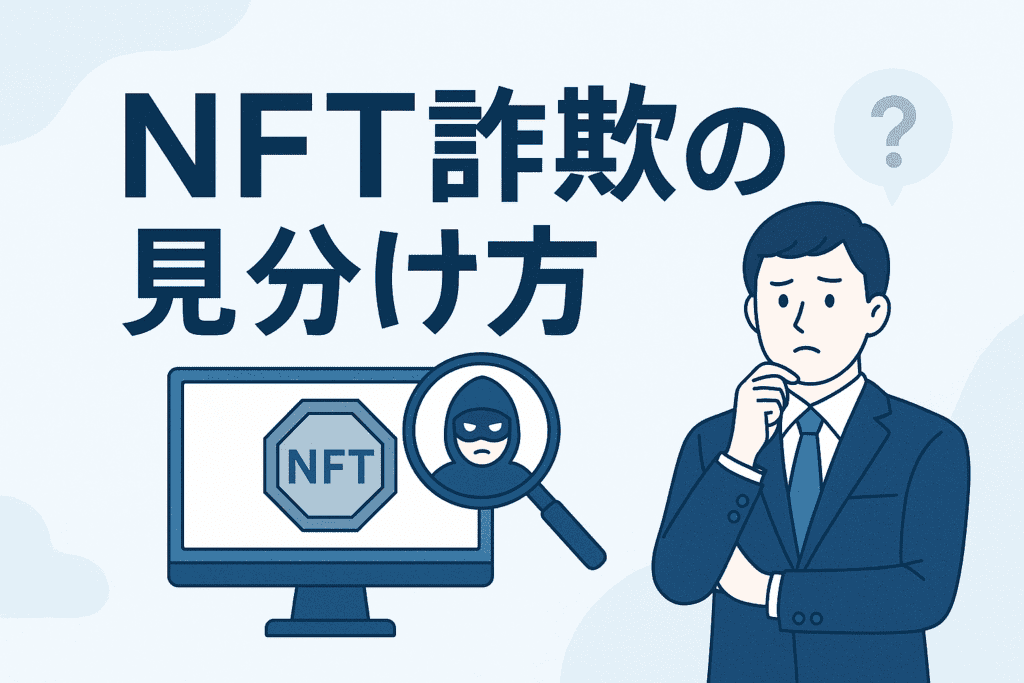
巧妙化するNFT詐欺から身を守るためには、取引相手やプロジェクトが本物かどうかを自分自身で見分けるスキルが不可欠です。ここでは、詐欺を見抜くための具体的なチェックポイントと方法を解説します。
公式情報や認証マークの確認
最も基本的かつ重要なのが、公式情報を確認することです。NFTマーケットプレイスのOpenSeaなどでは、信頼性の高い著名なコレクションに対して、アカウント名の横に青いチェックマーク(認証マーク)を付与しています。このマークは、そのコレクションが本物であることの一つの目安となります。
ただし、新しいプロジェクトや小規模なコレクションには認証マークがついていないことも多いため、マークがないからといって即座に偽物と判断はできません。
その場合は、必ずプロジェクトの公式ウェブサイト、公式X(旧Twitter)アカウント、公式Discordコミュニティなどを確認しましょう。本物のプロジェクトは、これらのプラットフォームで一貫した情報発信を行っています。公式サイトに掲載されているマーケットプレイスへのリンクからアクセスするのが最も安全です。
コントラクトアドレスと取引履歴の確認方法
NFTの真贋を見極める上で、技術的に最も確実な方法が「コントラクトアドレス」の確認です。コントラクトアドレスとは、そのNFTコレクションがブロックチェーン上でどのプログラム(スマートコントラクト)に基づいているかを示す、固有の識別子です。
本物のプロジェクトは、公式サイトやDiscordで正規のコントラクトアドレスを公開しています。購入を検討しているNFTが、その正規のコントラクトアドレスから発行されたものであるかを、Etherscanなどのブロックチェーンエクスプローラーで確認することで、偽物をほぼ確実に見分けることができます。
また、取引履歴(トランザクション履歴)を確認することも有効です。本物の人気コレクションであれば、活発な取引が継続的に行われているはずです。取引がほとんどない、またはごく一部のウォレット間でのみ行われている場合は注意が必要です。
URL・ドメインの正当性チェック
フィッシング詐欺や偽サイトへの誘導を防ぐためには、アクセスしているサイトのURLを注意深く確認する習慣が極めて重要です。
詐欺サイトは、本物のサイトのURLと酷似したドメイン名を使用します。例えば、本物が「opensea.io」であるのに対し、偽物は「opensea.co」や「opensea.xyz」であったり、文字の「o」が数字の「0」になっていたりするなど、巧妙な間違いが仕込まれています。
少しでも怪しいと感じたら、そのサイトでウォレットを接続したり、個人情報を入力したりしてはいけません。特に、メールやDMで送られてきたリンクは安易にクリックせず、必ず公式サイトをブックマークしておき、そこからアクセスするようにしましょう。ブラウザのアドレスバーを常に確認する癖をつけることが、資産を守る第一歩です。
出品者や販売元の実態調査
NFTを購入する際は、その出品者やプロジェクトの運営元が信頼できるかどうかを調査することが大切です。いわゆる「DYOR(Do Your Own Research)」、つまり自分で調べるという姿勢が求められます。
以下の点を確認してみましょう。
- 運営チームの情報開示: チームメンバーの顔や実名、過去の実績などが公開されているか。匿名性の高いチームは、ラグプルのリスクが高まります。
- ロードマップの具体性: プロジェクトの将来計画(ロードマップ)が、具体的で実現可能なものか。曖昧で壮大なだけの計画は危険信号です。
- コミュニティの活動状況: DiscordやTelegramなどのコミュニティは活発か。健全な質疑応答が行われているか、それとも価格の話ばかりで熱狂だけが煽られていないか。
これらの情報を総合的に判断し、信頼性に欠けると判断した場合は、取引を見送るのが賢明です。
取引量やオーナー数などの不自然な数値の見極め方
NFTマーケットプレイスに表示される各種データも、真贋を見分けるための重要な手がかりとなります。特に以下の3つの数値に注目しましょう。
- 取引量(Total Volume): これまでの総取引額。人気コレクションであれば、この数値は非常に大きくなります。極端に少ない場合は偽物の可能性があります。
- オーナー数(Owners): そのNFTを保有している人の数。オーナー数がアイテム数に対して不自然に少ない場合(例:アイテム10,000点に対しオーナー10人)、一部の人間による価格操作の可能性があります。
- フロアプライス(Floor Price): コレクション内で最も安く出品されている価格。市場価格とかけ離れて安すぎる場合は、盗品や偽物の可能性があります。
これらの数値は絶対的な指標ではありませんが、他の情報と合わせて総合的に判断することで、リスクを大幅に減らすことができます。
不審なDM・メール・広告への対応ルール
詐欺の入り口の多くは、DMやメール、SNS広告です。これらに対する自分なりの対応ルールを確立しておくことが、被害を防ぐ上で非常に効果的です。
まず、「知らない相手からのDMは基本的に無視・削除する」ことを徹底しましょう。特に、「あなたのアートを買いたい」「儲かる投資話がある」といったうますぎる話は、100%詐欺だと考えて差し支えありません。
次に、「公式発表は必ず一次情報源で確認する」ことです。Giveawayやセールなどの魅力的な情報が流れてきても、すぐに飛びつかず、プロジェクトの公式XやDiscordで本当にそのような発表があったかを確認します。
最後に、「絶対にシードフレーズは教えない・入力しない」という鉄則です。どのような理由であれ、他人にシードフレーズを尋ねられたり、サイトで入力を求められたりした場合は、即座に詐欺だと判断してください。
NFT詐欺を防ぐための対策
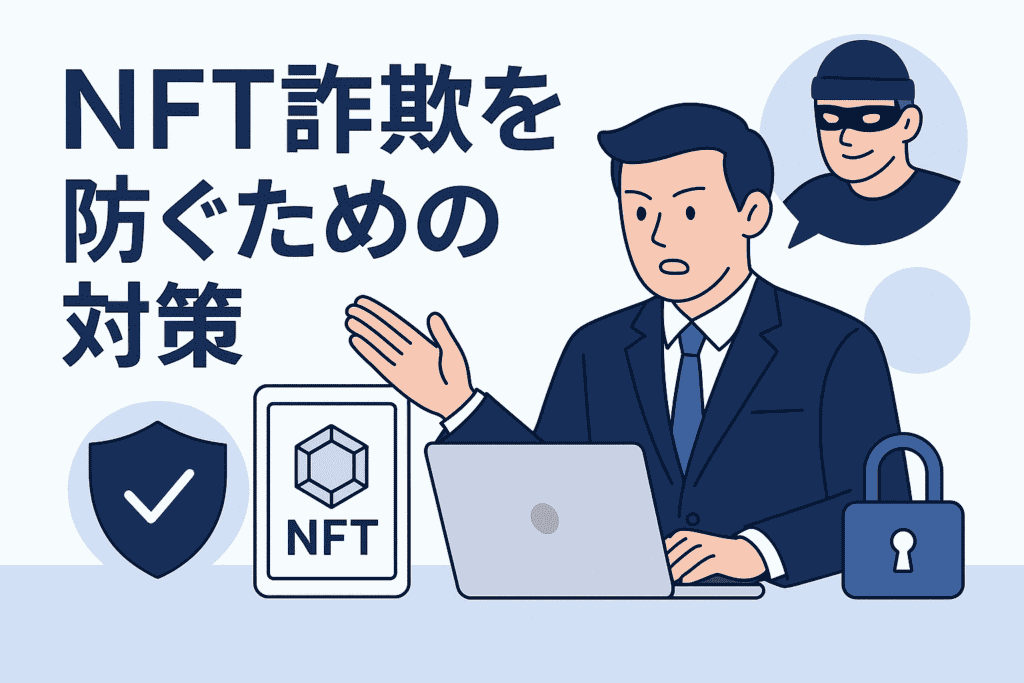
NFT詐欺の手口を理解した上で、次に重要になるのが、具体的な防御策を講じることです。ここでは、ご自身の資産を詐欺から守るために、今日から実践できる具体的な対策を解説します。
ウォレット運用の安全対策(用途分け・承認撤回・ハードウェアウォレット)
ウォレットの管理方法は、NFTのセキュリティにおいて最も重要な要素の一つです。まず、ウォレットを用途に応じて複数使い分けることを強く推奨します。高額なNFTや長期保有する資産を保管しておくための「保管用ウォレット」と、日常的にミントや取引で利用する「普段使い用ウォレット」を分け、普段使いのウォレットには必要最低限の資産しか入れないようにします。これにより、万が一普段使いのウォレットが攻撃されても、被害を最小限に抑えることができます。
次に、定期的な承認の撤回(リボーク)です。サイトにウォレットを接続して取引を行うと、そのサイトのスマートコントラクトに対して資産へのアクセスを「承認(Approve)」した状態になります。不要になった承認を放置しておくと、そのサイトがハッキングされた場合に資産を盗まれるリスクが残ります。Revoke.cashなどのツールを使い、定期的に不要な承認を解除する習慣をつけましょう。
そして、最も安全性の高い対策がハードウェアウォレットの導入です。ハードウェアウォレットは、秘密鍵をオフラインの専用デバイスで管理するため、オンライン上のハッキングリスクをほぼ完全に遮断できます。大切な資産はハードウェアウォレットで保管することが、現在の最善策と言えます。
秘密鍵やシードフレーズを守るための行動
秘密鍵(プライベートキー)とシードフレーズ(リカバリーフレーズ)は、ウォレットの全資産にアクセスするための「マスターキー」です。これを失ったり、他人に知られたりすることは、銀行の金庫の鍵を渡すのと同じ行為です。
絶対に、いかなる理由があっても、秘密鍵やシードフレーズを他人に教えてはいけません。 サポート担当者や運営者を名乗る人物から尋ねられても、絶対に応じないでください。
また、これらの情報はデジタルデータとして保管しないことが鉄則です。パソコンのメモ帳やスマートフォンのメモアプリ、クラウドストレージなどに保存すると、ハッキングやウイルス感染によって流出するリスクがあります。必ず紙に書き写し、金庫など物理的に安全な場所に複数保管するようにしてください。このアナログな管理方法が、結果的に最も安全です。
ブラウザ拡張やセキュリティツールの活用
NFT取引の安全性を高めるための、便利なツールも登場しています。これらを活用することで、詐欺のリスクを事前に検知し、回避することが可能になります。
例えば、「KEKKAI」や「Pocket Universe」といったブラウザの拡張機能は、ウォレットでトランザクションに署名する前に、その取引が安全かどうかをシミュレーションし、危険性を警告してくれます。資産が盗まれる可能性のある悪意のある契約に署名しようとすると、「この取引は危険です」といったアラートが表示され、被害を未然に防ぐことができます。
また、フィッシングサイトや詐欺サイトを検知して警告を発する機能を持つセキュリティソフトの導入も有効です。これらのツールを補助的に利用することで、ヒューマンエラーによる被害を減らすことができます。
公的機関や公式コミュニティの情報確認習慣
詐欺に関する最新情報や注意喚起は、信頼できる情報源から得るように心がけましょう。
警察庁や国民生活センターなどの公的機関は、サイバー犯罪や消費者トラブルに関する注意喚起をウェブサイトで定期的に行っています。これらの情報は信頼性が高く、社会的な詐欺の傾向を把握する上で非常に役立ちます。
また、自分が参加しているNFTプロジェクトの公式DiscordやX(旧Twitter)を日常的にチェックすることも重要です。プロジェクト内で詐欺被害が報告された場合、運営チームは迅速に注意喚起を行います。コミュニティからのリアルタイムな情報を得ることで、新たな手口にも対応しやすくなります。信頼できる情報源を複数持ち、常にアンテナを張っておくことが重要です。
高利回りや限定オファーを疑う意識の持ち方
最後に、最も重要なのは精神的な防御策、つまり「うまい話はまず疑う」という意識を持つことです。
「リスクなしで絶対に儲かる」「今だけの限定オファー」「あなただけに特別な価格で」といった、射幸心を過度に煽る言葉が出てきたら、それは詐欺である可能性が極めて高いです。特に、面識のない相手からDMでこのような話を持ちかけられた場合は、100%詐欺だと断定して問題ありません。
詐欺師は、人間の「欲」や「焦り」といった心理的な弱みにつけ込んできます。取引を行う前には必ず一呼吸おき、「これは本当に信頼できる話か?」「リスクはないか?」と自問自答する冷静さを保つことが、あらゆる詐欺から身を守るための最も強力な盾となります。
NFT詐欺の事例と得られる教訓
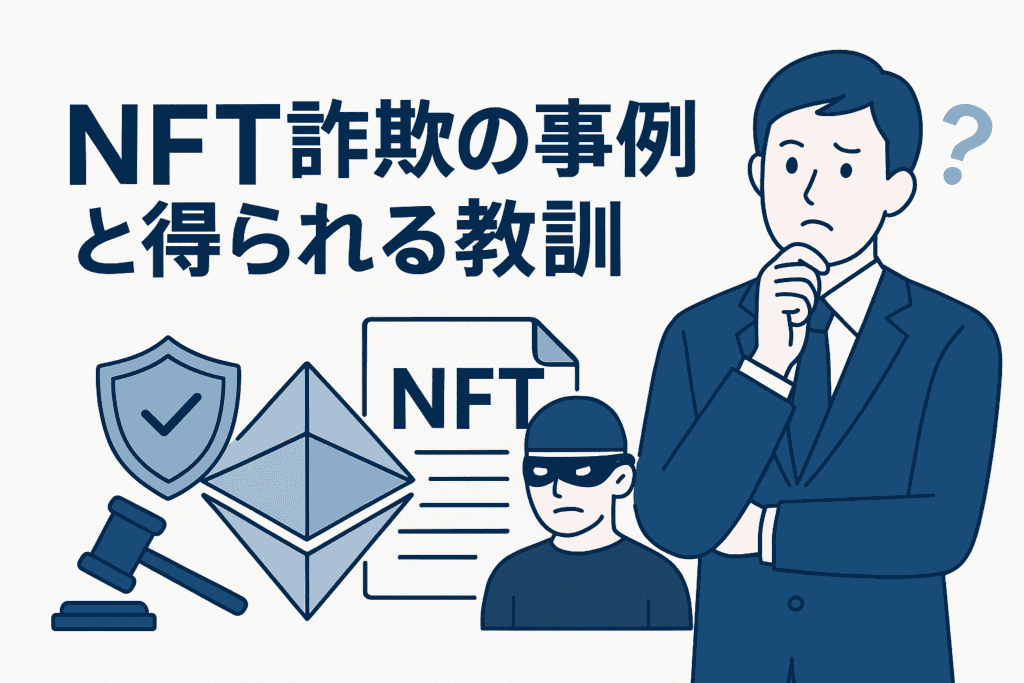
理論だけでなく、実際に起きた事件から学ぶことは非常に重要です。ここでは、国内外で発生した代表的なNFT詐欺の事例を紹介し、そこから得られる教訓を考えます。
国内で発生したNFT詐欺事件の概要
日本国内でも、NFTに関する詐欺事件は多数報告されており、その中でも特に有名なのが、人気NFTコレクションの偽サイトによるフィッシング詐欺です。
例えば、国内で絶大な人気を誇る「CryptoNinja Partners (CNP)」などの有名プロジェクトでは、セールやイベントのタイミングを狙って、本物そっくりの偽ミントサイトが複数出現しました。犯人は、X(旧Twitter)の広告機能などを悪用して偽サイトを宣伝し、多くの利用者を誘導。サイトにウォレットを接続してしまったユーザーのNFTや暗号資産が大量に盗まれるという被害が発生しました。
また、アーティスト個人を狙ったDM詐欺も後を絶ちません。「あなたの作品をNFTとして購入したい」と英語のDMで持ちかけ、偽のマーケットプレイスへの登録を促し、ガス代や登録料名目で金銭をだまし取る手口が横行しています。
海外の代表的なNFT詐欺事例
海外では、より大規模で組織的なNFT詐欺事件が発生しています。その代表例が「ラグプル」です。
2021年に起こった「Evolved Apes」事件では、猿をテーマにしたNFTプロジェクトが、魅力的な格闘ゲームの開発を約束して約1万点のNFTを販売しました。しかし、投資家から約270万ドル(当時のレートで約3億円)の資金を集めた後、開発者はプロジェクトのウェブサイトとXアカウントを突然削除し、すべての資金と共に姿を消しました。投資家の手元には、価値のなくなった猿の画像データだけが残されました。また、米司法省は「Frosties」という別のNFTプロジェクトでラグプルを行った容疑者を詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴しており、法執行機関による摘発も進んでいます。
また、有名人のアカウント乗っ取りによる詐欺も発生しています。2022年には、俳優のセス・グリーン氏がフィッシング詐欺に遭い、自身が保有していた人気NFTコレクション「Bored Ape Yacht Club (BAYC)」を含む複数の高額NFTを盗まれました。この事件は、NFTに詳しい著名人ですら被害に遭う危険性があることを示しています。
実例から学べる共通の注意点
これらの国内外の事例から、私たちはいくつかの重要な教訓を得ることができます。
第一に、「公式」の確認を徹底することです。CNPの事例が示すように、詐欺師は本物と見分けがつかないレベルで偽サイトを作成します。リンクをクリックする前には、それが本当に公式サイトや公式SNSから発信されたものなのかを、複数の情報源でクロスチェックする癖をつけなければなりません。
第二に、プロジェクトの匿名性リスクを理解することです。Evolved Apes事件のように、開発チームの身元が不明なプロジェクトは、資金を持ち逃げする「ラグプル」のリスクが常に伴います。投資を行う際は、チームの信頼性や実績を慎重に見極める必要があります。
そして最後に、個人のセキュリティ意識が最後の砦であることです。セス・グリーン氏の事件は、どんなに価値のあるNFTを保有していても、たった一度のミスで全てを失う可能性があることを教えてくれます。シードフレーズの管理や不審なリンクへの警戒など、基本的なセキュリティ対策の徹底が何よりも重要です。
NFT詐欺に遭った場合の初動対応と返金請求方法
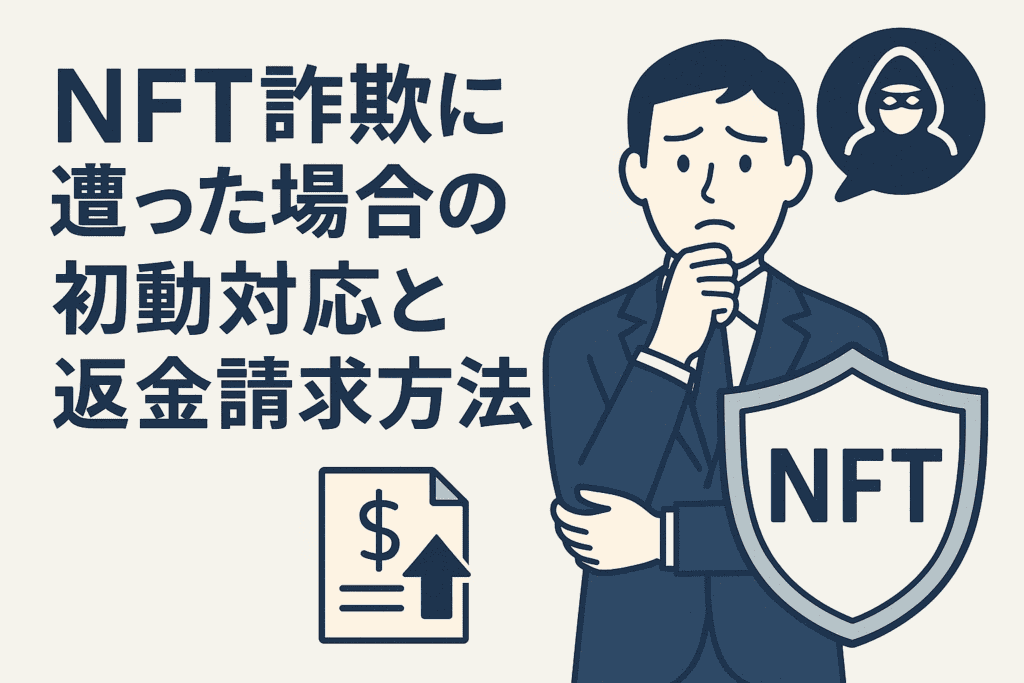
万全の対策を講じていても、残念ながら詐欺被害に遭ってしまう可能性はゼロではありません。もし被害に遭ってしまった場合、パニックにならずに冷静に行動することが、被害の拡大を防ぎ、将来的な解決の可能性を高める鍵となります。
証拠保全(スクリーンショット・取引記録・DM履歴)
被害に気づいたら、まず最初に行うべきことは証拠の保全です。これは、後の警察への相談や法的手続きにおいて、極めて重要な役割を果たします。
以下の情報を、可能な限りスクリーンショットやデータで保存してください。
- 詐欺師とのやり取り: SNSのDM、メール、LINEのトーク履歴など、相手とのすべてのコミュニケーション記録。
- 詐欺サイトの情報: アクセスした偽サイトのURLや画面のスクリーンショット。
- 取引の記録: ブロックチェーンエクスプローラー(Etherscanなど)で確認できる、資産が盗まれたトランザクション(取引履歴)のIDや、相手のウォレットアドレス。
- 送金記録: もし銀行振込などで金銭を送金してしまった場合は、その振込明細。
これらの証拠は、時間が経つと相手に削除されたり、アクセスできなくなったりする可能性があります。気づいた時点ですぐに、抜け漏れなく保存することを心がけてください。
承認撤回やウォレット移動などの技術的対応
証拠保全と並行して、さらなる被害を防ぐための技術的な対応も迅速に行う必要があります。
偽サイトにウォレットを接続し、何らかの承認(アプルーバル)をしてしまった場合は、まず承認の撤回(リボーク)を行います。「Revoke.cash」などのツールを利用し、不審なコントラクトへの承認をすべて取り消してください。これにより、詐欺師があなたのウォレットからこれ以上資産を抜き取ることを防ぎます。
もしウォレットのシードフレーズや秘密鍵自体を教えてしまった場合は、そのウォレットはもはや安全ではありません。直ちに新しいウォレットを作成し、残っている資産をすべて新しいウォレットに移動させてください。犯人との競争になるため、一刻を争う行動が求められます。
公的相談窓口(警察・消費者センター)への連絡
技術的な対応が一段落したら、公的な機関に相談しましょう。
まず、最寄りの警察署またはサイバー犯罪相談窓口に被害届を提出します。その際には、保全した証拠を持参してください。NFT詐欺は新しいタイプの犯罪であるため、すべての警察官が詳しいとは限りませんが、被害の事実を公的に記録してもらうことが重要です。緊急性のない相談であれば、警察相談専用電話「#9110」に連絡するのもよいでしょう。
また、事業者との契約トラブルなどの側面がある場合は、消費者ホットライン「188」に電話して、消費生活センターに相談することも有効です。同様の被害事例や対処法について、アドバイスをもらえる可能性があります。
これらの公的機関への相談は、直接的な返金に繋がるケースは少ないかもしれませんが、事件の解決や再発防止に向けた第一歩となります。
弁護士へ相談するメリット
NFT詐欺の被害回復や返金請求を本格的に目指す場合、弁護士への相談が最も現実的かつ効果的な選択肢となります。
NFTや暗号資産に関する詐欺は、国境を越えた取引や技術的な専門性が絡むため、個人で対応するには限界があります。この分野に詳しい弁護士に相談することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 法的な解決の見通しが立つ: ご自身のケースが法的にどのような手段を取りうるのか、専門的な見地からアドバイスを受けられます。
- 加害者の特定: 弁護士は、裁判所の手続きを通じて、暗号資産交換業者などに対し、詐欺師のウォレットに関連する個人情報の開示を請求できる場合があります。
- 返金交渉や訴訟: 加害者が特定できた場合、代理人として返金の交渉を行ったり、損害賠償請求訴訟を提起したりすることが可能です。
泣き寝入りする前に、一度専門家である弁護士に相談し、ご自身の権利を守るために何ができるのかを検討することが重要です。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
NFT詐欺の返金は泣き寝入りせず弁護士に相談を
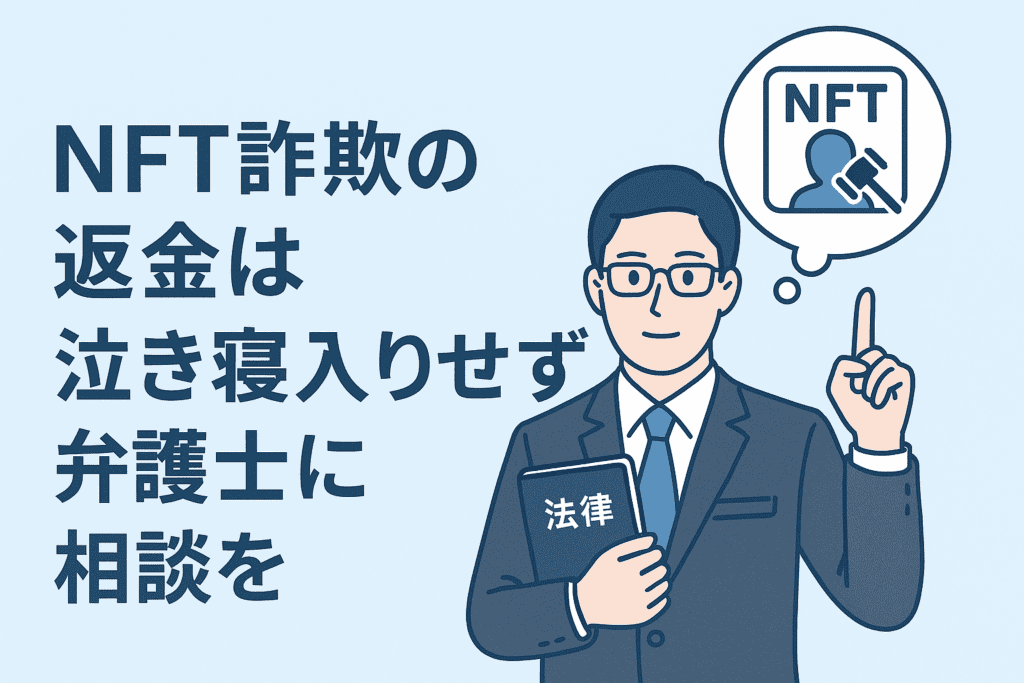
NFT詐欺の被害に遭うと、「もう取り返せない」と絶望的な気持ちになり、誰にも相談できずに泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。確かに、犯人の特定や資産の回収は容易ではなく、その道のりは決して平坦ではありません。
しかし、諦める必要はありません。
詐欺師は、被害者が泣き寝入りすることを見越して犯行に及んでいます。だからこそ、被害者が声を上げ、専門家と共に法的な手続きを進めることが、詐欺の連鎖を断ち切る力になります。
私たち弁護士法人FDR法律事務所は、NFTや暗号資産といった最先端分野の詐欺被害の解決に力を入れています。最新の技術や法規制を常に研究し、被害に遭われた方一人ひとりの状況に合わせた最善の解決策をご提案いたします。
「どこから手をつけていいかわからない」「こんなことを相談してもいいのだろうか」と一人で悩まず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。あなたがお持ちの証拠を基に、返金の可能性や今後の見通しについて、専門家の視点から誠実にお答えします。
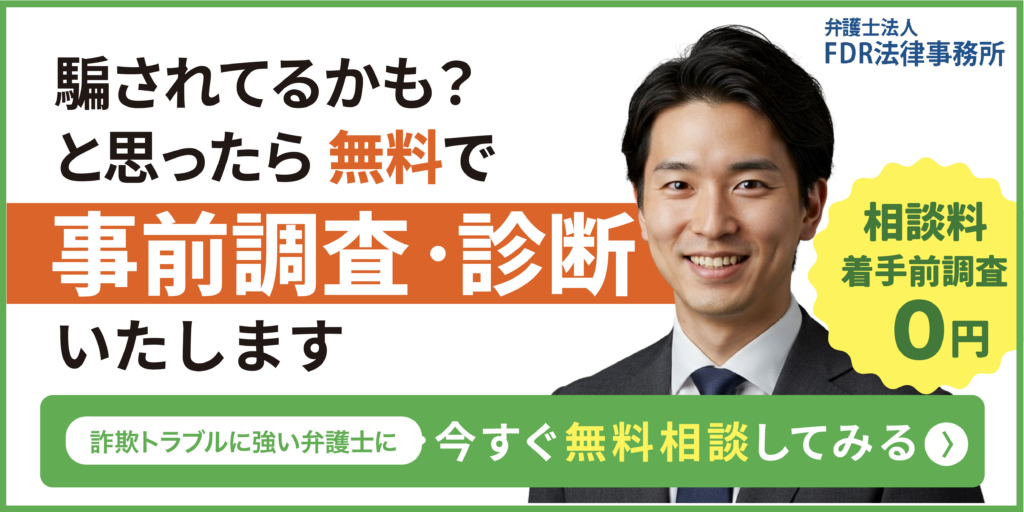
\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます