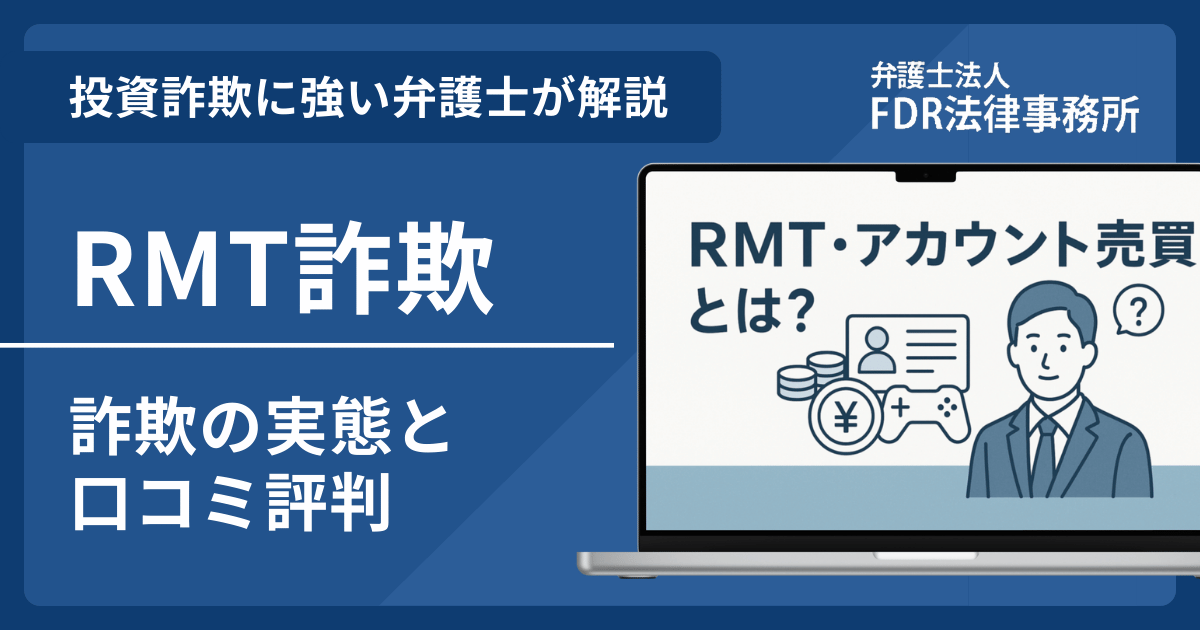オンラインゲームの世界では、アイテムやアカウントを現実のお金で取引する「RMT(リアルマネートレード)」や「アカウント売買」が広がっています。しかし、その裏側には詐欺被害やアカウント乗っ取り、規約違反によるアカウント停止といった大きなリスクが潜んでいます。
「安全に取引したい」と考える人も、「すでに詐欺に遭ってしまった」という人も、まずは正しい知識を持つことが不可欠です。本記事では、RMTやアカウント売買の仕組み、代表的な詐欺の手口、実際の法的リスク、そして被害に遭った場合の具体的な対処法を解説します。最後には、返金や加害者特定に向けて弁護士へ相談すべき理由についても紹介します。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
RMT・アカウント売買とは?

RMT(Real Money Trading)は、オンラインゲーム内のアイテムや通貨、キャラクターを現実のお金で取引する行為です。アカウント売買も広義のRMTに含まれ、ゲームアカウントそのものを売買するケースもあります。
一見するとプレイヤー同士の自由な取引のように見えますが、ほとんどのゲーム運営会社は利用規約で禁止しており、アカウント停止や削除の対象となります。さらに、詐欺被害が非常に多く、未成年者を中心に深刻なトラブルが頻発しています。
RMT・アカウント売買の主な詐欺手口
オンラインゲームにおけるRMTやアカウント売買は、一見すると簡単に利益を得られるように思えます。しかし実際には、詐欺被害やアカウント停止など大きなリスクが潜んでいます。特に被害が多いのは「先払い詐欺」「アカウント乗っ取り」「課金代行・チート代行詐欺」の3つです。それぞれの手口は年々巧妙化しており、SNSや掲示板を中心に被害報告が後を絶ちません。ここでは、代表的な詐欺手口の特徴と被害が発生する仕組み、そして予防策を詳しく解説します。
先払い詐欺(前払い未送付・未払い)
もっとも典型的な被害が「先払い詐欺」です。SNSや掲示板で「即日対応可能」「評価多数」といった文言で安心させ、代金を先に振り込ませる手口です。しかし、支払い後にアカウントやアイテムは送られてこない、あるいは逆にアイテムを渡したのに代金が支払われないといったトラブルが発生します。中には「保証金」や「本人確認料」と称して追加請求を繰り返す二重詐欺もあります。
被害を防ぐには、個人間での前払い取引は避け、第三者の正規エスクローサービスを利用することが不可欠です。被害後は振込明細ややり取りのスクリーンショットを必ず保存し、銀行やカード会社への連絡と併せて警察や消費者ホットラインに相談することが重要です。被害額が大きい場合や相手を特定したい場合は、弁護士に相談し、返金交渉や法的手続を進めることが現実的な解決策となります。
アカウント乗っ取り(フィッシング・なりすまし)
「本人確認」や「セキュリティ強化」と称して、偽サイトに誘導してログイン情報を入力させるのがアカウント乗っ取りの典型例です。最近では、二段階認証のワンタイムパスワードまでリアルタイムで盗み取るケースも増えています。さらに、身分証明書や自撮り画像を送らせて個人情報を悪用する事例もあります。
乗っ取り後は、ゲーム内の資産が売却されたり、フレンドに詐欺勧誘が送られたり、最悪の場合はアカウントが永久停止になることもあります。
予防策としては、ID・パスワードの使い回しを避け、二段階認証を必ず有効化し、ログインは必ずブックマークから行うことが大切です。被害に遭った場合は、速やかに全サービスのパスワードを変更し、運営に通報してログを保全してもらいましょう。身分証や資産が不正利用された可能性がある場合は、弁護士に相談することで加害者特定や被害拡大防止に向けた対応が可能です。
課金代行・チート代行詐欺
「公式より安く課金できます」「短時間でランクを上げます」といった誘いで利用者を引き込むのが課金代行・チート代行詐欺です。実態は盗用クレジットカードによる不正チャージであることが多く、後日チャージバックが発生すれば、利用者のアカウントは不正通貨の没収や停止処分を受けるリスクがあります。
さらに、依頼者自身も「不正と知りながら利用した」と評価されれば、詐欺の共犯や業務妨害として処罰対象となることがあります。チート代行では、アカウントを貸している間にデータを抜かれたり、設定を改ざんされてBANされる事例が後を絶ちません。「安すぎる取引」「BAN一切なし保証」といった甘い言葉には必ず裏があります。被害に遭った場合は、運営会社への早急な連絡と証拠保全が欠かせません。
高額被害やアカウント停止の撤回を求める場合には、法的交渉が必要となるため、弁護士に相談することが解決への近道です。
RMT詐欺の具体的な事例

実際の被害者の声を見てみると、RMT詐欺がいかに巧妙に仕組まれているかが分かります。以下は寄せられた口コミを参考にした具体的な事例です。
RMTで多発する“取り返し詐欺”
ゲームトレードというRMTサイトで恐らくですが取り返し詐欺に遭いました。
Yahoo!知恵袋
10万円で購入したアカウントを先日引き継ぎ、数日はプレイできていたのですが、今日プレイしようとしたら「別端末に引き継がれた」と表示されてしまいました。
前の持ち主の方以外に心当たりがなく、問い合わせをしたいのですが既に退会してしまっています。ゲームトレードの規約では警察が動けば開示請求可能とのことでしたが、アカウントを取り返されたという証拠がない以上警察は動いてくれませんよね?例えば、取り返したアカウントをもう一度出品しているとかなら可能なのでしょうか。また、今回の件で返金対応していただくにはどうすれば良いのでしょうか。
RMTサイトでの「取り返し詐欺」は、売却者が後から不正アクセスしてアカウントを奪い返す典型的な手口です。規約上は自己責任とされることが多く返金は困難ですが、金銭の授受ややり取りの証拠を整理すれば、民事的に返金請求できる可能性も残されています。被害を放置せず、早めに弁護士へ相談して法的手段を検討することが、被害回復への唯一の現実的な道です。
フィッシング型RMT詐欺
ゲームトレードで詐欺にあいました。
購入したらアドレスを教えてくれないとアカウント情報教えられないと言われ、ゲームトレードには使用していないアドレスを教えてしまいました。教えたアドレスにURLが送られてきてそれにアクセスしろと言うのでアクセスしたらゲームトレードにログインするとあり、ログイン情報を入力してしまいました。アドレスの方に認証番号を返信しろと指示があり従いました。
そしたらレビュー済みとなり、これは詐欺だなと確信しました。
アカウント情報を教えてもらったのですが当たり前にログインは出来ず、その旨を伝えると、他のアカウント情報を買取しろ。買取したら24時間後に自動返金される。としつこく催促され、不安なので問い合わせましたと返事をしたら退会されたようです。不審だなと思いながらアドレスを教えた自分も悪いので代金は諦めているのですが、カード情報が抜き取られていないか心配です。(すぐにペイパルに登録してあるカード情報は削除しました)
またゲームトレードに登録したアドレスがiCloudなのでそれも心配です。何もないなら勉強代として終わりでいいのですが、今からできる対処法ありますでしょうか?
Yahoo!知恵袋
このケースは、いわゆる「フィッシング型」のRMT詐欺です。外部のアドレスを使わせ、偽のログインページに誘導して情報を入力させるのは典型的な手口で、被害者の心理を利用してさらに別のアカウント購入を迫るのも特徴です。カード情報を削除したことは正しい対応ですが、念のため利用明細の監視やパスワード変更、二段階認証の設定が必須です。被害金を取り戻すのは難しいため、弁護士や警察に証拠を持ち込むことが再発防止にもつながります。
他にもRMT詐欺の具体的な事例としては以下のようなものが挙げられます。
| 詐欺の種類 | 手口の概要 | 被害の内容 | 特徴的なポイント |
|---|---|---|---|
| フリマアプリでのアカウント販売詐欺 | フリマアプリに高レベルアカウントを出品し、購入者から代金を受け取った後にアカウント情報を渡さず逃走 | 数万円の金銭被害、運営からの補償なし | 規約違反取引のため運営の救済対象外、警察が詐欺罪で立件 |
| SNSのDMによる先払い詐欺 | 「即日取引」などと勧誘し、PayPayやプリペイドカードで先払いさせて連絡を断つ | 少額から高額までの金銭被害、追加被害に発展 | 「取引実績」の偽スクショ、信頼させてから高額詐欺を仕掛けるステップ型 |
| 課金代行詐欺(逮捕事例あり) | 「正規より安く課金」と宣伝し、盗用クレカで不正チャージ | アカウント停止、通貨没収、依頼者も共犯として逮捕 | 「安さ」に惹かれた利用者が加害者側に立たされるリスク |
| アカウント乗っ取り詐欺 | 「高額で買い取る」と持ちかけてID・PWを入手し、乗っ取り | アカウント資産流出、二次被害としてフレンドへの詐欺勧誘 | 二段階認証を突破されると復旧が困難、被害が連鎖的に拡大 |
RMT詐欺の見分け方と危険サイン

RMTやアカウント売買は、表面上は魅力的に見えても、多くが詐欺や不正行為に結びついています。特にSNSや掲示板を中心に横行する取引は、初心者ほどだまされやすい傾向があります。ここでは、典型的な「危険サイン」と、その見分け方を整理しました。少しでも当てはまる点があれば、取引を中止し慎重に対応することが重要です。
不自然に安い価格や限定勧誘
希少アイテムや高レベルアカウントが、相場より極端に安い値段で提示されている場合は注意が必要です。「本日限り」「残り1枠」などと購入を急がせる勧誘文句も典型的なサインです。こうした条件は、冷静に考えれば利益が出るはずがなく、ほとんどが詐欺目的です。
取引相手の情報が曖昧
事業者情報が不明瞭、口座名義と名乗りが一致しない、連絡先がSNSのDMしかない場合は要警戒です。特に、LINEやDiscordだけでやり取りを完結させようとする相手は、逃げることを前提にしている可能性が高いです。
追加料金や本人確認料を要求される
「保証金」「手数料」「本人確認のための身分証送付」などを求められたら、ほぼ詐欺と考えてよいでしょう。正規の取引ではこのような追加料金は発生しませんし、身分証の提出を求められるケースも不自然です。個人情報の悪用にもつながる危険なサインです。
偽サイトや偽ログインページへの誘導
本物そっくりのログイン画面や決済ページを用意し、IDやパスワード、さらには二段階認証コードを入力させる手口があります。URLを確認すると、ドメインが微妙に違っていたり、不自然な短縮URLが使われていることが多いです。公式サイトは必ずブックマークからアクセスするのが鉄則です。
「BANなし保証」「安全代行」をうたう
課金代行やチート代行サービスで「絶対にBANされません」「安全です」と強調している業者は、まず信用できません。そもそも運営の規約違反であり、保証自体が成立しません。過去には依頼者側が共犯として逮捕された事例もあり、利用すること自体が大きなリスクです。
RMT詐欺は、安さ・即断・曖昧な情報・追加請求・偽サイトといったサインが揃っているのが特徴です。少しでも不審に感じたら、取引をやめるのが最善策です。万が一被害に遭ってしまった場合は、証拠を保全した上で、警察や弁護士に相談することが解決への第一歩となります。
RMT詐欺被害に遭ったらすぐやるべき初動対応

RMT詐欺は、一度入金してしまうと資金を取り戻すのが難しいのが現実です。しかし、初動の対応が早ければ早いほど、返金の可能性を高められるケースもあります。被害に気づいた時点で、以下の行動を速やかに取ることが重要です。
1. 入金を止める・追加送金は絶対にしない
詐欺業者は「出金に必要」「税金を払えば返金される」などの口実で、追加の送金を迫ってきます。しかし、これ以上応じても返金されることはありません。気づいた時点で入金をストップし、それ以上の被害拡大を防ぐことが第一歩です。
2. 振込先口座・取引履歴をすべて保存する
銀行振込やクレジットカード決済を行った場合は、振込先口座情報や決済明細を必ず保存してください。これらは返金請求や警察への相談の際に必要な証拠になります。スクリーンショットでも構いませんが、できるだけ正式な取引明細を入手しましょう。
3. 銀行・カード会社に連絡する
振込を行った金融機関に事情を説明し、振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の対象になるか確認します。クレジットカード決済の場合は、不正利用としてチャージバック手続きを依頼できるケースもあります。初動が遅れると対応が難しくなるため、できるだけ早く連絡することが肝心です。
4. 警察・消費生活センターへ相談する
被害を公式に記録として残すため、最寄りの警察署や消費生活センターに相談しましょう。警察のサイバー犯罪相談窓口では、詐欺サイトや運営者の追跡を進めてくれる場合があります。複数の被害者が声を上げることで、摘発につながる可能性も高まります。
5. 弁護士への相談を検討する
個人での対応に限界を感じた場合は、詐欺被害に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。海外業者が絡むケースや高額被害では、専門家による交渉や法的手段が返金の糸口になる可能性があります。
被害拡大を防ぐための行動
詐欺に気づいた後の行動を、フローチャートで整理します。パニック状態でも、この流れに沿って冷静に行動してください。
- 【詐欺だと認識】:「おかしい」「騙されたかも」と感じる。 ↓
- 【連絡を遮断】(最優先)
- LINE、メール、電話など、全ての連絡先をブロック。
- サイトのアカウント・LINEなどのグループを退会(可能であれば)。
- 相手からの連絡には一切応じない。 ↓
- 【証拠を保全】
- やり取りの履歴、相手のプロフィール、サイト情報、支払いの記録などをスクリーンショット等で保存。 ↓
- 【決済機関へ連絡】(支払い方法による)
- クレジットカードの場合:カード会社に連絡し、不正利用の調査と支払い停止(チャージバック)を依頼。
- 銀行振込の場合:振込先の金融機関と警察に連絡し、口座凍結を依頼。 ↓
- 【専門家へ相談】
- 詐欺返金に強い司法書士や弁護士などの専門家へ無料相談する。
- 消費生活センター(188)や警察(#9110)へ相談する。
このフローで最も重要なのは、一人で解決しようとせず、早い段階で専門家に相談することです。特に返金交渉は専門的な知識が必要です。詐欺被害に強い司法書士や弁護士は、被害者の代理人として冷静かつ法的に交渉を進めてくれます。多くの事務所では無料相談を実施しているので、まずは気軽に連絡してみましょう。
RMT詐欺の返金方法と可能性

「騙し取られたお金はもう戻ってこない」と諦めてしまうのはまだ早いです。支払い方法によっては、返金を受けられる可能性があります。ただし、返金交渉は時間との勝負であり、専門的な知識も必要です。
この章では、決済方法別の返金手続きや、そのために必要な準備について解説します。
- クレジットカード決済での返金交渉(チャージバック):カード会社の補償制度を利用します。
- 銀行振込での振り込め詐欺救済法の利用:相手の口座を凍結する制度です。
- 電子マネー・ウォレット決済の返金可能性:返金が難しいケースと対処法を解説します。
- 返金請求に必要な証拠と文面例:交渉を有利に進めるための準備について説明します。
クレジットカード決済での返金交渉(チャージバック)
クレジットカードで支払ってしまった場合、「チャージバック(支払異議申し立て)」という手続きを利用できる可能性があります。これは、不正利用や加盟店とのトラブルがあった際に、カード会社が売上を取り消し、利用者に返金する制度です。
チャージバックを申請するには、まずクレジットカード会社に連絡し、「RMT詐欺に遭い、意図しない決済だった」という旨を伝えます。その際、なぜその決済が不当なのかを具体的に説明する必要があります。事前に集めた証拠(サイトのURL、相手とのやり取りなど)を提出することで、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
ただし、チャージバックは必ず成功するとは限りません。カード会社の調査の結果、返金が認められないケースもあります。また、申請には期限が設けられていることが多いため、被害に気づいたら一日でも早くカード会社に連絡することが重要です。自力での交渉に不安がある場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
銀行振込での振り込め詐欺救済法の利用
銀行振込でお金を支払ってしまった場合は、「振り込め詐欺救済法」という法律に基づき、被害回復の申請ができます。この法律は、詐欺などに利用された疑いのある銀行口座を凍結し、その口座に残っているお金(残高)を被害者に分配する制度です。
手続きとしては、まずお金を振り込んだ金融機関と、最寄りの警察署に被害を申告します。警察から金融機関に対して情報提供が行われ、口座が犯罪に利用されたと判断されると、その口座は凍結されます。その後、預金保険機構のウェブサイトで公告が行われ、被害者は所定の期間内に被害回復分配金の支払い申請を行います。
この方法の注意点は、相手の口座にお金が残っていなければ返金されないことです。詐欺師はすぐに現金を引き出してしまうため、一刻も早い対応が求められます。また、他にも被害者がいる場合は、口座残高を被害額に応じて按分するため、全額が返ってくるとは限りません。それでも、被害を回復するための有効な手段の一つですので、すぐに金融機関と警察に相談しましょう。
電子マネー・ウォレット決済の返金可能性
近年、PayPayやLINE Payなどの電子マネー(ウォレット決済)や、コンビニで購入できるプリペイド式の電子ギフト券(Apple Gift Card、Google Playギフトカードなど)で支払いを要求する詐欺が増えています。これらの決済方法は、匿名性が高く、一度送金すると取り消しが非常に困難なため、詐欺師に好まれます。
残念ながら、電子マネーやギフト券での支払いは、クレジットカードや銀行振込に比べて返金される可能性が低いのが現状です。しかし、諦める必要はありません。まずは、利用した決済サービスの運営会社に詐欺被害を報告し、相手のアカウント凍結や送金の取り消しが可能か問い合わせましょう。
同時に、警察にも必ず被害届を提出してください。すぐに返金に繋がらなくても、捜査によって犯人が検挙されれば、将来的に損害賠償請求ができる可能性があります。被害額が少額でも泣き寝入りせず、まずは関係各所に相談することが大切です。
返金請求に必要な証拠と文面例
自力で返金請求を行う場合、内容証明郵便を利用する方法があります。これは、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスで、相手に心理的なプレッシャーを与え、支払いを促す効果が期待できます。
内容証明には、以下の内容を簡潔かつ明確に記載します。
- 通知書
- 通知人(自分)の氏名・住所
- 被通知人(相手事業者)の名称・住所
- 請求の趣旨:「貴社に対し、以下の通り金〇〇円の返金を請求いたします。」
- 請求の原因:契約日、サービス内容、支払った金額、詐欺だと判断した理由(例:「『必ず稼げる』と説明されたが、実際には全く稼げず、説明と事実が異なるため」など)を時系列で記載。
- 請求金額
- 支払期限:「本書面到達後、〇日以内に下記口座へお振り込みください。」
- 振込先口座情報
- 日付と署名
ただし、内容証明には法的な強制力はなく、相手が無視すればそれまでです。また、文面に不備があると効果がありません。より確実な返金を目指すなら、法律の専門家である司法書士や弁護士に依頼するのが最善の策です。専門家は、法的な観点から適切な請求書を作成し、代理人として相手と交渉してくれます。まずは専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
RMT詐欺の相談窓口と頼れる支援先

「誰に相談すればいいかわからない」と一人で抱え込むことが、最も危険です。RMT詐欺の被害に遭った場合、相談できる公的な窓口や専門家が存在します。それぞれの窓口の役割を理解し、自分の状況に合った支援先を選びましょう。
この章では、信頼できる相談窓口と、それぞれの特徴や利用方法について解説します。
- 消費者ホットライン(188)と消費生活センター:契約トラブル全般の相談窓口です。
- 警察相談専用電話(#9110)と被害届の提出:事件性がある場合の相談先です。
- 弁護士・司法書士への相談と費用感:法的な解決や返金交渉の専門家です。
- 未成年・若年層の相談時の注意点:特に知っておくべきポイントを解説します。
消費者ホットライン(188)と消費生活センター
契約に関するトラブルで困ったときに、まず頼りになるのが消費者ホットライン「188(いやや!)」です。ここに電話をかけると、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターや自治体の消費生活相談窓口を案内してもらえます。相談は無料で、専門の相談員が事業者とのトラブル解決に向けた助言や情報提供をしてくれます。
消費生活センターでは、詐欺的な契約の問題点を整理し、今後の対応方法についてアドバイスをもらえます。場合によっては、事業者に連絡を取って交渉(あっせん)を行ってくれることもあります。
ただし、消費生活センターはあくまで中立的な立場で助言や交渉のサポートをする機関であり、代理人として法的な手続きを進めてくれるわけではありません。しかし、問題を客観的に整理し、次に取るべき行動を明確にするために非常に役立つ窓口ですので、まずは気軽に電話してみることをお勧めします。
警察相談専用電話(#9110)と被害届の提出
詐欺被害は犯罪ですので、警察に相談することも重要な選択肢です。緊急の対応が必要ない場合は、110番ではなく、警察相談専用電話「#9110」に電話しましょう。専門の相談員が話を聞き、状況に応じて必要な手続きや担当部署を案内してくれます。
「個人情報をばらまくぞ」と脅迫された、アカウントを乗っ取られたなど、明らかな犯罪行為(事件性)がある場合は、最寄りの警察署に出向いて被害届の提出を検討します。被害届を提出する際は、事前に集めた証拠(スクリーンショット、振込履歴など)を持参すると話がスムーズに進みます。
ただし、警察の主な目的は犯人を捜査・検挙することであり、被害金の回収を直接手伝ってくれるわけではありません。また、「契約上のトラブル」と判断され、すぐには被害届が受理されないケース(民事不介入)もあります。それでも、被害の事実を公的な記録として残すことは、後の返金交渉などで有利に働く可能性もあるため、相談する価値は十分にあります。
弁護士・司法書士への相談と費用感
被害金の返還を最も強く望むのであれば、弁護士や司法書士といった法律の専門家への相談が最も効果的です。専門家は、被害者に代わって法的な手続きや相手事業者との交渉をすべて行ってくれます。
費用面が心配な方も多いと思いますが、詐欺返金に強い事務所の多くは、無料相談を実施しています。一人で悩まず、まずはプロの力を借りることを検討してください。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます