「突然、高額な支援金を譲渡するというメールが届いた」
「当選金を受け取るために手数料が必要だと言われたが、これは本当だろうか?」
このようなうまい話に、期待と同時に強い不安を感じていませんか。あるいは、すでにお金を支払ってしまい、「もしかして詐欺だったのでは…」と後悔や焦りを抱えているかもしれません。
近年、メールやLINEなどを利用した支援金詐欺・当選金詐欺が急増しており、その手口はますます巧妙になっています。警察庁の発表によると、令和5年中の特殊詐欺全体の被害額は約452.6億円にものぼり、自分は大丈夫と思っていても、誰でも被害に遭う可能性があるのが実情です。
この記事では、支援金詐欺や当選金詐欺の被害に悩む方に向けて、以下の内容を網羅的に解説します。
- 支援金詐欺・当選金詐欺の巧妙な仕組みと手口
- 被害に遭ってしまった場合に取るべき具体的な行動と相談窓口
- 支払ったお金を取り戻すための「返金手続き」の詳細
- 二度と騙されないための詐欺サイトやメールの見分け方
この記事を最後まで読めば、怪しい儲け話が詐欺かどうかを冷静に判断できるようになり、万が一被害に遭っても、泣き寝入りせず解決に向けて行動を起こすための一歩を踏み出せます。一人で抱え込まず、まずは正しい知識を身につけることから始めましょう。もし具体的な被害でお困りの場合は、私たち弁護士法人FDR法律事務所が無料でご相談に応じています。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
支援金詐欺や当選金詐欺とは?仕組みを解説

支援金詐欺や当選金詐欺は、一見すると幸運が舞い込んできたかのように思えますが、その実態は被害者から金銭を騙し取るための巧妙な罠です。まず、これらの詐欺がどのような仕組みで成り立っているのか、その本質を理解することが重要です。
このセクションでは、以下の2つのポイントから詐欺の全体像を解説します。
- 支援金詐欺・当選金詐欺の本質は「手数料詐欺」
- 本物の公的給付金との決定的な違い
支援金詐欺・当選金詐欺の本質は「手数料詐欺」
支援金詐欺や当選金詐欺の核心は、高額な金銭を受け取れるという期待感を煽り、そのための「手数料」や「登録料」といった名目で金銭を騙し取ることにあります。犯人たちは、最初から支援金や当選金を支払うつもりは一切ありません。
例えば、「1億円の支援金をお渡しします。受け取るにはまずサイトへの登録料として5,000円が必要です」といった手口が典型的です。被害者は「1億円が手に入るなら5,000円くらいは…」という心理状態に陥り、つい支払ってしまいます。しかし、一度支払うと犯人たちは「文字化け解除料」「セキュリティ費用」「送金手数料」など、次から次へと理由をつけて金銭を要求し続けます。被害者が詐欺だと気づいて支払いをやめるまで、被害額は雪だるま式に膨らんでいくのです。
このように、うまい話を見せ金にして、実際には少額(時には高額)の手数料を繰り返し支払わせることが、これらの詐欺の本当の目的です。したがって、理由の如何を問わず、金銭を受け取るために支払いを要求された場合は、その時点で詐欺であると強く疑う必要があります。
本物の公的給付金との決定的な違い
詐欺師は、信憑性を高めるために「国の機関」や「公的な団体」を名乗ることがありますが、本物の公的給付金と詐欺には決定的な違いがあります。それは、国や地方公共団体などの公的機関が、給付金の支給にあたって手数料や登録料の振込を求めたり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたりすることは絶対にないという点です。
この事実は、警察庁や消費者庁といった公的機関も強く注意喚起しています。本物の給付金は、原則としてマイナンバーカードを利用したオンライン申請や、自治体から送付される確認書を返送するといった正規の手続きを経て、指定の口座に直接振り込まれます。申請手続きで不明な点があれば、必ずお住まいの市区町村の役所の窓口に直接問い合わせましょう。
「公的機関から」と名乗るメールや電話であっても、少しでも金銭の支払いを匂わせる内容であれば、それは詐欺です。相手の言うことを鵜呑みにせず、一度立ち止まって公式な情報源を確認する冷静さが、被害を防ぐ上で最も重要になります。
支援金詐欺の手口とは?典型的なパターン

支援金詐欺や当選金詐欺の犯人たちは、私たちの日常に巧みに紛れ込み、さまざまな手口で罠を仕掛けてきます。ここでは、被害に遭わないために知っておくべき典型的な手口を具体的に解説します。
- LINEやSMSで突然届く「1億円当選」「支援金譲渡」の通知
- 手数料を要求する巧妙な支援金詐欺サイトへの誘導
- 「生活支援救済金」など公的機関を装う詐欺メールの文面例
- 少額の手数料を電子マネーや銀行振込で繰り返し要求する
LINEやSMSで突然届く「1億円当選」「支援金譲渡」の通知
ある日突然、スマートフォンに「【当選通知】1億円が当たりました」「資産家の〇〇です。遺産の一部である5,000万円を支援金としてお譲りします」といった内容のメッセージが届くのが、詐欺の入り口として非常に多いパターンです。送信元は、実在の企業や富豪、あるいは慈善団体などを騙っていることが多く、一見すると信じてしまいそうになります。
これらのメッセージには、必ずと言っていいほど「詳細はこちら」「受け取り手続きに進む」といった文言と共にURLが記載されています。このリンクは、個人情報を入力させたり、金銭を騙し取ったりするための詐欺サイトに繋がっています。見知らぬ送信元からの甘い誘いには絶対に乗らず、メッセージは無視して削除することが鉄則です。特に、国民生活センターが注意喚起しているように、宝くじや懸賞に応募した覚えがないにもかかわらず当選通知が届いた場合は、100%詐欺だと考えて間違いありません。安易にURLをタップしないよう、くれぐれも注意してください。
手数料を要求する巧妙な支援金詐欺サイトへの誘導
LINEやメールのリンクをタップすると、非常に巧妙に作られた支援金詐欺サイトに誘導されます。これらのサイトは、一見すると公的機関や大手企業の公式サイトのように見えますが、実際には金銭を騙し取るためだけの偽物です。サイト上では、支援金や当選金を受け取るための手続きと称して、氏名、住所、電話番号、銀行口座といった個人情報の入力を求められます。
そして、手続きの最終段階で「本人確認のための手数料」「サイト登録料」といった名目で、数千円から数万円の支払いを要求してきます。サイト内では、他の利用者からの「本当にお金がもらえました!」といった偽の感謝のコメント(サクラ)を掲載し、支払いを躊躇している利用者の背中を押そうとします。しかし、これらはすべて詐欺師が用意した自作自演です。一度でも支払いに応じてしまうと、前述の通り次々と追加の支払いを要求される悪循環に陥るため、絶対に支払ってはいけません。
「生活支援救済金」など公的機関を装う詐欺メールの文面例
詐欺師は、ターゲットを信用させるために公的機関を装う手口を多用します。例えば、「内閣府」「総務省」といった実在の省庁や、「国民生活センター」などの団体名を騙り、「生活支援救済金」「コロナ特別給付金」といった、もっともらしい名称の給付金が受け取れるかのようなメールを送ってきます。
これらのメールは、本物の通知と見分けがつきにくいように、ロゴやデザインを巧妙に模倣している場合があります。しかし、本文をよく読むと「申請手続きを簡略化するため、以下のサイトから登録してください」「手数料として電子マネーで3,000円分お支払いください」など、多くの自治体が指摘する不審な点が見つかります。前述の通り、公的機関がメールで個人サイトへ誘導したり、手数料の支払いを求めたりすることは絶対にありません。「生活支援救済金」という名称の公的な制度も存在しないため、このようなメールはすべて詐欺だと判断し、すぐに削除してください。
少額の手数料を電子マネーや銀行振込で繰り返し要求する
支援金詐欺で要求される手数料の支払い方法として、コンビニなどで購入できる電子マネー(ギフトカード型)が使われるケースが非常に多いのが特徴です。犯人たちがこの方法を好むのは、カードに記載された番号さえ入手すれば、誰が支払ったかを特定されずに金銭をだまし取ることができ、警察の捜査による追跡を困難にするためです。
「〇〇(電子マネー名)のカードを5,000円分購入し、裏面のコード番号を写真に撮って送ってください」といった指示は、詐欺の典型的な手口です。もちろん、銀行振込やクレジットカード決済を指示される場合もあります。いずれの方法であっても、一度支払ってしまうと「あなたの口座情報が間違っていた」「送金システムにエラーが発生した」などと理由をつけ、何度も支払いを要求してきます。被害額が数十万円から数百万円にまで膨れ上がるケースも少なくありません。最初の支払いに応じないことが、被害を最小限に食い止めるための鍵となります。
支援金詐欺の被害に遭ったら?すぐに相談すべき窓口とやるべきこと

万が一、支援金詐欺の被害に遭ってしまった、あるいは被害に遭ったかもしれないと気づいた場合、パニックにならずに冷静かつ迅速に行動することが何よりも重要です。一人で抱え込まず、すぐに以下の対応を取りましょう。
- まずは警察相談専用電話「#9110」へ連絡する
- 消費生活センター「188」で今後の対応を相談する
- 詐欺師とのやり取りや振込記録など証拠をすべて保存しておく
- クレジットカード情報を入力した場合はカード会社へ連絡を
まずは警察相談専用電話「#9110」へ連絡する
詐欺の被害に遭ったと確信したら、ためらわずに警察に相談してください。 緊急の事件・事故ではない場合は、110番ではなく、全国共通の警察相談専用電話である「#9110」に電話をかけましょう。専門の相談員が状況を詳しく聞き取り、被害届の提出方法や今後の対応についてアドバイスをしてくれます。
被害届を提出することで、警察が正式に捜査を開始するきっかけになります。犯人が逮捕されれば、被害金が返還される可能性も出てきます。また、被害届の受理番号は、後述する「振り込め詐欺救済法」による返金手続きの際に必要となる場合があります。たとえ被害額が少額であっても、「このくらいで警察に相談するのは…」と躊躇する必要はありません。あなたの通報が、他の被害者を救うことに繋がる可能性もあります。まずは勇気を出して、警察に連絡することが解決への第一歩です。
消費生活センター「188」で今後の対応を相談する
警察への相談と並行して、消費者ホットライン「188(いやや!)」にも電話しましょう。こちらは、商品やサービスの契約トラブル、悪質な事業者との問題など、消費生活全般に関する相談を受け付けている公的な窓口です。支援金詐欺も悪質な手口の一つとして、専門の相談員が対応してくれます。
消費生活センターでは、被害の状況に応じて、具体的な解決策や、他の適切な相談機関(弁護士会など)を紹介してくれます。また、同様の手口による被害相談が多数寄せられている場合もあり、有効な対処法に関する情報を持っている可能性があります。自分と同じような被害に遭った人がいると知るだけでも、精神的な負担が軽くなるかもしれません。中立的な立場から客観的なアドバイスがもらえるため、どうしていいか分からず混乱している場合には、まず「188」に電話して状況を整理することをお勧めします。
詐欺師とのやり取りや振込記録など証拠をすべて保存しておく
警察への相談や、後に行う返金請求の手続きにおいて、被害の事実を証明するための「証拠」が極めて重要になります。 詐欺だと気づくと、腹立たしさから相手とのやり取りを消去してしまいたくなるかもしれませんが、それは絶対にやめてください。以下のものは、すべて削除せずに大切に保存しておきましょう。
| 証拠の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 相手とのやり取り | メール本文、SMSのメッセージ、LINEのトーク履歴(スクリーンショット)、詐欺サイトのURLや画面のスクリーンショット |
| 支払いの記録 | 銀行の振込明細書、ATMの利用明細、購入した電子マネーのカード本体やレシート、クレジットカードの利用明細 |
| 相手の情報 | 相手の氏名(偽名の可能性大)、電話番号、メールアドレス、振込先の口座情報(銀行名、支店名、口座番号、名義人) |
これらの証拠は、被害の状況を客観的に説明し、犯人を特定したり、支払ったお金を取り戻したりするための強力な武器となります。できるだけ多くの情報を、整理してまとめておくように心がけてください。
クレジットカード情報を入力した場合はカード会社へ連絡を
もし詐欺サイトにクレジットカードの番号や有効期限、セキュリティコードなどを入力してしまった場合は、直ちに利用しているクレジットカード会社に連絡してください。 不正利用されてしまう前に、カードの利用を停止してもらう必要があります。
カード会社の連絡先は、カードの裏面に記載されています。24時間対応の紛失・盗難窓口に電話し、「詐欺サイトにカード情報を入力してしまった」と正直に伝えましょう。カード会社は利用停止の手続きを取るとともに、すでに不正な請求が上がっていないかを確認してくれます。もし不正利用による被害が発生していた場合でも、カード会社の補償制度によって被害額が補填される可能性があります。対応が早ければ早いほど、被害を未然に防いだり、拡大を食い止めたりできる可能性が高まります。少しでも不安を感じたら、すぐにカード会社へ連絡してください。
支援金詐欺の被害金は返金される?弁護士に相談するべき理由

被害に遭われた方が最も知りたいのは、「支払ってしまったお金は戻ってくるのか?」という点でしょう。結論から言うと、返金される可能性はゼロではありませんが、簡単な道のりではありません。 しかし、泣き寝入りせずに、利用できる制度や専門家の力を借りて行動を起こすことが重要です。
ここでは、返金を実現するための具体的な方法や、専門家である弁護士に相談するメリットについて解説します。
- 犯人の口座凍結を目指す「振り込め詐欺救済法」とは
- 被害回復分配金の申請手続きの流れと必要書類
- 返金請求は弁護士や司法書士への相談も有効な手段
- 返金が困難になりやすいケースも存在する
犯人の口座凍結を目指す「振り込め詐欺救済法」とは
銀行振込で被害に遭った場合に、返金の望みとなるのが「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」です。この法律は、詐欺などに利用された銀行口座を凍結し、その口座に残っているお金(犯罪被害資金)を、被害に遭った人たちに分配(返金)するための手続きを定めたものです。
この制度を利用するには、まずお金を振り込んでしまった金融機関に連絡し、被害の事実を申告する必要があります。金融機関が詐欺に利用された疑いがあると判断すれば、その口座を凍結します。その後、預金保険機構のホームページで口座の名義や残高などが公告され、被害者は所定の期間内に申請手続きを行うことで、口座残高に応じた金額の分配金を受け取れる可能性があります。ただし、犯人がすでにお金を引き出してしまっていて口座に残高がなければ、この制度による返金は受けられません。そのため、被害に気づいたら一日でも早く金融機関に連絡することが重要です。
被害回復分配金の申請手続きの流れと必要書類
振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の申請は、以下の流れで進めるのが一般的です。手続きには時間と手間がかかりますが、返金の可能性を追求するためには不可欠なステップです。
手続き①:お金を振り込んだ金融機関への迅速な連絡
まず、被害金の振込手続きを行った金融機関(自分の口座がある銀行ではなく、振込先の銀行)の窓口や電話で、支援金詐欺の被害に遭った旨を申告します。このとき、警察への被害届の提出を求められる場合があるため、事前に警察へ相談しておくとスムーズです。申告を受けた金融機関は、口座の取引履歴などを調査し、犯罪利用の疑いがあれば口座を凍結します。
手続き②:申請書の記入と提出(本人確認書類・振込記録の写し等)
振込先の金融機関が口座を凍結した後、預金保険機構のサイトでその口座に関する公告が開始されます。被害者は、公告期間中(通常30日以上)に、その金融機関に対して被害回復分配金の支払いを申請します。申請には、金融機関所定の申請書に加え、以下の書類が必要となるのが一般的です。(※申請書の記入例はゆうちょ銀行のサイトなどで確認できます)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込の事実がわかる資料の写し(振込明細書、通帳の該当ページなど)
- 警察に被害届を提出した場合は、その受理番号がわかる資料
申請後、金融機関による審査を経て、分配額が決定され、指定の口座に振り込まれます。
返金請求は弁護士や司法書士への相談も有効な手段
詐欺の被害金を取り戻す方法は、振り込め詐欺救済法だけではありません。犯人が特定できた場合には、弁護士を通じて直接、不法行為に基づく損害賠償請求(返金請求)を行うという方法があります。また、前述の救済法の手続きも、個人で行うには複雑で時間がかかるため、法律の専門家である弁護士に依頼することで、よりスムーズかつ有利に進められる可能性が高まります。
弁護士に依頼すれば、証拠の収集から金融機関とのやり取り、犯人との交渉や訴訟手続きまで、返金に向けた一連のプロセスを代行してもらえます。特に、詐欺業者が海外にいる場合や、複数の決済手段が使われている複雑なケースでは、専門的な知識と交渉力が不可欠です。私たち弁護士法人FDR法律事務所では、支援金詐欺をはじめとするネット詐欺被害に関するご相談を無料で受け付けています。 「返金は無理かもしれない」と諦める前に、一度お気軽にご相談ください。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
返金が困難になりやすいケースも存在する
残念ながら、すべてのケースで返金が成功するわけではありません。以下のような場合は、被害金の回収が困難になる可能性が高くなります。
- 犯人の口座残高がゼロの場合: 振り込め詐欺救済法は、あくまで口座に残っているお金を分配する制度のため、すでに全額引き出されている場合は返金されません。
- 電子マネーで支払った場合: 電子マネーは匿名性が高く、犯人の特定や資金の追跡が非常に困難なため、返金は極めて難しいのが現状です。
- 証拠が不十分な場合: 相手とのやり取りや支払いの記録が残っていないと、被害の事実を客観的に証明することが難しくなります。
- 被害から時間が経過しすぎている場合: 口座が解約されたり、証拠が散逸したりするだけでなく、損害賠償請求権の時効(被害と加害者を知った時から3年)が成立してしまう可能性があります。
だからこそ、被害に気づいたらすぐに証拠を保全し、専門家に相談するなど、迅速に行動を起こすことが何よりも大切なのです。
もう騙されない!支援金詐欺サイトから身を守るチェックリスト

支援金詐欺の被害を未然に防ぐためには、詐欺師の手口を知り、怪しいサインにいち早く気づくことが重要です。ここでは、日頃から実践できる詐欺サイトやメールの見分け方を、具体的なチェックリスト形式で紹介します。
- 怪しい支援金詐欺サイトのURLやデザインの共通点
- 支援金詐欺メールの不自然な日本語や送信元アドレスを見抜く
- LINEで友達追加を求められたら公式マークの有無を確認する
怪しい支援金詐欺サイトのURLやデザインの共通点
詐欺サイトには、本物のサイトとは異なるいくつかの特徴があります。サイトにアクセスしてしまった際は、以下の点を確認し、一つでも当てはまれば詐欺を疑いましょう。
| チェック項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| URLの文字列 | http://で始まっている(暗号化されていない)。正規のサイトと微妙に違う(例: goverment→goverment)。意味のない文字列の羅列になっている。 |
| ドメイン | .xyz .top .bizなど、見慣れないドメインが使われている。 |
| サイトのデザイン | 全体的にデザインが安っぽい。画像の解像度が低い。ロゴが本物と少し違う。 |
| 会社概要の有無 | 運営会社の情報(住所、電話番号)が記載されていない、または記載されていても虚偽の情報である。 |
| 過剰な煽り文句 | 「今すぐ手続きしないと権利が失効します!」など、異常に緊急性を煽ってくる。 |
| 個人情報の入力 | 必要以上に詳細な個人情報(家族構成など)や金融機関の暗証番号などを求めてくる。 |
これらのポイントを総合的に見て、少しでも「おかしい」と感じたら、すぐにそのサイトを閉じ、個人情報の入力や支払いに応じないようにしてください。
支援金詐欺メールの不自然な日本語や送信元アドレスを見抜く
詐欺師から送られてくるメールにも、見分けるためのヒントが隠されています。メールを開いてしまった場合は、以下の点に注意して詐欺かどうかを判断しましょう。
| チェック項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| 送信元のメールアドレス | 公的機関や企業を名乗っているのに、フリーメール(@gmail.com, @yahoo.co.jpなど)や意味不明な文字列のドメインが使われている。 |
| 件名 | 「当選おめでとうございます」「【重要】支援金送金のお知らせ」など、射幸心を煽る、または緊急性が高いと思わせる件名。 |
| 本文の日本語 | 「てにをは」の使い方がおかしい、句読点が不自然、漢字の変換ミスが多いなど、日本語として違和感がある。 |
| 宛名 | 「お客様へ」「会員様へ」のように、個人名での宛名になっていない。 |
| 添付ファイル | 不審な実行ファイル(.exe)や圧縮ファイル(.zip)が添付されている。 |
特に、海外の詐欺グループが翻訳ソフトを使ってメールを作成している場合、不自然な日本語になる傾向があります。本文の表現に少しでも違和感を覚えたら、詐欺メールである可能性が高いと判断し、記載されているURLや添付ファイルは絶対に開かずに削除しましょう。
LINEで友達追加を求められたら公式マークの有無を確認する
近年では、LINEを悪用した詐欺も急増しています。企業や有名人を名乗るアカウントから突然メッセージが届き、友達追加を求められるケースが典型的です。このような場合、そのアカウントが本物かどうかを慎重に見極める必要があります。
最も簡単な確認方法は、アカウント名の横に「公式マーク(緑色や紺色の盾のマーク)」が付いているかどうかです。このマークは、LINE社が審査を行い、認証した公式アカウントにのみ付与されます。もし、大手企業や有名人を名乗っているにもかかわらず公式マークが付いていない場合は、なりすましの偽アカウントである可能性が極めて高いと言えます。
また、個人名のアカウントから「代理で連絡しています」といったメッセージが届く場合も詐欺の典型的な手口です。安易に友達追加をしたり、指示に従って個人情報を送ったりしないようにしてください。不審なアカウントは、友達追加せずにブロック・通報するのが最も安全な対処法です。
支援金詐欺は一人で悩まず専門家へ相談を
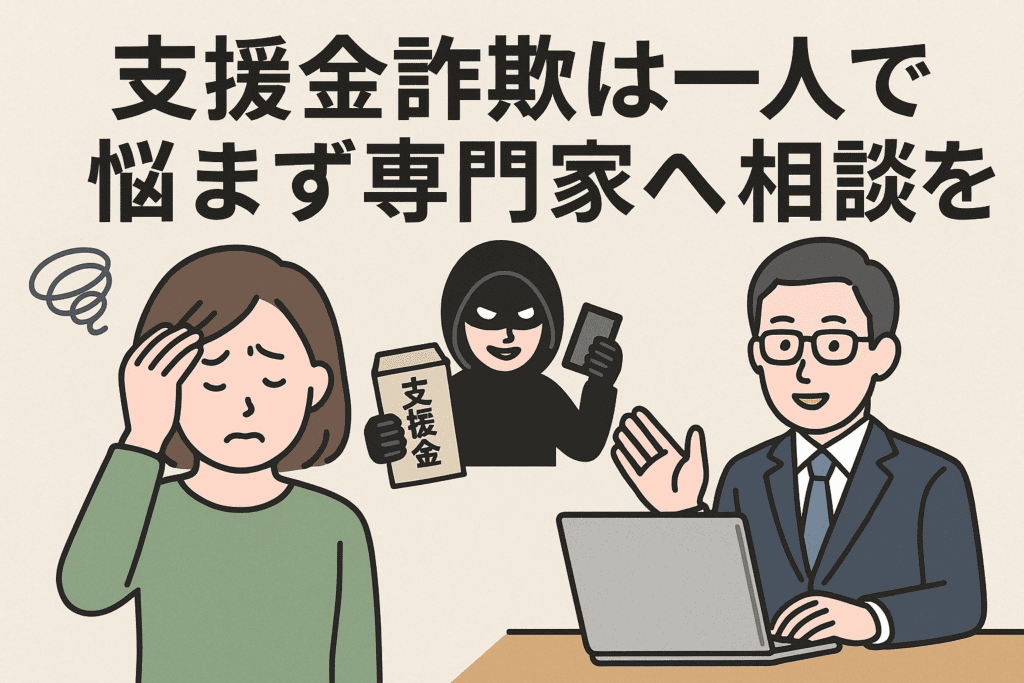
この記事では、支援金詐欺・当選金詐欺の巧妙な手口から、被害に遭った際の具体的な対処法、そして返金手続きの方法までを詳しく解説してきました。
詐欺の手口は日々進化しており、どんなに気をつけていても、一瞬の隙を突かれて被害に遭ってしまう可能性は誰にでもあります。「まさか自分が」と思っていても、実際に被害に遭うと、冷静な判断ができなくなり、パニックに陥ってしまうものです。
もし、あなたが支援金詐欺の被害に遭い、どうすればいいか分からず一人で悩んでいるのであれば、どうか諦めないでください。最も重要なのは、一人で抱え込まず、できるだけ早く専門家に相談することです。
私たち弁護士法人FDR法律事務所は、これまで数多くの支援金詐欺やネット詐欺の被害相談を受け、解決に導いてきた実績があります。被害金の返金請求には、法律の専門知識と経験が不可欠です。迅速に行動すれば、大切なお金を取り戻せる可能性は決してゼロではありません。
当事務所では、詐欺被害に関するご相談を無料で受け付けております。 被害の状況を詳しくお伺いし、返金の可能性があるか、どのような手続きを進めるべきか、専門家の視点から具体的なアドバイスをさせていただきます。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずは、あなたの状況をお聞かせください。解決への第一歩を、私たちが全力でサポートします。
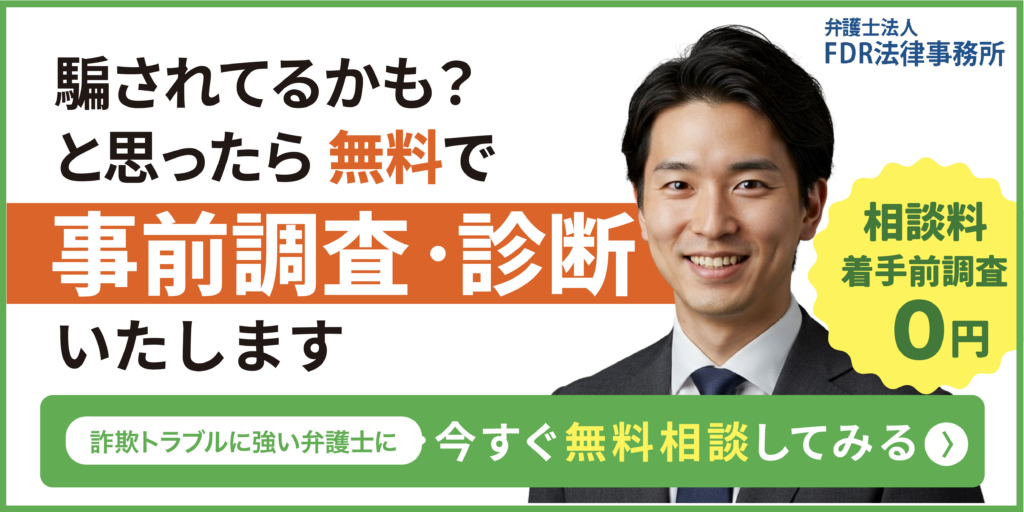
\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます


