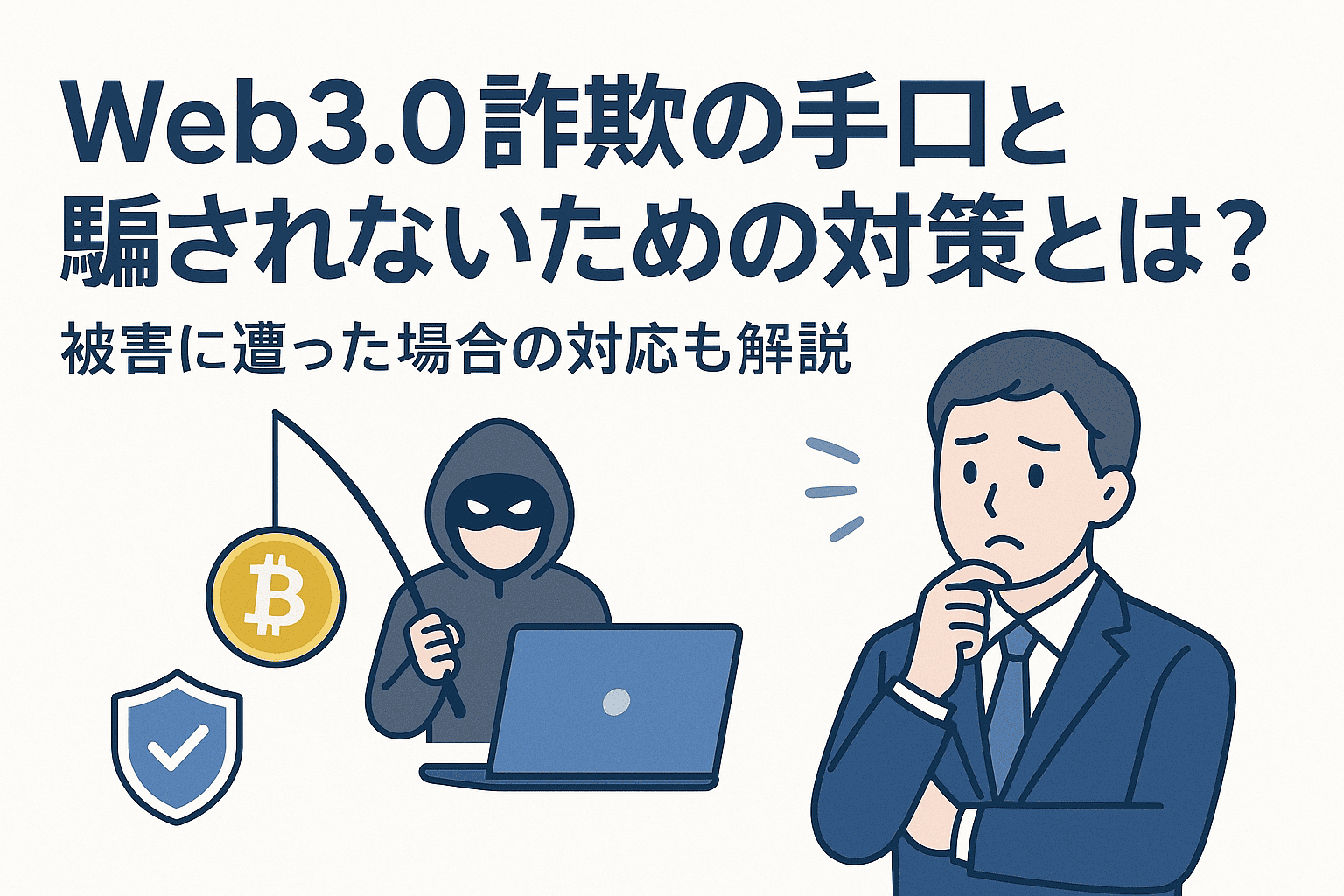近年、暗号資産やNFT、DeFiなどの新しい技術が広がる中で、web3.0詐欺による被害が日本国内でも急増しています。SNSやマッチングアプリをきっかけに投資話を持ちかけられた、出金できない状況が続いている、税金や手数料の支払いを要求された――そんな経験をしていませんか。
web3は革新的な可能性を秘めていますが、その匿名性や仕組みの複雑さを悪用したweb3詐欺は巧妙かつ国境を越えて行われるため、被害の回復が難しいケースも少なくありません。知らない間に資産や個人情報を奪われる危険性もあります。
本記事では、最新のweb3.0詐欺の手口と特徴、日本国内で実際に起きている被害事例、そして被害を防ぐための実践的な対策をわかりやすく解説します。さらに、もし被害に遭ってしまった場合の初動対応や相談先、証拠の残し方も具体的にご紹介。
「もしかして自分も…?」と少しでも不安を感じている方は、ぜひ最後まで読んで、今日から取れる安全対策を実践してください。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
web3.0詐欺とは何か?その危険性とは
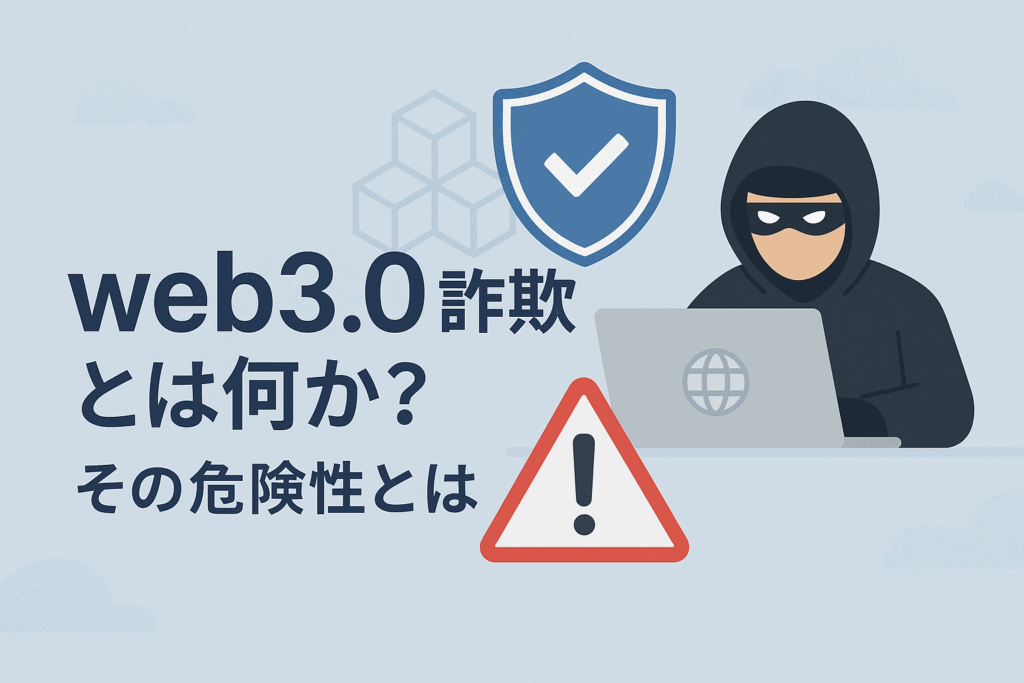
Web3.0詐欺とは、ブロックチェーン技術を基盤とする新しいインターネットの世界(Web3.0)に関連した詐欺行為の総称です。この詐欺は、暗号資産(仮想通貨)やNFTといったデジタル資産をターゲットにしており、その手口は年々巧妙かつ多様化しています。
この分野で詐欺が横行する背景と、実際にどのような被害が起きているのかを理解することが、ご自身の資産を守るための第一歩です。具体的には、以下の3つのポイントからWeb3.0詐欺の全体像を掴んでいきましょう。
- web3詐欺の代表的な手口と特徴
- 日本国内で増加している被害事例
- なぜweb3.0詐欺が急増しているのか
web3詐欺の代表的な手口と特徴
Web3.0詐欺の最大の特徴は、ブロックチェーン技術の「匿名性」や「取引の不可逆性(一度送金すると取り消しが困難)」といった性質を悪用している点にあります。一度だまし取られてしまうと、犯人の特定や被害金の回復が非常に難しいのが現実です。
代表的な手口としては、SNSなどを通じて恋愛感情や信頼関係を築き、投資名目で金銭をだまし取る「ロマンス投資詐欺」、有名プロジェクトの公式サイトを模倣した偽サイトへ誘導し、ウォレット情報を盗み取る「フィッシング詐欺」、そしてプロジェクト運営者が投資家から集めた資金を持ち逃げする「ラグプル」などが挙げられます。
これらの手口は単独で行われるだけでなく、複合的に組み合わされることも少なくありません。詐欺師は、Web3.0の技術的な複雑さや、大きな利益を得たいという投資家の心理巧みに利用してきます。そのため、利用者一人ひとりが「自分の資産は自分で守る」という意識を持ち、手口のパターンを学んでおくことが極めて重要になります。
日本国内で増加している被害事例
Web3.0詐欺は海外だけの問題ではなく、日本国内でも被害が深刻化しています。特に、SNSを通じて著名人や実業家になりすまし、投資を勧誘する「SNS型投資詐欺」の被害は急増しており、警察庁の発表によると、2023年の被害額は過去最悪の約277.9億円にのぼりました。
具体的な事例としては、「有名実業家が主催する投資勉強会」と称するLINEグループに招待され、アシスタントを名乗る人物の指示通りに偽の暗号資産取引プラットフォームへ入金した結果、全額出金できなくなったというケースが多発しています。
また、国民生活センターにも「マッチングアプリで知り合った相手に勧められて海外の取引所で暗号資産を購入したが、出金しようとすると高額な税金の支払いを要求された」といった相談が数多く寄せられています。これらの事例からも分かる通り、Web3.0詐欺は決して他人事ではなく、誰の身にも起こりうる身近な脅威となっているのです。
なぜweb3.0詐欺が急増しているのか
Web3.0詐欺がこれほどまでに急増している背景には、主に3つの要因が考えられます。
第一に、技術の複雑さと発展途上である点です。ブロックチェーンやスマートコントラクト、ウォレットの仕組みは専門的で、一般のユーザーがそのすべてを正確に理解するのは容易ではありません。詐欺師はこの情報格差を突き、もっともらしい専門用語を並べ立てて利用者を巧みに信用させます。
第二に、法整備や規制が追いついていない点です。Web3.0は国境を越えてサービスが展開されるため、日本の法律だけでは取締りが難しいケースが多く存在します。特に海外に拠点を置く無登録の暗号資産交換業者を利用した詐欺の場合、被害回復はさらに困難になります。この点については、デジタル庁のWeb3.0研究会報告書でも利用者保護が喫緊の課題であると指摘されています。
そして第三に、大きな利益への過度な期待感です。「億り人」といった言葉に象徴されるように、暗号資産投資で莫大な利益を得たという話が広まり、多くの人が「自分も乗り遅れたくない」という焦りを感じています。詐欺師はこうした射幸心を煽り、冷静な判断力を失わせて高リスクな投資へと誘導するのです。
web3.0詐欺の典型パターン
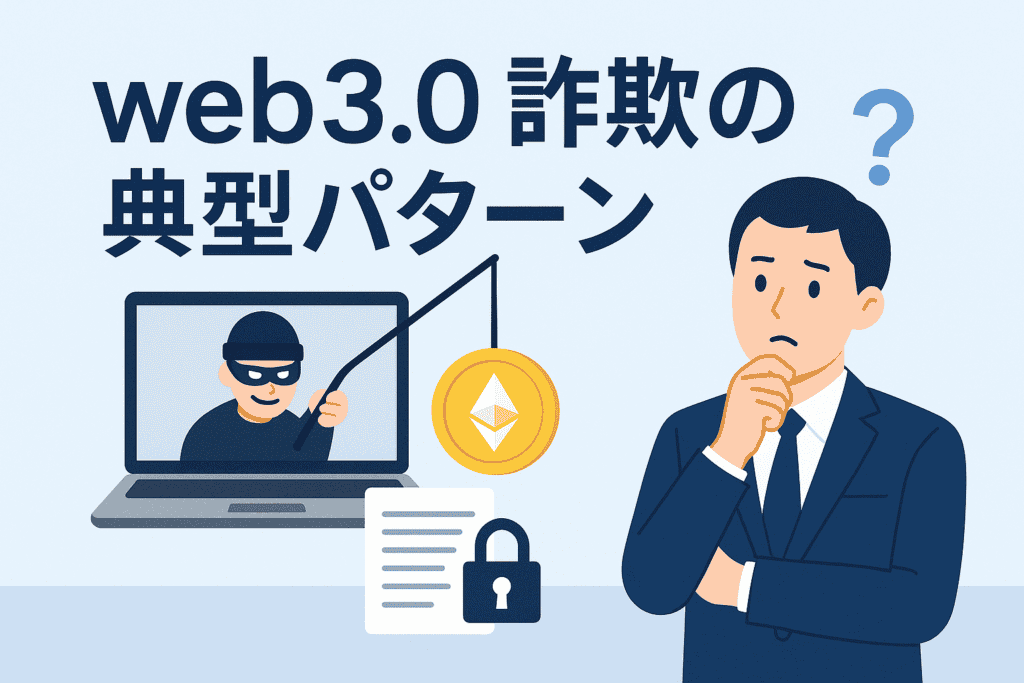
Web3.0詐欺には、いくつかの典型的なパターンが存在します。詐欺師がどのようなシナリオで金銭をだまし取ろうとするのか、その手口を知っておくことは、被害を未然に防ぐ上で非常に有効です。ここでは、特に被害報告の多い代表的なパターンを解説します。
- ロマンス投資詐欺(SNS・マッチングアプリ型)
- NFT詐欺(偽ミントサイト・フィッシング)
- ラグプル(プロジェクト運営の持ち逃げ)
- 無登録暗号資産交換所への誘導
- 税金・手数料の先払い要求
ロマンス投資詐欺(SNS・マッチングアプリ型)
ロマンス投資詐欺は、SNSやマッチングアプリでターゲットに接触し、恋愛感情や親近感を抱かせた上で投資に誘導し、金銭をだまし取る極めて悪質な手口です。犯人は長期間にわたってターゲットとコミュニケーションを取り、信頼関係をじっくりと構築するのが特徴です。
信頼関係が十分に築かれたと判断すると、犯人は「二人の将来のために一緒に投資を始めよう」「自分が儲かっている特別な方法を教える」などと持ちかけ、偽の投資サイトやアプリを紹介してきます。ターゲットは相手を信じ込んでいるため、言われるがままに多額の資金を入金してしまいます。
初めは少額の利益が出て出金できる場合もありますが、それは信用させるための罠です。ターゲットがさらに高額の資金を投入した後、突然サイトが閉鎖されたり、相手と連絡が取れなくなったりして、初めて詐欺だと気づくケースが後を絶ちません。恋愛感情という人の心の隙につけ込む、非常に卑劣な犯罪です。
NFT詐欺(偽ミントサイト・フィッシング)
NFT(非代替性トークン)の人気に便乗した詐欺も多発しています。その代表格が、偽のミントサイト(NFTを新規発行・購入するサイト)を利用したフィッシング詐欺です。
詐欺師は、人気NFTプロジェクトの公式サイトや、X(旧Twitter)、Discordなどをそっくりに真似た偽のウェブサイトを作成します。そして、「サプライズミント」「限定セール」などと称してDMや投稿で偽サイトのURLを拡散し、ユーザーを誘導します。
ユーザーが偽サイトとは知らずにウォレットを接続し、購入ボタン(実際は資産を抜き取るための不正なトランザクション)をクリックしてしまうと、ウォレット内にある暗号資産やNFTがすべて盗まれてしまいます。公式からのアナウンスではない安易なリンククリックや、「フリーミント(無料発行)」といった甘い言葉には、常に警戒心を持つことが重要です。
ラグプル(プロジェクト運営の持ち逃げ)
ラグプル(Rug Pull)とは、暗号資産プロジェクトの運営チームが、投資家から集めた資金を意図的に持ち逃げする詐欺行為を指します。カーペット(Rug)を勢いよく引く(Pull)と、その上に乗っている人が転んでしまう様子になぞらえられています。
この手口は、特にDEX(分散型取引所)に上場されたばかりの新しいプロジェクトで多く見られます。運営チームは、SNSなどでプロジェクトの将来性を過大に宣伝し、投資家から資金を集めてトークンの価格を吊り上げます。そして、価格が十分に高騰したタイミングで、運営が保有する大量のトークンを売却し、資金プールから流動性(例:イーサリアムなど)を引き抜いて逃亡します。
その結果、トークンの価格はほぼ無価値となり、残された投資家は大きな損失を被ることになります。プロジェクトの公式サイトやホワイトペーパーの内容が薄い、運営チームの経歴が不明確であるといった場合は、ラグプルのリスクが高いと判断し、投資を避けるべきでしょう。
無登録暗号資産交換所への誘導
日本国内で暗号資産交換業を行うには、金融庁への登録が法律で義務付けられています。しかし、詐欺師は海外に拠点を置く無登録の業者を使い、高額なレバレッジや非現実的なボーナスキャンペーンを謳って利用者を誘導します。
これらの無登録業者は、最初は少額の出金に応じることで利用者を安心させますが、利用者が多額の資金を入金すると、様々な理由をつけて出金を拒否し始めます。例えば、「システムメンテナンス中」「マネーロンダリングの疑いがあるため口座を凍結した」といった言い訳を使い、最終的には連絡が取れなくなります。
海外の無登録業者は日本の法律の適用が及ばず、一度トラブルになると被害回復は極めて困難です。取引を行う前には、必ず金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」を確認し、登録済みの安全な事業者を利用することが鉄則です。
税金・手数料の先払い要求
これは、偽の取引サイトや投資プラットフォームで利益が出ているように見せかけ、その利益を出金させようとする利用者に対して「税金」や「手数料」といった名目で追加の支払いを要求する手口です。
例えば、「利益分の20%を税金として先に納付しなければ、システム上出金できない」「口座のロックを解除するために、保証金が必要だ」などと、もっともらしい理由をつけて送金を迫ります。しかし、これはすべて嘘であり、一度支払ってしまうとそのお金が返ってくることはありません。さらに支払いを続けると、被害は雪だるま式に膨らんでいきます。
正規の暗号資産取引所では、取引手数料などは利益の中から差し引かれるのが一般的です。出金のために、外部のウォレットから別途送金を要求されることは絶対にありません。「出金のための先払い」を要求された時点で、それは詐欺であると断定し、絶対に応じてはいけません。
よく使われる勧誘文句と心理操作のパターン
詐欺師は、人間の心理を巧みに操る言葉を使ってきます。以下のような勧誘文句を見聞きした場合は、詐欺の可能性が非常に高いと考え、警戒レベルを最大限に引き上げてください。
- 「元本保証」「絶対に儲かる」「月利30%」: 投資の世界に「絶対」はありません。このような高利回りを保証する表現は、出資法に違反する可能性のある典型的な詐欺の謳い文句です。
- 「あなただけに紹介する特別な情報です」: 特別感を演出し、冷静な判断を失わせようとする手口です。本当に有益な情報であれば、不特定多数に安易に広めることはありません。
- 「今すぐ決断しないと乗り遅れる」「期間限定のチャンス」: 焦燥感を煽り、考える時間を与えずに契約させようとする常套句です。
- 「みんなやっているから大丈夫」: 同調圧力を利用し、集団心理に訴えかける手口です。他人がやっているからといって、安全であるとは限りません。
web3.0詐欺の被害を受けたかもしれないときの判断基準
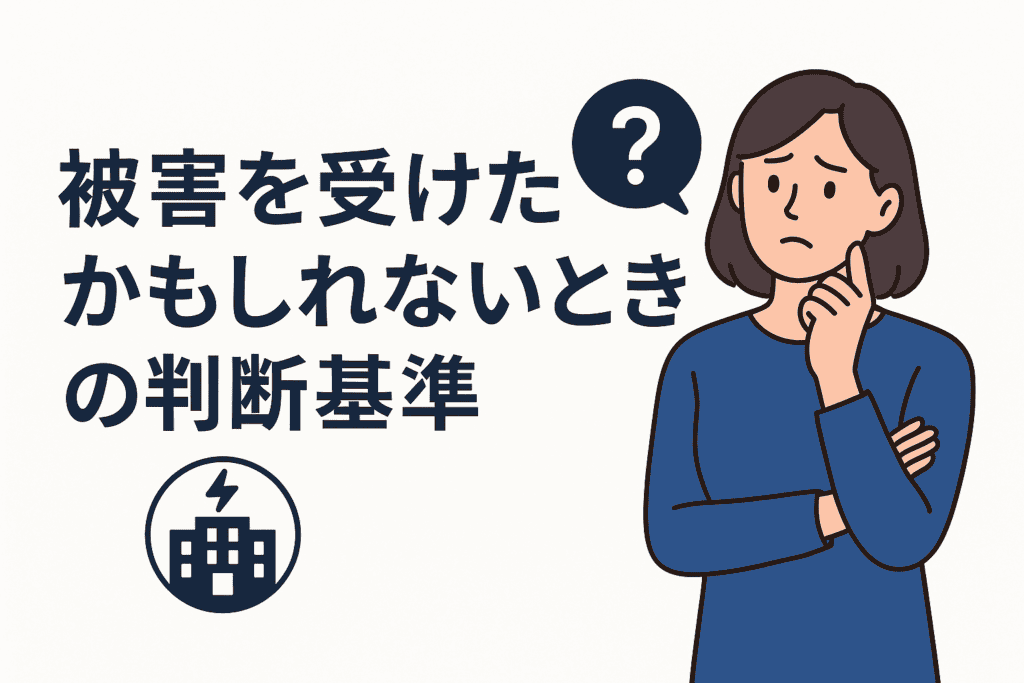
「もしかして、自分は詐欺に遭っているのではないか?」と少しでも感じたら、まずは冷静に状況を客観視することが重要です。感情的になって追加の入金をしてしまうと、被害はさらに拡大してしまいます。
ここでは、詐欺の可能性を判断するための具体的なチェックリストと、安全な事業者を見分けるための方法について解説します。
- 詐欺の可能性を確認するチェックリスト
- 安全な取引所・危険な取引所の見分け方
詐欺の可能性を確認するチェックリスト
もし、ご自身の状況が以下の項目に一つでも当てはまる場合は、詐欺被害に遭っている可能性が非常に高いと言えます。すぐに専門家への相談を検討してください。
- SNSやマッチングアプリで知り合った相手から投資を勧められた
- 「元本保証」や「絶対に儲かる」といった説明を受けた
- 日本の金融庁に登録されていない海外の取引所を利用するよう指示された
- 利益を出金しようとしたら、税金や手数料、保証金などの名目で追加の支払いを要求された
- 運営会社の情報(所在地、連絡先)が不明確、または存在しない
- 担当者とLINEや個別のチャットでしか連絡が取れない
- 解約や出金を申し出ると、高額な違約金を請求されたり、脅されたりした
- 消費者金融などからの借金を勧められ、投資資金にするよう指示された
これらの項目は、典型的な投資詐欺で共通して見られる危険なサインです。希望的観測で「自分だけは大丈夫」と思い込まず、客観的な事実に基づいて冷静に判断することが、被害の拡大を防ぐために不可欠です。
安全な取引所・危険な取引所の見分け方
Web3.0の世界で安全に資産を管理するためには、利用する取引所やサービスが信頼できるかどうかを見極めることが最も重要です。安全な取引所と危険な取引所には、明確な違いがあります。
| 観点 | 安全な取引所の特徴 | 危険な取引所・詐欺サイトの特徴 |
|---|---|---|
| 登録・認可 | 金融庁の「暗号資産交換業者」として登録されている | 無登録。海外法人であることを強調する場合が多い |
| 運営者情報 | 会社の所在地、代表者名、連絡先が明確に公開されている | 運営者情報が不明確、または虚偽の情報を記載している |
| 資産管理 | 会社の資産と顧客の資産を分けて管理(分別管理)している | 分別管理がされておらず、運営資金と混同されている |
| セキュリティ | 二段階認証、コールドウォレット管理など高度な対策を講じている | セキュリティ対策が不十分、または説明がない |
| 勧誘方法 | 過度なリターンを約束せず、リスクについて明記している | 「元本保証」「高利回り」など非現実的なリターンを強調する |
| サポート体制 | 日本語での問い合わせ窓口があり、対応が迅速・丁寧 | 連絡先がチャットのみ、返信がない、日本語がおかしい |
最も簡単で確実な見分け方は、金融庁への登録の有無を確認することです。魅力的なキャンペーンや高い利回りを謳うサービスがあっても、まずは登録業者であるかどうかのファクトチェックを怠らないようにしましょう。
金融庁登録業者の確認手順と注意点
利用しようとしている、あるいは利用中の暗号資産交換業者が金融庁に登録されているかどうかは、以下の手順で誰でも簡単に確認できます。
- 金融庁の公式サイトにアクセスする 金融庁のウェブサイト内にある「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページを開きます。
- 「暗号資産交換業者登録一覧」を確認する 一覧の中から「暗号資産交換業者」の項目を探し、PDFまたはExcelファイルを開きます。
- 事業者名を照合する 一覧に、利用している(または利用を検討している)事業者の正式名称が記載されているかを確認します。
【注意点】 詐欺業者は、正規の登録業者の名称やロゴを無断で使用して、あたかも登録業者であるかのように見せかけることがあります。必ず金融庁の公式サイトにある最新の正規リストで確認するようにしてください。また、リストに記載があっても、その業者を名乗る偽サイトや偽アプリの可能性もあるため、公式サイトのURLはブックマークからアクセスするなど、細心の注意が必要です。
web3.0詐欺で被害に遭った場合の初動対応
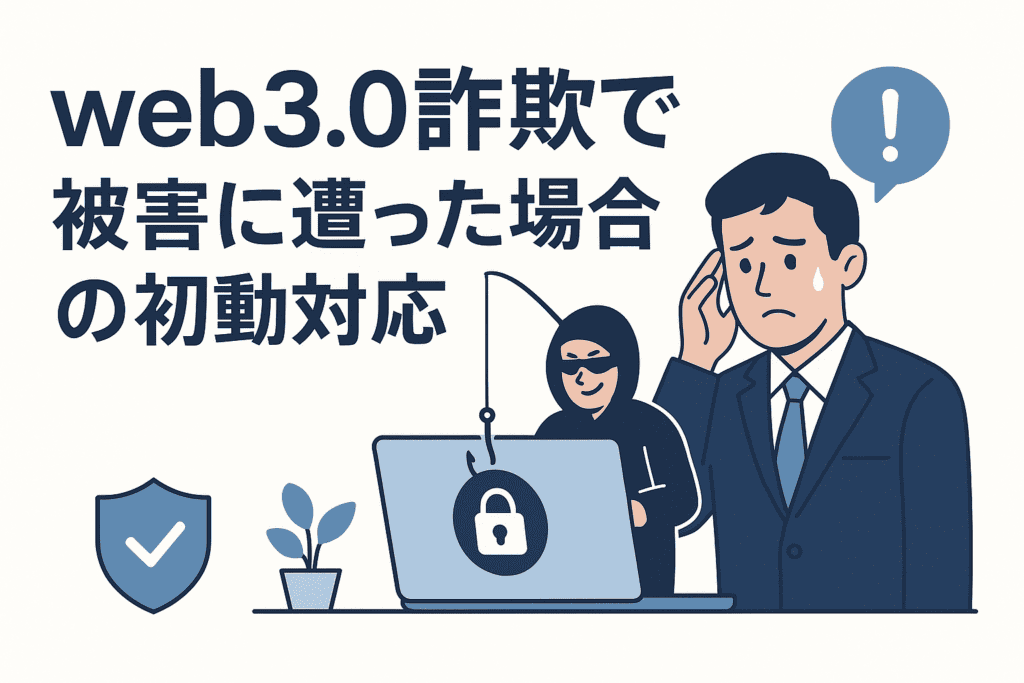
万が一、Web3.0詐欺の被害に遭ってしまったと気づいた場合、パニックにならずに冷静に行動することが、被害の拡大を防ぎ、将来的な被害回復の可能性を高める上で極めて重要です。
ここでは、被害に気づいた直後に取るべき具体的な初動対応について解説します。
- 追加送金を止めるための即時行動
- 証拠の残し方と保存方法
- ウォレットやアカウントの防御策
追加送金を止めるための即時行動
被害に気づいた時点で、詐欺師との金銭的なやり取りは完全に停止してください。詐欺師は、被害者がお金を取り戻したいという心理につけ込み、「システムエラーの解除料」「出金手数料」など、様々な名目をつけてさらなる送金を要求してきます。
しかし、それらはすべて被害を拡大させるための嘘です。一度でも支払いに応じてしまうと、「この相手はまだお金を出す」と判断され、要求はエスカレートしていきます。たとえ脅迫めいた言葉を投げかけられたとしても、絶対に追加の送金には応じないでください。
可能であれば、相手との連絡を完全に絶つことも有効です。LINEやチャットアプリをブロックし、着信を拒否するなど、毅然とした態度で関係を断ち切ることが、被害の連鎖を食い止めるための最も重要な行動です。冷静さを失わず、まずはこれ以上の金銭的被害を防ぐことを最優先に行動してください。
証拠の残し方と保存方法
被害金の返還請求や警察への被害届提出を行うためには、客観的な証拠が何よりも重要になります。詐欺師は、足がつくのを恐れてウェブサイトを閉鎖したり、アカウントを削除したりして証拠隠滅を図るため、気づいた時点ですぐに、関連するあらゆる情報を保存してください。
証拠がなければ、被害の事実を立証することが非常に困難になります。少しでも関連があるかもしれないと感じたものは、すべて記録・保存しておくという意識が大切です。具体的にどのような情報を残すべきか、次の項目で詳しく見ていきましょう。
これらの証拠は、後の法的手続きにおいて、相手方を特定し、詐欺行為を証明するための強力な武器となります。面倒に感じるかもしれませんが、将来の被害回復のために、できる限り網羅的に収集・整理しておきましょう。
画面キャプチャ・取引履歴・やり取りの保存
保存すべき証拠は多岐にわたります。以下のリストを参考に、漏れなくデータを確保してください。
- 相手とのやり取りの記録:
- LINE、Telegram、WhatsAppなどのチャット履歴(最初から最後まで全て)
- メールの送受信履歴
- マッチングアプリ上のプロフィールやメッセージ画面
- 相手のSNSアカウントのプロフィール画面
- ウェブサイトの情報:
- 詐欺サイトのURL
- サイトのトップページ、ログインページ、取引画面、残高画面などのスクリーンショット
- 送金の記録:
- 銀行の振込明細書(インターネットバンキングの場合は取引履歴のスクリーンショット)
- 暗号資産を送金した際の取引履歴(トランザクションIDやハッシュ値、送金先アドレスがわかる画面)
- その他:
- 相手の氏名、住所(自称で構いません)、電話番号、アカウントIDなど、相手に関する全ての情報
- 勧誘に使われた広告やウェブサイトのスクリーンショット
これらの情報は、スクリーンショットだけでなく、可能であればPDF形式で保存したり、印刷したりしておくと、より確実な証拠となります。
ウォレットやアカウントの防御策
フィッシング詐欺などでウォレットを不正なサイトに接続してしまった場合や、アカウント情報が漏洩した可能性がある場合は、二次被害を防ぐための防御策を直ちに講じる必要があります。
まず、詐欺サイトに接続してしまったウォレットは、Revoke(リボーク)という作業を行い、サイトへのアクセス許可を取り消してください。「Revoke.cash」などの専門ツールを使えば、自分のウォレットがどのサイトに接続を許可しているかを確認し、個別に許可を取り消すことができます。これにより、残っている資産が勝手に抜き取られるリスクを低減できます。
また、詐欺に関連して使用したウェブサイトやアプリのパスワードは、すべて変更してください。同じパスワードを他のサービスでも使い回している場合は、それらもすべて変更する必要があります。可能であれば、二段階認証(2FA)を設定し、アカウントのセキュリティレベルを最大限に高めておくことを強く推奨します。
web3.0詐欺に関して公的機関や専門家に相談する方法
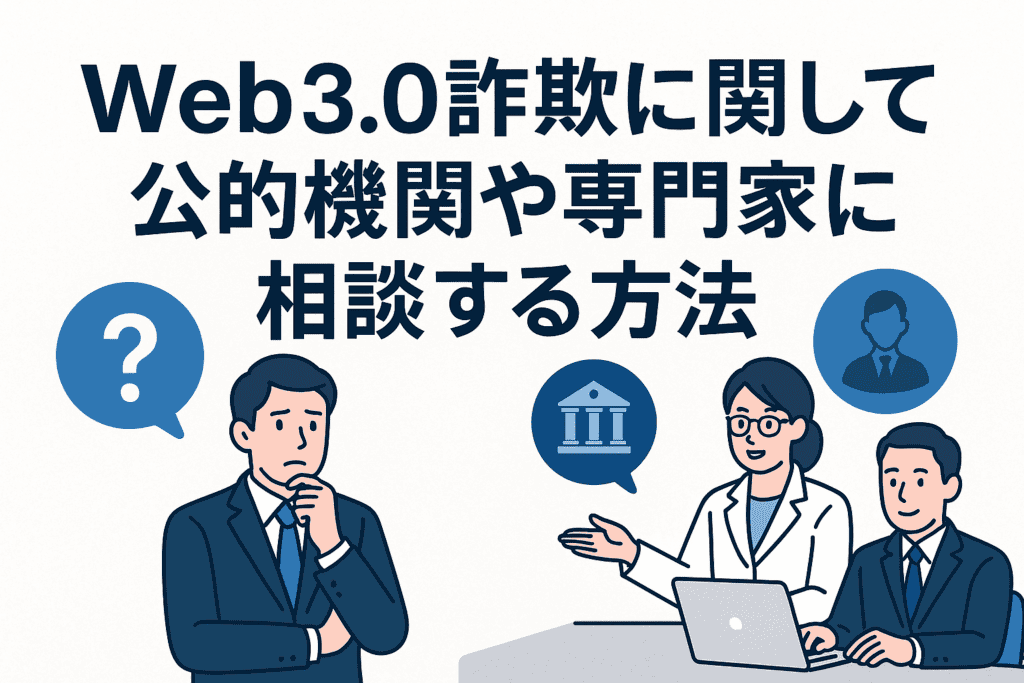
Web3.0詐欺の被害に遭ってしまった場合、一人で悩みを抱え込む必要はありません。日本には、こうした金銭トラブルに対応してくれる公的機関や、被害回復をサポートしてくれる専門家が存在します。
ここでは、具体的な相談先とその役割について解説します。どこに相談すればよいかを知っておくだけで、精神的な負担は大きく軽減されるはずです。
- 消費生活センター(188)への相談手順
- 警察相談窓口(#9110)やサイバー犯罪相談窓口
- 金融庁・財務局への通報と無登録業者リストの活用
- 弁護士に相談するメリット
消費生活センター(188)への相談手順
消費生活センターは、商品やサービスの契約に関するトラブルなど、消費者からの相談を受け付けている公的な機関です。Web3.0詐欺の中でも、特に事業者との間で生じたトラブルについて、今後の対応方法などを助言してくれます。
相談は無料で、局番なしの電話番号「188(いやや!)」にかけることで、最寄りの消費生活センターにつながります。相談員が、被害の状況を丁寧に聞き取り、トラブル解決のためのアドバイスや、他の適切な相談窓口の情報を提供してくれます。
ただし、消費生活センターはあくまで助言や情報提供を行う中立的な機関であり、代理人として相手方と交渉したり、法的な手続きを進めたりすることはできません。しかし、問題を客観的に整理し、次に取るべき行動を明確にする上で非常に役立つ相談先ですので、まずは一度電話してみることをお勧めします。
警察相談窓口(#9110)やサイバー犯罪相談窓口
詐欺は刑法に触れる犯罪行為であり、警察は捜査機関として犯人を検挙する役割を担っています。被害の事実を申告し、犯人の処罰を求める場合は、警察に相談する必要があります。
緊急の事件・事故ではない相談事については、全国共通の警察相談専用電話「#9110」にかけることで、専門の相談員が対応してくれます。また、インターネット上の犯罪については、各都道府県警察に設置されている「サイバー犯罪相談窓口」に相談するのが適切です。
警察に相談し、被害届や告訴状が受理されれば、捜査が開始されます。犯人が検挙されれば、刑事手続きの中で被害弁償が行われる可能性もあります。ただし、警察の主目的はあくまで犯人の検挙であり、被害金の回収を直接代行してくれるわけではない点は理解しておく必要があります。収集した証拠を持参の上、最寄りの警察署に直接出向いて相談することも有効です。
金融庁・財務局への通報と無登録業者リストの活用
利用した業者が金融庁に登録されていない無登録業者であった場合、金融庁や財務局にその情報を通報することができます。金融庁のウェブサイトには「金融サービス利用者相談室」という窓口が設けられており、無登録での金融商品取引業に関する情報提供を受け付けています。
通報したからといって、直接的に自分の被害金が返ってくるわけではありません。しかし、提供した情報が金融庁の注意喚起や行政処分につながり、新たな被害者が生まれるのを防ぐという社会的な意義があります。
また、金融庁は無登録で暗号資産交換業を行っているとして警告を行った業者のリストを公表しています。自分が利用している業者がこのリストに掲載されていないかを確認することも、リスクを判断する上で重要です。貴重な情報源として、これらの公的機関のウェブサイトを定期的に確認することをお勧めします。
弁護士に相談するメリット
被害金の返還を具体的に目指す場合、弁護士への相談が最も有効な手段となります。弁護士は、法律の専門家として、被害回復のために必要となる法的な手続きを代理人として進めることができます。
弁護士に依頼する主なメリットは以下の通りです。
- 相手方の特定: 弁護士会照会などの法的な権限を用いて、振込先の口座情報などから相手方の氏名や住所を調査できる場合があります。
- 交渉・訴訟の代理: 相手方との返金交渉や、裁判所を通じた支払督促、民事訴訟といった法的手続きをすべて任せることができます。
- 精神的負担の軽減: 詐欺師との直接のやり取りや、煩雑な法的手続きから解放され、精神的な負担を大幅に軽減できます。
- 最適な解決策の提案: 被害額や証拠の状況に応じて、費用対効果も踏まえた上で、最も現実的で効果的な解決策を提案してくれます。
Web3.0詐欺は専門性が高く、被害回復のハードルも決して低くありません。だからこそ、この分野に精通した弁護士のサポートが不可欠です。多くの法律事務所では初回無料相談を実施していますので、まずは一度、専門家の意見を聞いてみることを強くお勧めします。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます
web3.0詐欺に遭わないための予防策
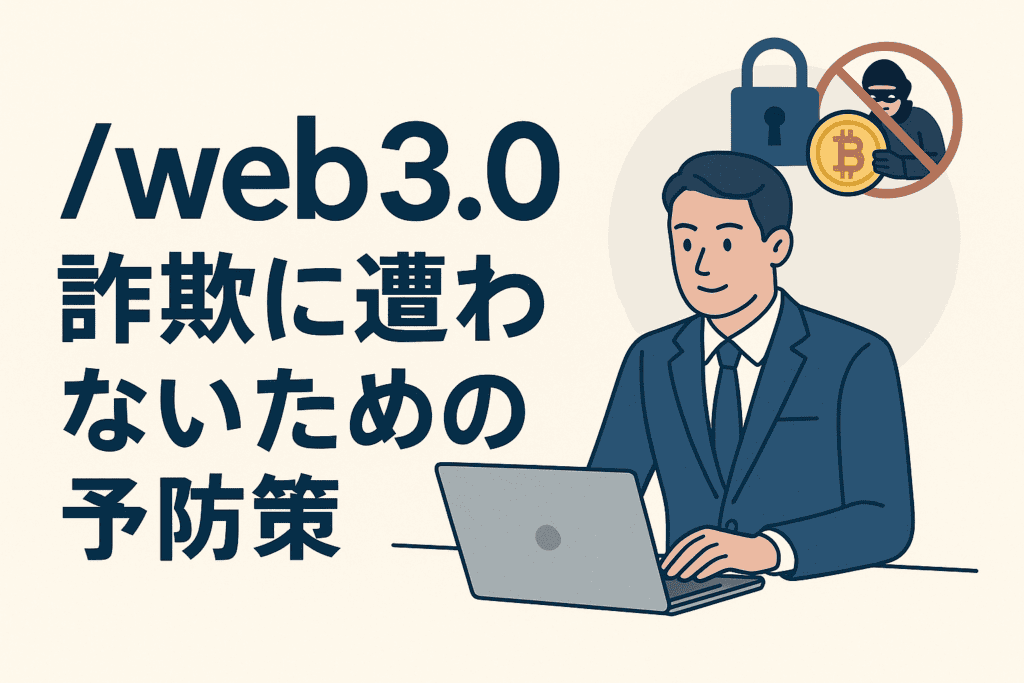
Web3.0詐欺の被害回復は困難を伴うため、何よりも被害に遭わないための「予防」が重要になります。「自分の資産は自分で守る」という意識を常に持ち、日頃から対策を講じることが、安全にWeb3.0の世界を楽しむための鍵となります。
ここでは、今日から実践できる具体的な予防策をご紹介します。
- DMや招待リンクからの投資勧誘を避ける
- 意味を理解しないままの署名やウォレット接続をしない
- 高配当・元本保証をうたう案件に注意する
- 定期的な情報収集と最新手口の把握
DMや招待リンクからの投資勧誘を避ける
X(旧Twitter)やDiscord、LINEなどのDM(ダイレクトメッセージ)を通じて送られてくる見知らぬ相手からの投資の誘いや、お得情報を謳うリンクは、詐欺である可能性が極めて高いと考えましょう。
詐欺師は、魅力的なプロフィール写真や経歴を使い、親しげに話しかけてきますが、その目的はあなたを詐欺サイトへ誘導することです。特に、「あなただけに特別な情報を教えます」「一緒に投資で成功しましょう」といった甘い言葉には絶対に乗ってはいけません。
また、コミュニティ内で共有されるリンクであっても、それが本当に公式のものなのかを慎重に確認する癖をつけてください。安易にリンクをクリックしたり、招待に応じたりすることは、自ら危険に飛び込む行為と同じです。うまい話には必ず裏がある、ということを肝に銘じておきましょう。
意味を理解しないままの署名やウォレット接続をしない
Web3.0の世界では、ウォレットをウェブサイトに接続し、「署名(Sign)」を求められる場面が頻繁にあります。この「署名」は、現実世界における契約書へのサインと同じくらい重要な行為です。
署名をすることで、そのサイトに対して、あなたのウォレット内の資産を操作する許可を与えてしまう場合があります。フィッシングサイトで意味を理解しないまま署名をしてしまうと、ウォレット内の暗号資産やNFTを根こそぎ盗まれてしまう危険性があります。
署名を求められた際には、ポップアップに表示される内容を注意深く確認し、どのような許可を与えようとしているのかを理解するよう努めてください。少しでも怪しい、内容が理解できないと感じた場合は、ためらわずに「拒否」または「キャンセル」を選択する勇気が、あなたの資産を守ります。
高配当・元本保証をうたう案件に注意する
投資の世界において、「元本が保証される」「絶対に損はしない」「月利30%を確約する」といった謳い文句は、100%詐欺であると断言できます。そもそも、金融商品取引法や出資法では、元本を保証して投資を勧誘する行為は原則として禁止されています。
詐欺師は、投資経験の浅い人々の「楽して儲けたい」という心理につけ込み、非現実的なリターンを提示してきます。しかし、ハイリターンには必ずハイリスクが伴うのが投資の原則です。リスクについての説明をせず、メリットばかりを強調するような話は絶対に信用してはいけません。
冷静に考えればあり得ないような好条件を提示された場合は、一度立ち止まり、「なぜ、そんなにうまい話が見ず知らずの自分に回ってくるのだろうか?」と自問自答してみてください。その冷静さが、詐欺被害を防ぐための最も強力なブレーキとなります。
定期的な情報収集と最新手口の把握
Web3.0詐欺の手口は、技術の進歩と共に日々新しく、巧妙になっています。今日安全だった方法が、明日には危険になっているということも十分にあり得ます。そのため、継続的に情報を収集し、最新の詐欺手口やセキュリティ対策について学び続ける姿勢が不可欠です。
信頼できる情報源としては、以下のようなものが挙げられます。
- 金融庁や国民生活センターなどの公的機関が出す注意喚起
- 信頼性の高い暗号資産専門メディアやニュースサイト
- セキュリティ専門家や著名なプロジェクトの公式X(旧Twitter)アカウント
これらの情報源を定期的にチェックし、世の中でどのような詐欺が流行しているのかを把握しておくだけで、多くの危険を回避することができます。知識は、Web3.0の世界を安全に航海するための羅針盤となるのです。
web3.0に関する詐欺被害の相談は弁護士法人FDR法律事務所へ
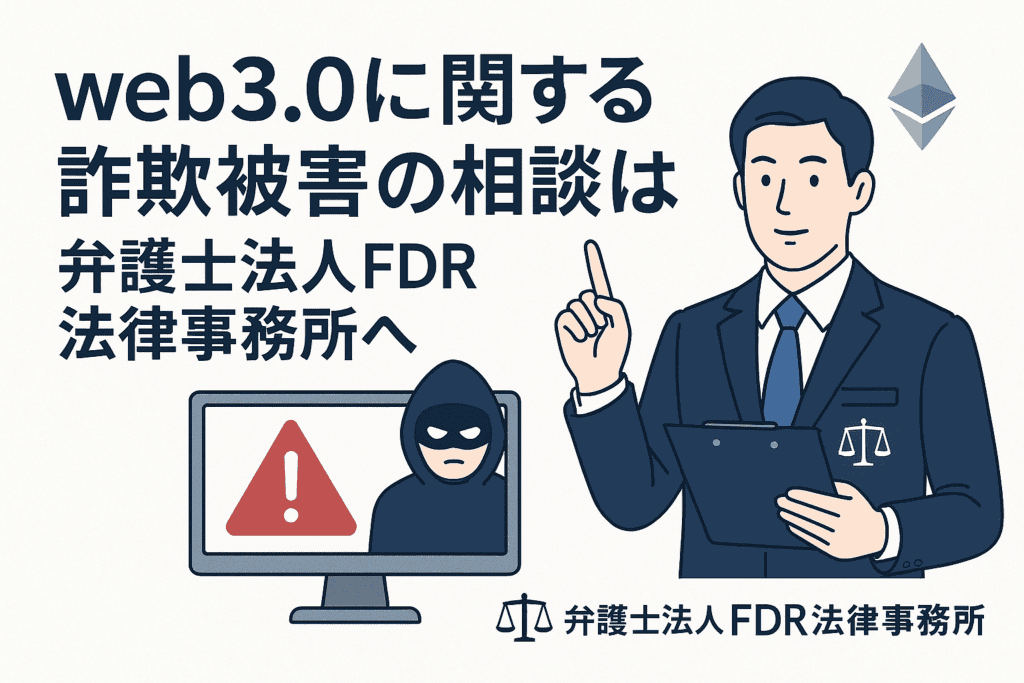
ここまでお読みいただき、Web3.0詐欺の恐ろしさや対策の重要性をご理解いただけたかと思います。しかし、どれだけ注意していても、巧妙な手口にだまされてしまう可能性はゼロではありません。
もし、あなたがWeb3.0詐欺の被害に遭い、一人で悩み、不安な夜を過ごしているのであれば、どうか諦めないでください。私たち弁護士法人FDR法律事務所は、そんなあなたの力になるために存在します。
当事務所には、暗号資産やNFTといったWeb3.0関連の詐欺被害案件を専門的に取り扱うチームがあり、豊富な知識と経験を有しています。被害金の回復に向けて、証拠収集から相手方の調査、交渉、そして訴訟に至るまで、あらゆる法的手続きを駆使して全力でサポートいたします。
「弁護士に相談するのは敷居が高い」と感じるかもしれません。しかし、行動を起こさなければ、大切なお金が戻ってくる可能性は限りなく低くなってしまいます。最初の一歩を踏み出すことが、解決への最大の近道です。
当事務所では、Web3.0詐欺に関するご相談を無料で受け付けております。 一人で抱え込まず、まずは専門家である私たちに、あなたの状況をお聞かせください。被害回復の可能性を診断し、あなたにとって最善の解決策をご提案いたします。
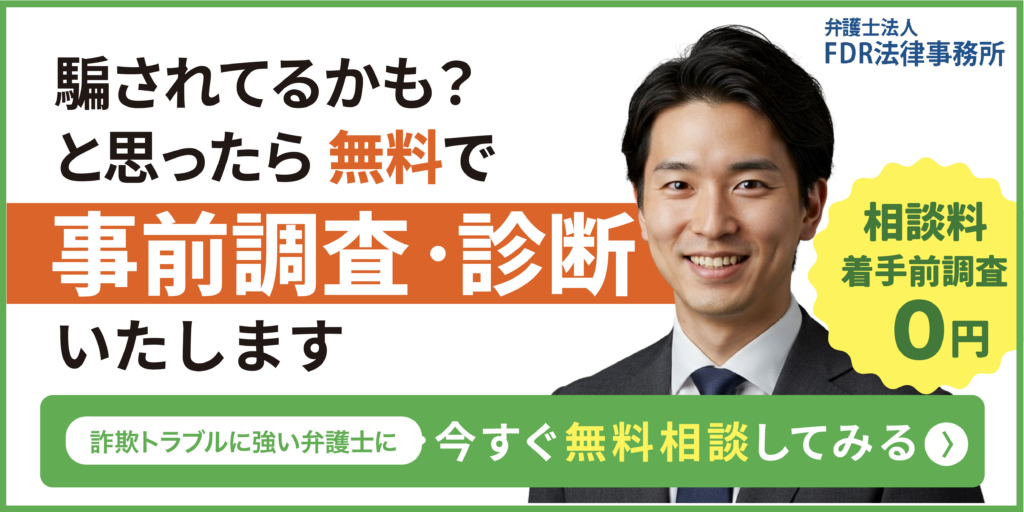
\ 返金請求の可能性をお伝えします! /
※LINEで簡単にご相談いただけます